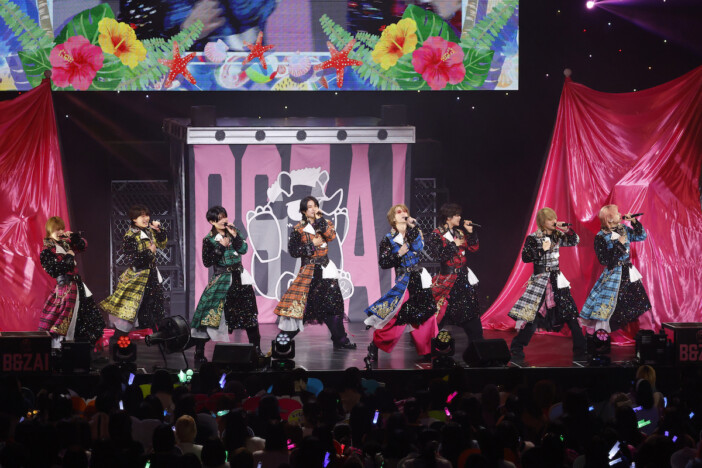androp、ステージを幻想的な空間に染め上げた祝祭の夜 リベンジも果たした5年ぶり日比谷野外大音楽堂公演

今年5月から6月にかけて最新アルバム『effector』を携えたツアー『androp one-man live tour 2022 “effector”』を完走したばかりのandrop。アルバム制作を経て新たなバンド像を築き上げた彼らが今回立った舞台は、自身5年ぶりとなる日比谷野外大音楽堂だ。5年前とは異なるモードで、『androp one-man live 2022 at Hibiya Open-Air Concert Hall』を9月3日に開催した。前回は秋雨に見舞われたが、リベンジ成功ともいうべきか、今年の日比谷上空には一粒の雨粒も零さない晴天が佇んでいた。本公演では、観客を演出の一部とするという試みでドレスコードの指定があり、白系の服を纏った観客で客席が埋め尽くされた。また、メンバーの背後に吊り下げられる多数の鏡、客席中央に設置された巨大ミラーボールなど、セットにも注目が集まった本公演を振り返る。

臨場感のあるSEが流れる中、メンバーがステージ上に姿を現すと、観客はあたたかな拍手で迎え入れる。小刻みなドラムロールが物語のプロローグをなぞっていくかのようなインストナンバーで、本公演の幕は上がった。直後演奏した最新曲「SummerDay」では、ブリージーな内澤崇仁(Vo/Gt)の歌声にあわせて打ち鳴らされる観客の息の合ったハンドクラップが、幸福感に満ちた空間を醸成していく。本楽曲を早々に投下したのは、andropの“今”をこの特別な場所に刻み付けたいといった意思表示によるものであろう。
佐藤拓也(Gt/Key)によるガットギターの情熱的なカッティングとリズミカルなパーカッションの調和で異国情緒漂う「Chicago Boy」を演奏すると、「来てくれてありがとう」と感謝を伝える内澤。鍵盤とサックスが織りなすシネマティックなイントロで場内の空気を一変させた「Koi」では、甘美な歌声で観客の視線をステージ中央に集める。続いて、6月の豊洲PIT公演にも参加したサックス奏者 Juny-aと、サポートキーボードとして迎えた佐藤雄大の2名を紹介し、「次の曲はこの2人からこの雰囲気に合ったぴったりな感じを」と内澤。サックスの色気ある音色にフィーチャーした「Radio」を披露すると、観客は自ずと肩を揺らし、濃密な音世界へ我先にと飛び込んでいく。「Know How」では、佐藤がサンプラーを駆使し奏でるアコギのリフとパーカッションのハネるビートが絡み、立体感のあるグルーヴが場内を駆け巡っていた。


タンバリンが効いた「Traveler」の演奏を終えると、佐藤、伊藤彬彦(Dr)、Juny-aが一旦ステージからはけるのを合図に「リベンジをしたいことがあって」と話し始める内澤。5年前、客席中央のセンターステージで「Tokei」を一人歌い出した瞬間に雨が降り始めたという、ちょっぴり苦い思い出を振り返る。その時のリベンジと称し、ステージ最前にセットされた椅子に座り、丁寧に「Tokei」を歌い上げた。
再びバンド形態に戻り披露した「Moonlight」では、ステージ上部でミラーボールがまわり、くるくると旋回する多数のサーチライトが場内全体を眩く照らす。チルな雰囲気へと誘う「Lonely」のあと、ポストロック直系の耽美な旋律が小気味よい「Water」へ繋ぐ流れも非常にスタイリッシュだ。ちょうどこの辺りの時間帯から本格的に日が落ち始め、「目論見どおりだな」と呟く内澤。今回の野音ライブは“反射”がテーマの一つであることを語り、「あなたの心の中に、今日も明日も綺麗な光が灯っていますように」と披露した「Hikari」では、ステージに吊り下げられた鏡に観客のスマホライトが反射。野音とその周辺が、今夜限りのどこまでもシームレスで美しい光の世界へと変貌を遂げた。
客席中央の巨大ミラーボールを駆使し、会場全体のみならず日比谷公園の木々をも煌びやかで祝祭感のあるムードに染め上げた5年ぶり2度目の野音ライブ。前田恭介(Ba)が操るシンベのグルーヴがスリリングな「Beautiful Beautiful」で描く、緻密なサウンドプロダクションと照明演出の融合から生まれる迫力には思わず息を飲み、続く「Bright Siren」のサビでステージ上全域が最大出力の照明で真っ白に染まる様は、まるで夢の中にいるかのような感覚を呼び起こさせる。