小説『モンパルナス1934~キャンティ前史~』エピソード10 第2次世界大戦 村井邦彦・吉田俊宏 作

第2次世界大戦 #3
紫郎と智恵子、ハールの3人は1939年12月1日、マルセイユ港から諏訪丸に乗り込んだ。ハールの妻アイリーンはしばらくパリに残り、年が明けてから夫に合流するという。日本人の多くはドイツのポーランド侵攻が始まった9月に帰国したが、この船も戦火を逃れて故郷に戻る日本人客でごった返していた。
昨夕、マルセイユのホテルに着くころから冷たいミストラルが吹き荒れ、夜は雨になってさらに冷え込んだ。そのせいか、智恵子は熱を出してホテルで寝込んでしまった。ところが夜が明けてみるとミストラルのミの字も感じさせない快晴で、どこまでも青い地中海が3人を快く迎えてくれた。
「おお、地中海。ラピスラズリのような青。実に神秘的だ。ああ、コダクロームを買っておけば良かったよ。この青さをフィルムに収められないなんて残念でならない。それにしても穏やかな海だね。ヨーロッパが戦争になっているなんて信じられないよ」
湖や川なら何度も経験しているが、船で海に乗り出すのは初めてというハールが、次第に遠ざかっていくマルセイユの港と地中海を交互に眺めながら言った。
「ええ、平和そのものね」
すっかり元気を取り戻した智恵子がうなずいた。
「どうしたの。気分でも悪いの?」
ずっと黙ったままの紫郎の肩に智恵子がそっと手をかけた。
「い、いや、何でもないよ。確かに、今日の地中海はいつになく濃い青だな。カンヌやニースの沖で見てきたエメラルドグリーンとは違って、ちょっと不気味な感じがするね。この青…。群青色と呼ぶべきかな」
紫郎はネクタイを締め直し、まぶしそうに目を細めながら言った。
「群青って、紫の入った青のことね?」
智恵子が紫郎の横顔を見上げて応えた。
「そうか、青と紫か。紫は何色を混ぜればできるんだっけ?」
「青と赤で紫になるはずよ。でも、青い絵の具に赤を混ぜても、なかなかこんな色にはならないわね」
「赤か…」
紫郎はヴァレリーの講演録を思い出していた。解体されて地中海に捨てられたマグロ。コバルトブルーの海に赤黒い液体が混じっていく夢。
考えてみれば、ギリシャやローマの時代から、地中海を舞台に多くの戦いが繰り広げられてきたのだ。サラミスの海戦、アクティウムの海戦、レパントの海戦…。おびただしい数にのぼる船と人と馬と財宝が、この群青の海の底に沈んでいるはずだ。
諏訪丸が東に向かって旋回した。紫郎は西の方角を見て「向こうがスペインだ」と思った。富士子の姿が目に浮かぶ。船員たちの前に颯爽と立ちはだかった後ろ姿が。風になびく長い髪、純白のブラウス、真っ青のスカート、長い脚。
…と、そこでカシャリとシャッターの音が鳴った。ハールのライカだった。紫郎の脳裏のスクリーンから富士子が消え、赤黒い液体の残像だけが残った。
「ああ、やっぱりシローは斜めから、チエは正面から撮るのがベストのようだね。シローは考え事をしている時の顔が一番ハンサムに見えるぞ。ははは。よーし、今のツーショットはきっとうまく撮れているはずだ」
「もう、ハールったら、急に撮るんだから。油断も隙もあったもんじゃないわ。変な顔に写っていたら捨ててちょうだいね」
智恵子がむくれてみせると、ハールと紫郎は同時に笑った。
スエズ運河を通過している時、紫郎はデッキで懐かしい顔を見つけた。エッフェル塔の前で富士子と見間違えた香港からの留学生アグネス・ホーだ。
「やあ、アグネス。久しぶりだね。香港に帰るのかい?」
「あら、シローじゃないの。ええ、香港とパリとどっちが安全か微妙なところだけどね。あなた、近ごろモンパルナスで見かけなくなったから、どうしたのかなと思っていたのよ」
背の高さ、髪の長さは、やはり富士子を思い出させる。
「いろいろと忙しくてね」
「やっぱり日本に帰るの? 富士子さんのお墓参りかしら?」
「墓参り?」
「日本人はお墓参りが大好きだって聞いたわ」
「いや、好きというわけでも…」
墓か。紫郎はどきりとした。そういえば富士子は誰が、どこに葬ったのだろう。日本大使館の参事官の娘、絹江が手配したのか。いや、彼女は父の転勤に伴ってカナダに行ったはずだ。あるいは富士子に言い寄っていた伯爵家の御曹司が手を回したのか。
いや、彼らではなく、自分こそがやるべきではなかったのか。富士子のために。今さらどうしようもないことで、紫郎は自分を責めた。
上海で元日を迎え、3人が神戸港に着いたのは1940年1月5日の朝だった。諏訪丸は横浜港まで行くのだが、あえて途中で下船したのは、挨拶しておくべき相手が神戸にいたからだ。3人は港からタクシーで御影に向かった。山手の豪邸、伊庭簡一宅だ。伊庭家は1938年にカンヌからパリに移った後、1939年春に坂倉と同じ船で帰国していた。
人の背丈ほどの立派な門松を両脇に立てた玄関の呼び鈴を押すと、待ち構えていたかのように勢いよくドアが開き、懐かしい人たちが一斉に飛び出してきた。
「ご無沙汰しております、伊庭さん。あけましておめでとうございます」
「おめでとう。よく来てくれたね」
紫郎が簡一に会うのは1938年の夏にカンヌの伊庭邸を訪ねて以来だ。
「こちらはハンガリー出身の写真家、ハールさんです」
紫郎はフランス語でハールを紹介し、続いて日本語で智恵子を紹介した。智恵子はパリで長男マルセルと次女シモンには会ったことがある。
「シロー、おチエさん、久しぶり。会いたかったよ」
マルセルが紫郎に抱き着いてきた。絹江との仲がうまく行かず、一時はずいぶん落ち込んでいたが、もうすっかり立ち直ったようだ。
「シロー、元気そうね」
「やあ、シモン。きれいになったなあ。もう18歳だもんな」
「19よ」
紫郎は彼女にお年玉を渡した。
「あ、ありがとう。でも、もう子ども扱いしないでよね。お年玉はもらってあげるけど」
シモンが頬を膨らませると、みんなが笑った。
「タローはどうしたの?」
紫郎が訊くと、愛犬は病気がちで、今も姉のエドモンドが正月休み中の獣医に無理を言って診てもらっているのだとシモンが答えた。
「それは心配だね。そういえば、絵の上手なタローはまだパリに残っているよ」
紫郎が言うと、みんなに笑顔が戻った。
「あのね、シローの仲間に岡本太郎っていう美術家がいるのよ。伊庭家のワンちゃんと同じ名前の」
智恵子がハールにフランス語で解説した。
「さあさあ、みなさん、奥に入って。ゆっくりしていってください」
簡一がフランス語で言った。ハールに気を使って、フランス語で通すことにしたようだ。
「わあ、パスティスだ。カンヌでよくいただきましたね。懐かしい。まさか日本でパスティスにありつけるとは。パスティスは夏に飲むのが最高だけど、こうして暖炉の前で飲むのも乙なものですね」
グラスに入った琥珀色の液体は、シモンが水を注ぐと乳白色に変わった。
「うわ、一気に白くなった。マドモワゼル、あなたは魔法使いですか」
ハールがシモンの顔と乳白色の液体を交互に見て目を丸くした。
「ははは、ハールはパスティスを知らないんだね。僕も最初は驚いたよ。ところで伊庭さんは昨年もベルリンに行ってこられたそうですね」
紫郎はパスティスに口をつけてから、簡一に訊いた。
「今年だよ。ああ、いや、もう昨年の話になるか。ちょうどベルリンに着いた日に独ソ不可侵条約が結ばれたんだ。あれには驚いたよ。1週間後にはポーランドに侵攻してしまった。まさに電光石火の早業だった。英国とフランスが宣戦布告したけれど、明らかに後手に回ってしまったね」
と簡一が応えた。
「後手に回った?」
マルセルが身を乗り出した。
「あれは一昨年、1938年の出来事かな、ドイツがオーストリアを併合したのは。圧倒的な軍事力で威圧して、あっけなく併合した。明らかにヴェルサイユ条約違反だよ。歴史のある主権国家が消滅してしまったんだからね。しかし、英国やフランスをはじめ西欧諸国は形式的な抗議しかしなかった。あれでヒトラーは味をしめた。力で押していっても、英国やフランスなどは腰が引けて、力で押し戻そうとはしないと分かってしまったんだ」
簡一が壁に架かっている油彩の風景画を見ながら言った。手前に古代ギリシャかローマ時代の人物が数人、遠景には石造りの神殿が描かれている。作者はニコラ・プッサンだろうか。そうだとすれば模写か。いや、伊庭家のことだから、ひょっとすると本物かもしれないと紫郎は妙なことが気になった。
「ムッシュー・イバ、次にヒトラーが狙ったのがチェコスロヴァキアのズデーテン地方でしたね。あそこは何度か行ったことがあります。ドイツ系の住民が多いのです。ドイツ系住民を保護するため、というのがヒトラーの口実でした」
ハールがすかさず答えた。
「さすが、ハールさん。口実とおっしゃいましたね。その通りです。ヒトラーの目的はドイツ民族の統合と東方生存圏の獲得です。実際、ドイツ系住民を保護するという名目で、次々と東ヨーロッパの国を侵略していきましたね」
簡一はパスティスを一口飲んで言った。
「英国やフランスはズデーテン割譲をめぐるミュンヘン会談でヒトラーの要求を全面的に認めたのですよね。ズデーテンを譲ればヒトラーは満足して、これ以上、傍若無人な侵略はしないとでも思ったのでしょうか」
と紫郎が訊いた。
「あれはまずかったね。ヒトラーに宥和政策なんて甘すぎる。何も分かっちゃいないんだ。案の定、ヒトラーはチェコの西半分を保護領、スロヴァキアを保護国にしてしまった」
簡一は暖炉の横にあるキャビネットから地球儀を取り出してテーブルに置き、東ヨーロッパのあたりを指で追いながら言った。

「はい、ミュンヘン協定は全く意味をなしませんでした。あれで完全に風向きが変わりました。我が祖国ハンガリーもナチスの力を恐れて、ドイツにすり寄るようになりましたしね」
そう言って、ハールは溜め息をついた。
「ハールさん、おっしゃる通りです。その勢いの中でドイツはポーランドに侵攻した。やはり口実の1つは、ポーランド国内で迫害されているドイツ系住民の保護でした。続いてソ連もポーランドに攻め込みましたが、その侵攻理由も『ドイツに攻められて国家崩壊が差し迫ったポーランドにおけるウクライナ系住民とベラルーシ系住民の保護』でしたからね。侵略者の口実はますます巧妙になっていくでしょう」
簡一もハールと同じくらい深い溜め息をついた。
「西からヒトラー、東からスターリンではたまったものじゃありませんよ。ポーランドは西半分をドイツ、東半分をソ連に取られて、国家として消えてしまいましたね。ソ連は今、フィンランドに攻め込んでいます。国際連盟はソ連を除名しましたが、ソ連は痛くもかゆくもないでしょう」
ハールが言った。一度はフランス軍に志願して銃を取ろうと考えたこともある彼は、国際情勢を熟知しているようだ。フランス語もずいぶん上達した。
「いったい日本はどうなるのでしょうか」
智恵子が泣き出しそうな声を上げた。
「今年が正念場だね。日本は昨年、1939年にソ連と戦って完敗しているんだ。智恵子さんもご存じでしょう?」
と簡一が訊いた。
「ノモンハン事件ですね。満州とモンゴルの国境あたりで戦ったと聞きました」
と智恵子が応えると、簡一は
「その通りです。ソ連はノモンハンで日本軍と激戦を繰り広げている最中に、ドイツと不可侵条約を結んだわけです。しかもソ連は9月半ばに日本との停戦協定が成立した直後、間髪を入れずポーランドに侵攻している。スターリンという男は、極めてしたたかで抜け目がない。今後もソ連には要注意だな」
と地球儀をゆっくり回しながら言った。
「ドイツはどうなんです?」
紫郎が地球儀の一点を指さして、簡一を見た。
「敵対したくはないが、味方にもしたくないというところかな。私のドイツの友人はそろって善良で優秀だが、ナチスは別だ。あくまでも個人的な意見だがね」
簡一はそう言って地球儀を勢いよく回し、妻のガブリエルが運んできたボルドーの赤ワインを一口飲んだ。
カラカラと乾いた音を立てて回り続ける地球儀をマルセルが止めて「えーっと、ヌーヴェルカレドニーはどのあたりでしたか」と言った。南半球のオーストラリア付近を指でたどっている。
「ありました。ここです。オーストラリアの東、ニュージーランドの北に浮かぶ細長い島。日本の四国ぐらいの面積があります」
と言って、マルセルが紫郎を見た。
「ああ、日本ではニューカレドニアという英語名で知られている島だね。フランス領だったかな」
紫郎は地球儀に顔を近づけ、目を細めて小さな文字を読んだ。
「はい、フランス領です。私は春からこの島に赴任します」
マルセルがもう一度同じ場所を指さした。
「ええっ、こんな遠くの島に? 仕事で?」
紫郎はマルセルと簡一の顔を交互に見た。簡一はマルセルの顔を見て、目顔で「自分で伝えなさい」と言っていた。
「はい、仕事です。シローにはまだお知らせしていませんでしたね。私は神戸にある帝国酸素に勤めているのです」
帝国酸素はフランスのエア・リキードと住友が共同出資した会社だ。酸素製造の会社がニューカレドニアでどんな事業をするのか、マルセルは「まだ全く説明されていません」とこぼして、少し不安げな顔を見せた。
「あのー、シロー。ひとつ質問してもいい?」
シモンがテーブルに指で「の」の字を書きながら言った。
「質問? ああ、構わないよ」
紫郎も赤ワインのグラスを取った。
「智恵子さんをお嫁さんに選んだ理由を教えてほしいの」
「り、理由? いやー、参ったなあ」
紫郎は頭をかいた。
「それ、私も知りたいわ。ねえ、シロー。どうなのよ」
智恵子がピアニストの力強いタッチで彼の肩をたたいた。
「結婚に理由なんてあるのかなあ」
「そりゃ、あるでしょう」
智恵子が新婚の夫に詰め寄った。
「そ、そういう運命だったんじゃないかな」
「何よ、その言い方。運命だから仕方なく結婚したみたいな言い方じゃないの」
智恵子が声を上げた。簡一が「なんだか夫婦漫才みたいだな」と言うと一同がドッと笑ったが、シモンだけは複雑な顔をしてうつむいていた。
紫郎、智恵子、ハールの3人は伊庭家で一泊した翌朝、神戸から特急「燕」で東京に向かった。
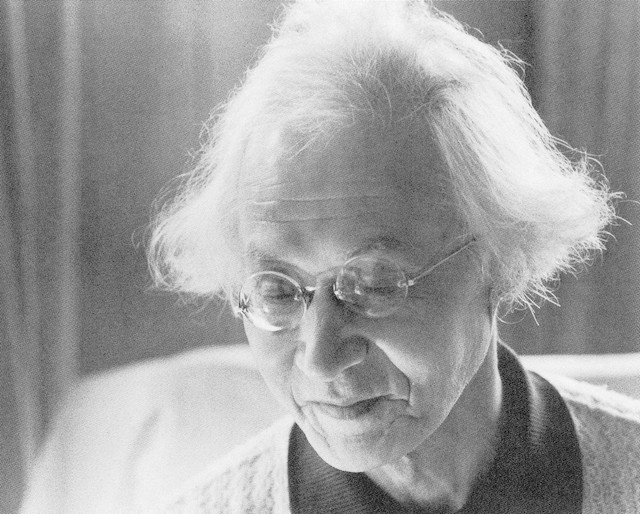
3人は東京駅の丸の内北口で小島威彦、井上清一、坂倉準三、丸山熊雄をはじめ、大勢の仲間や新聞記者たちに迎えられた。記者連中の目当ては帰国した名ピアニスト、原智恵子だった。
「ねえ、サカ。僕が見つけておいた赤坂桧町の家、どうだった?」
全員に一通りの挨拶を済ませた後、紫郎が坂倉に尋ねた。彼は日清戦争直後に建てられた旧オーストリア領事館が空き家になっていると聞きつけ、建築研究所を開く場所を探していた坂倉に手紙で知らせていたのだ。陸軍歩兵第一連隊の近くにあるペンキ塗りの2階建て洋館で、1階に15畳の部屋が2つ、2階には4つも部屋があった。
「気に入ったよ。ありがとう。早ければ再来週に引っ越すつもりだ。ただ、今の僕にはちょっと広すぎるかな。坂倉建築研究所は今のところ1階だけで十分だ」
坂倉が応えた。
「2階の使い道は、追い追い考えていこう。じゃあ、申し訳ないけどハールをよろしく頼むよ。帝国ホテルまで連れていってくれれば十分だ。ちゃんと部屋を確保してあるからね」
紫郎は坂倉と握手を交わし、タクシーに乗り込んだ。すでに後部座席の奥に小島、助手席には智恵子が座っている。小島の発案で、広尾の仲小路邸を訪ねることにしたのだ。
仲小路邸は有栖川宮記念公園近くの麻布台地に建つ和洋折衷の洋館だ。タクシーを降りて門をくぐると、何人かの書生が飛び出してきた。やけに物々しい雰囲気だ。仲小路の用心棒代わりを自任しているのだろうと紫郎は思った。彼らは小島の顔を見ると急に態度を変えて腰が低くなり、紫郎たちの荷物を持って邸内へと案内した。
「やあやあ、智恵子さん、紫郎さん、わざわざお寄りくださってありがとうございます」
仲小路は玄関の隣にある12畳ほどの書斎で3人を迎えた。和洋折衷の屋敷の中で、ここだけ洋館の造りになっている。朝から自室にこもっているらしいのに、三つ揃えの背広を着て、蝶ネクタイを締めている。肩のあたりまで伸びた長い髪は、白髪というより、銀髪と呼びたくなる鈍い光を放っていた。
「紫郎さん、月刊誌『戦争文化』が創刊から9号で休刊に追い込まれたのはご存じですか」
仲小路はテーブルに積んでいた原稿用紙の山をデスクに移し、書生が運んできた紅茶を置くスペースを空けた。
「先ほど、威彦さんから車の中でおおよそのことはうかがいました。昨年11月号が発禁になったのをきっかけに休刊を決めたそうですね」
紫郎は「いただきます」と言って、砂糖やミルクを入れずに紅茶をすすった。「セイロンのウバでございます」と書生が小声で説明した。
「では、スメラ学塾の構想についてもお聞き及びでしょうか」
「スメラ? いえ、初耳です」
紫郎がそう応えると、仲小路は小島をちらりと見た後、また視線を紫郎に戻して話し始めた。
「雑誌は少しでも何かあれば揚げ足をとられて発禁になります。しかし、まだ手立てはあります。私たちは言葉による啓発と教育に活路を見いだすことにしました」
「言葉による、ですか」
紫郎はティーカップをテーブルに置いて、仲小路の説明を待った。
「ええ、言葉による。つまり講演です。その点、あなたの従兄の小島さんは哲学や歴史の知識はもちろんですが、雄弁ということにかけても、右に出る者がいないほど素晴らしい才能をお持ちです。私たちの一派は、小島さんをはじめ、雄弁かつ有能なる識者たちによる講演、講座を定期的に持つことにしました。国民啓発のための学塾です。過日、スメラ学塾と名づけました」
仲小路は真っすぐに紫郎を見たまま視線をそらさない。
「ス、スメラとは、いったい?」
紫郎はその眼力の圧力に息苦しくなった。
「あははは。よし、僕から説明しよう。シュメール文明から発想したのさ。シュメールやスメルは、スメラミコトのスメラ、澄む、住む、統べるという言葉に響き合う。我々の学塾に打ってつけの名前だと思わないか?」
小島が場に似合わない陽気な調子で言った。
紫郎は仲小路の著書「図説世界史話大成」の一節「世界文明の根源としての日本神代史」を思い出していた。太古の日本民族が西へ渡り、チグリス・ユーフラテス川流域で古代シュメール文明を興し、それが再びペルシャ湾を出て東進し、インダス文明を経て日本に帰還する。つまり日本民族はあらゆる民族の根源をなすという話だった。かなり飛躍した異説で、紫郎は戸惑っていた。
「今は世界史の大転換の時を迎えています。もちろん誰も戦争などやりたくはありません。しかし、日本は世界戦争に巻き込まれようとしている。日本人が自らのエネルギーを結集し、最善を尽くして戦い抜く以外に、未来を拓く道はないのです。いいですか、紫郎さん。そのために私たちは日本人を啓発し、歴史的運命を自覚させる必要があるのです」
柱時計がゴーンと鳴って半時を知らせたのを機に仲小路が言葉を切り、紫郎はゴクリと生唾をのみこんだ。
「日本人の歴史的運命って、何ですか?」
智恵子が静寂を破るような甲高い声で訊いた。
「日本民族の源郷であるスメル文化圏の復興による人種平等、有色民族解放の達成です。まさに世界維新というべきでしょう。欧米の植民地侵略に対する最後の砦としての日本人の結束と覚醒が必要なのです」
仲小路はそう言って、自分の弁に満足したように微笑んだ。
「つまりね、スメラ学塾は我々にとってのエピクロスの庭なんだよ」
小島が紅茶を飲み干して言った。
「エ、エピクロスの…庭?」
智恵子がまた甲高い声を上げた。
「エピクロスは古代ギリシャのヘレニズム期の哲学者さ。ああ、それは知っているね? ヘレニズム期はアレクサンドロス大王と、彼の師匠アリストテレスが亡くなった後に始まるんだ。紀元前320年頃の話さ。この2人の死で古典期のギリシャの文化と社会は終わった。以降のギリシャでは血なまぐさい抗争や略奪、虐殺が横行するようになるんだ。そんな時代に現れた哲学者がエピクロスさ。彼は自分の庭に学園をつくったんだ」
小島が得意の雄弁を振るった。仲小路は時折うなずきながら、黙って耳を傾けている。
「ああ、だからエピクロスの庭。つまり学校ということですね」
智恵子が相槌を打った。
「その通り。しかもエピクロスの学園は、当時の教育機関から排除されていた女性や奴隷も受け入れたんだ」
小島が言った。
「へえ、知らなかった。それは素晴らしい。エピクロスの庭は現代からみても理想的な学園ですね。スメラ学塾の開講が楽しみになってきましたよ」
と紫郎が小島に向かって拍手すると、智恵子もそれに倣った。
「智恵子さん、紫郎さん、これがどこだかお分かりですか」
仲小路が大きな地図を広げた。
「ヨーロッパですね。幾つか書き込まれている青い矢印はナチスの動きでしょうか?」
智恵子が即答した。
「智恵子さん、お見事。その通りです」
智恵子はうれしそうに頭をかいた。前の日に伊庭家で話題に上ったばかりだから、まだ記憶が鮮明だった。
「ご覧の通り、ポーランドまで来ていますね。さて、この矢印は今後どうなると思いますか」
仲小路が地図を指さしながら紫郎を見た。
「英国とフランスが宣戦布告していますから、ナチスの矢印は西にも向かうはずですが、今のところ停滞しています。やはりマジノ線の威力が大きいのでしょうか」
紫郎がドイツとフランスの国境線を指でなぞった。
「とても良い視点ですね。ただ、ドイツ軍が西に進軍するとして、あえてマジノ線の強固な壁を打ち破っていく必要があるでしょうか」
仲小路はそう言った後、マッチを擦って燭台のろうそくに火を灯し、テーブルに広げた地図を照らした。
「マジノ線を迂回して進軍すればいいという意味でしょうか。オランダやベルギーの方から回り込んでフランスに入る、と」
仲小路は紫郎の言葉を受けてペンを執り、青インクをたっぷりつけて大胆に矢印を描き始めた。
「まずヒトラーは北に行きます。デンマークとノルウェー。冬の間は寒すぎるから春の訪れを待つでしょう。続いてルクセンブルク、ベルギー、オランダ。そこまで行けばフランスも時間の問題になります。さて、東側の矢印はどうなるでしょうねえ」
矢継ぎ早に青い矢印を書き込んだ仲小路は再び紫郎を見た。
「ひ、東ですか。ポーランドの先はソ連の勢力圏になりますね」
紫郎が地図をのぞきこむと、ろうそくの炎が激しく揺れた。
「ヒトラーはナポレオンみたいな男ですよ。必ず東に向かいます」
仲小路が天井を見上げながら言った。
「しかし、独ソ不可侵条約を結んだばかりですよ」
紫郎は仲小路の眼鏡に映ったろうそくの炎を見つめた。
「ヒトラーやスターリンがそんな条約に縛られると思いますか」
「はあ…。ナポレオンはロシアを攻めて失敗しますね。ヒトラーも同じ道をたどるとお考えですか」
「とても良い質問ですね。しかし、その話は保留にしておきましょう。それより、我が日本にとって、もっと重要な懸念があります。見落としてはいけません」
仲小路の眼鏡の奥が鋭く光り、さらに話を進めた。
「我が国はノモンハン事件でソ連の強さを痛感しました。それで北進論が衰退し、代わりに南進論が勢いづいています。東南アジアには石油やボーキサイトなどの資源が豊富ですからね。先ほど申しましたように、ヒトラーは近いうちにオランダを占領します。いとも簡単に。するとアジアの南洋に存在する広大なオランダ領はどうなりますか。蘭領を巡って、利害が衝突する国はどこでしょう」
「ええっと…」
頭を抱えている紫郎を見て、仲小路はろうそくの火を吹き消し、こう言った。
「日本と英米が全面戦争になりかねません」
柱時計が5時を告げ、同時に窓ガラスがカタカタと震えた。どうやら外は冬の嵐になっているらしい。紫郎は隣で身動きもせずに黙っている智恵子の手を握った。氷のように冷たかったが、紫郎の手も同じくらい冷え切っていた。仲小路の予言はことごとく当たっていくのである。(つづく)
(※)永井荷風著「ふらんす物語」の引用は新潮文庫より。






















