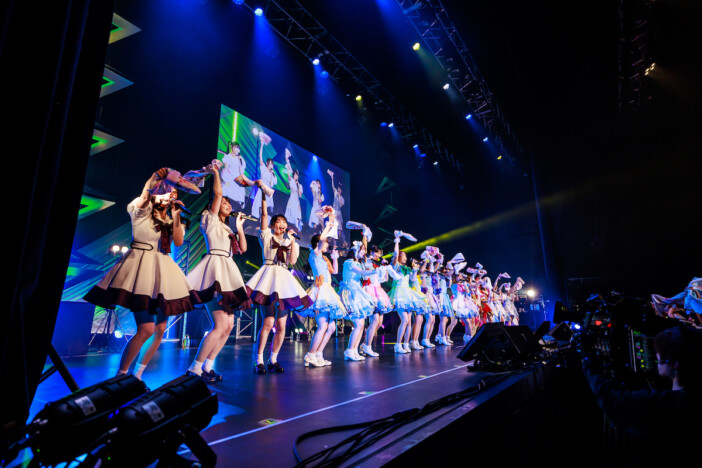KEYTALK、KANA-BOON、ロットン、スカパラ、マンウィズ......今春ベストアルバムでキャリアを総括するバンドたち
この春、注目のベストアルバムのリリースが相次いでいる。KEYTALK、KANA-BOON、ROTTENGRAFFTY、東京スカパラダイスオーケストラ、MAN WITH A MISSION。いずれも、音楽シーンの第一線を長年張り続け、ロックフェスのステージでも多くのオーディエンスを前に強烈な存在感を発揮し続けてきたバンドだ。彼らはどのようにそれぞれの道を切り開き、キャリアを積み重ねてきたのか。楽曲を軸に、その歩みを振り返ってみたい。
KEYTALK

まずは3月18日にビクター在籍時代の5年間を総括するベストセレクションアルバム『Best Selection Album of Victor Years』をリリースしたKEYTALK。2枚組、全20曲のトラックリストには、シングル曲を中心にライブでもおなじみの楽曲が並んでいる。
メジャーデビューシングル「コースター」やメジャー初期の代表曲「パラレル」に象徴される、ツインボーカルによるエモーショナルな歌と、その歌と同じくらいメロディアスなギター、タイトで手数の多いドラム。その“基本形”は今も変わらず彼らの真ん中にある。そしてこの5年間の中でKEYTALKはその“基本形”をどんどん発展させ、いくつものフェスアンセムを生み出してきた。
振り付けもあっという間に定着した「MONSTER DANCE」や「MATSURI BAYASHI」といったオーディエンスを問答無用で巻き込んでいくダンスチューンから「桜花爛漫」や「スターリングスター」のようなメロディと歌が際立つポップチューンまで、ベストアルバムを聴き返すと、彼らがシーンの中で揉まれながら、自分たちの武器をひたすら研ぎ澄ませてきた軌跡が浮かび上がってくる。
2018年にリリースされたビクター最後のアルバム『Rainbow』は、その意味では彼らにとってひとつの到達点といえる作品となった。「黄昏シンフォニー」や「セツナユメミシ」には、フェス的な盛り上がりとポップミュージックとしての強度、その両面においてさらにスケールアップしたKEYTALKがいる。2019年のユニバーサル移籍以降の彼らはますます音楽的なバンドになってきているが、その萌芽も、このベストアルバムにはしっかりと記録されている。
KANA-BOON

そのKEYTALKとほぼ同時期に結成され、同年にメジャーデビューを果たしたKANA-BOONもまた、フェスという場を主戦場にファンベースを広げてきたバンドだ。3月4日にリリースされた『KANA-BOON THE BEST』には、自主時代やインディーズ時代の楽曲、そしてシングル化されていないアルバム曲も含め、彼らのこれまでの全軌跡が凝縮されている。
KANA-BOONの場合、なんといっても高速4つ打ちビートとギターロックという組み合わせを一躍ロックシーンの主流フォーマットにしたということの意味は限りなく大きい。「ないものねだり」のキャッチーな4つ打ちギターロックは、フェスにおいてライトユーザーを前に鳴らすのにきわめて効果的な“最適解”だった。KANA-BOONの登場以降、若手バンドのキラーチューン(この“キラーチューン”という言葉自体が“踊れてノレる”という意味を含むようになったのも彼ら以降だと思う)は4つ打ち一色になっていったし、その流れは今も終わっていない。
ただし、彼らの楽曲を振り返って改めて感じるのは、KANA-BOONの5年間はそのパブリックイメージやステレオタイプからいかに脱却するかという闘いの歴史だったということだ。「結晶星」や「生きてゆく」「シルエット」といった曲には、よりスタンダードで広いポップミュージックを目指す彼らの思いが滲んでいる。とりわけ「ダイバー」以降、アルバムでいえば3rd『Origin』以降の楽曲には、より大ぶりのリズムとリフでスケールの大きなロックを鳴らそうとするKANA-BOONの姿が見える。その意味では、彼らの本当の真価が問われるのはこれからなのかもしれないと思う。