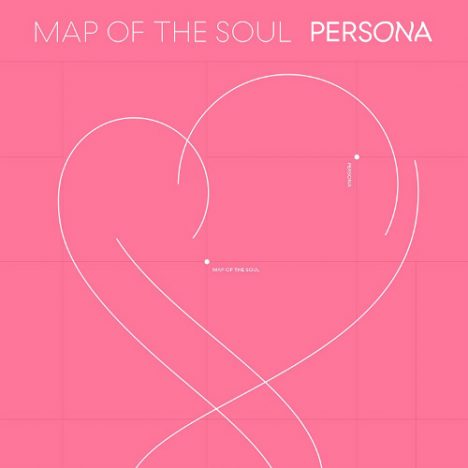BTS『MAP OF THE SOUL:7』の“内向き”な歌詞 SNSカルチャーの一つの到達点に
作品に内包される“外向き”と“内向き”の姿勢
以前「Rolling Stone」のK-POPアーティストに楽曲を提供しているアメリカの作曲家へのインタビューでは「韓国のポップスでは大胆な展開が好まれる」「アメリカの曲の大半が4つか5つのメロディでできてるのに対して、K-popの曲には平均して8〜10くらいのメロディがある。リッチなハーモニーも特徴のひとつね」(中略)「韓国じゃ短いビートのループは通用しない。曲にあんなにも多くの展開を持たせるのはK-popだけだろうね。作曲家としては大いにやりがいがあるよ」と語られていた。それを踏まえてBTSの今作を聴いてみると、新録曲にダンスブレイクがないわけではないし、様々なジャンルにも挑戦しているが、よりシンプルな構成の曲が増えているようには感じられる。タイトル曲の「ON」は「Boy With Luv」のポップさとは対極の、悲壮感すら漂うダイナミックなパフォーマンスとメッセージで、アーティスティックな表現に挑んでいるようだ。
しかし、音楽やパフォーマンス面で“外向き”の視線を演出する一方で、歌詞の内容はどれも非常に“内向き”だ。初期の学校3部作時代は“外の世界=社会”との対決を歌っていた彼らは、『花様年華』シリーズの青春三部作の時期を迎え、自らの内面と対峙する世界観へと転換していった。そのような精神的・内的葛藤の向こう側の世界が“ファンと自分たち”という、よりクローズドなものだったのは、彼らの現状を反映するかのように予想外の展開とも言える。彼らの世界は物理的には広がったはずなのに、表現する精神世界はより狭くなっているように感じられる。実際、今回のアルバムの楽曲の内容はほとんどが“ファンソング”と呼べるようなものだ。ソロ曲やユニット曲にしても彼ら個人に関心があったり、彼らの歴史をある程度知っているリスナー向けというのがまず前提になっている。
彼らのアイドル/芸能人としての“Persona”を表現したのが『MAP OF THE SOUL : PERSONA』の5曲で“Shadow”や“EGO”を表したのが今回の新曲14曲だという解釈をするならば、この中で表現されている彼らの“self=全てを内包した自己”には“アイドル/BTSである自分”以外の部分がないということになる。そこでもう一度「Intro:Persona」の歌詞を見ると、「Shadow」と「EGO」のリファレンスの他にも「ON」の歌詞“俺なんかが何の使命”と、「Respect」の歌詞“俺なんかがmuse”といった、今作『MAP OF THE SOUL:7』の楽曲のフレーズがリファレンスされている。その後に続く“俺の名前の3文字”が“BTS”だとするなら、「EGO」で達成した“自己実現”というのはやはり全てを内包した“self”というよりも、あくまで“BTSである自分”という枠組みの中でのことなのだろう。
本当のプライベートやアティチュードを晒し/晒されて時にそれが作品の源にもなるいわゆる“欧米のアーティスト”とBTSが決定的に異なるのは、彼らが“韓国のアイドル”である以上、彼らが見せる/見せられる“プライベート”は実際はかなり限定されているという点だ。アイドルが楽曲やパフォーマンス含めた“ファンタジー化された自己”そのものを売るビジネスである以上、見せる部分と見せない部分の演出は不可欠だ。そのような限られた範囲で“己を晒す”以上、“アイドル/芸能人である自分”の枠をはみ出すことはほとんどない。その上でファンドムとの絆や関係性をここまで前面に出した作品を作るのは、“ファン=ARMY”が現在の“BTS”のアイデンティティの大きな部分を占める存在になってしまっていることを、図らずも赤裸々に表現しているとも言える。“K-POPではなくBTS POP”という表現も、韓国では人気アイドルを指して「○○が出せば童謡でも売れる」というフレーズがあり、どのような音楽か、よりも“誰が歌うか”の方が重要なジャンルにおいては至極当然の表現とも言えるだろう。それも含めた上での「ON」=we on(我々がやってきたこと)・carry on(それでもやり続けていく)という、諦観にも似た覚悟の表明なのかもしれない。
このような“作品の外面と内面のズレ”と、「N.O.」では“他人の夢に閉じ込められて生きるな”と歌っていた防弾少年団が、BTSに至り、表現する対象のほとんどがファンドムとの絆になったという点は、考えさせられるものがある。しかし、ファンドムが時にはアーティスト以上の力を持ち、ビジネスを動かす“スタンカルチャー(熱烈すぎるファン文化)の時代”になった2010年代後半において、 BTSは間違いなく最もその恩恵を受けて成功したグループだろう。このアルバムを真に心から共感して味わうには、彼らのファンドムに“入信”するしかないということだ。そういう時代を究極の形で表現したアルバムという点で、2010年代後半を代表するSNSカルチャーの一種の到達点とも言えるのかもしれない。
■DJ泡沫
ただの音楽好き。リアルDJではない。2014年から韓国の音楽やカルチャー関係の記事を紹介するブログを細々とやっています。
ブログ:「サンダーエイジ」
Twitter:@djutakata