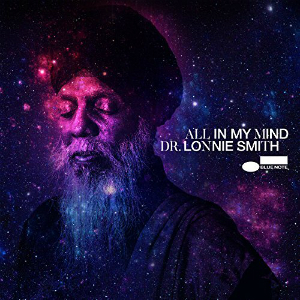柳樂光隆の2018年ジャズ年間ベスト10
柳樂光隆が選ぶ、2018年ジャズ年間ベスト10 ロバート・グラスパーが打ち立てたものの先へ
1:Kamasi Washington『Heaven and Earth』
2:Brad Mehldau『After Bach』
3:Ambrose Akinmusire『Origami Harvest』
4:Rafiq Bhatia『Breaking English』
5:Antonio Sanchez『Lines in The Sand』
6:Julian Lage『Modern Lore』
7:Makaya Mccraven『Universal Beings』
8:Marcus Strickland『People of The Sun』
9:Ben Wendel『Seasons』
10:Nels Cline 4『Currents, Constellations』




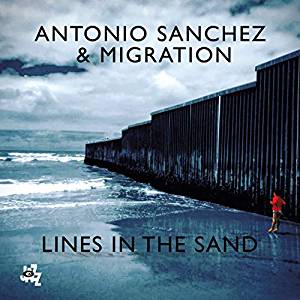
2018年のジャズは豊作だった。とにかく充実していた。なので、「選ぶのが大変だった」というのはお世辞でも誇張でもない。
ただ、わかりやすいトレンド的なものはあまりなかったので、その豊作具合が見えにくい部分もあるのかもしれない。というか、ジャズに関してはここ数年、トレンドと言えるトレンドはあるようで存在しないので、充実はしているが、何かが流行っていた感はずっとないんだろうなとは思う。
振り返ってみると、ロバート・グラスパーが『Black Radio』をリリースしたのが2012年、J・ディラの曲をピアノトリオで演奏した『In My Element』が2007年。つまり「ジャズとヒップホップやR&Bが同居したハイブリッドなジャズ」なんてものにもそれなりの歴史がすでにできていて、もはや珍しくもなんともなくなったということだ。今や、様々なものが入り混じることは前提の前提の前提の前提くらいの感じで、「それがどういう形で混ざるのか」、「どういう形で組み合わさるのか」、「組み合わさった結果出来上がったものは今までに見たことがないようなものなのか」、そして、「それがどの程度のクオリティーなのか」みたいなことまでが問われている。そこではジャズ以外のジャンルへの理解や、その他ジャンルの要素をジャズミュージシャンがやることの意味も求められる。ロバート・グラスパーが『OkayPlayer』のインタビューで「ジャズバンドでヒップホップっぽいことをやってちゃだめだ。本物をやりたかったら、本物のヒップホップのバンドで演奏しろ」と言っていたのは、そういう部分に関するメッセージなのだろう。要はもはやチャレンジでも何でもなく、その中身が問われているのだ。
さらに言えば、この10年、ジャズの中心地アメリカでは、オバマからトランプの時代になり、様々な価値観が揺らいでいる。そういった状況の中で、自身のアイデンティティーやルーツ、もしくは自身のカルチャーの成り立ちにまでさかのぼりながら、私は何なのか、私を取り巻いている文化は何なのか、そして、私が奏でている音楽とはそもそもどこからきたもので、どんなものなのか、そんなことまでも意識しながら、音楽を奏で、生み出している音楽家が増えている。
アフロアメリカンのルーツをたどり、カリブ海から西アフリカまで思いを馳せるものもいれば、アメリカの各地の音楽を広く探求しながらアメリカそのものを掘り下げるものもいれば、そういった様々な音楽がアメリカの地で融合して生まれたジャズという音楽の在り方を問い直すような活動をする者もいる。さらに言えば、カリブはもとより、中東(イスラエルなど)からアジア(インドなど)に至るまで、様々な土地から移ってきた移民(とその子供たち)たちがそのルーツを探求して得たものが、アメリカの音楽としてのジャズを前に進めたという部分もある。
「ジャズは終わった」なんて言葉はしょっちゅうささやかれるし、一般的にはそんな軽口が許されていることも感じるが、20世紀の終わりからジャズは急速に進化し、メタモルフォーゼし、どんどん形を変えている。スウィングジャズがビバップになってもそのまま「ジャズ」と呼ばれ続けたのと同じように、ジャンル名の変更の必要性さえ感じさせながら、それでもジャズとしか呼べない何かであり続けているような変化が起きている。
そして、ここ30年くらいにあった大きな変化がここにきて、さらに加速している雰囲気がある。00年代以降のカート・ローゼンウィンケルやマーク・ターナー、ブラッド・メルドーらが打ち立ててきた流れをさらに進めるものもいれば、全く違う文脈の音楽を発明し奏で始めているものもいる。その中にはロバート・グラスパーもいるが、ロバート・グラスパーが打ち立てたものを前提に先に進める若手がどんどん出ている。技術、理論、そして、思想、哲学に至るまでここにきて、レベルが上がり、新たなフェーズに到達している感があるのだ。
というわけで、ようやく2018年のジャズの年間ベストの話をすると、年間ベストとしてまとめた作品群たちを説明するには、個々の作品を一枚ずつ説明するのか、もしくはそういったものが生まれる背景や状況をこうやって大きな話として記すしかないような気がしたのだ。
強いて言えば、ジャンルを超えた混ざり具合がさらに細かくなり、同時に大胆になりながら、完成度が上がっている、ということだろうか。
ジェイムス・フランシーズやブラクストン・クックといったまだ20代の若手たちは、00年以降のコンテンポラリージャズの進化を作曲や演奏の面でそのまま反映させながら、同時に同時代のヒップホップやR&Bとも接続させることに成功している。21世紀のジャズの進化の流れに逆らわずに、むしろその流れに身を委ねるように音楽を作り、その上で自身が聴いてきたものや身に付けてきたものを自然に昇華している。
一方で、ジュリアン・ラージのようにアメリカの様々な時代や様々な地域の音楽をギター1本で縦横無尽に奏でるツワモノもいれば、マーカス・ストリックランドのようにアフロアメリカンのルーツをさかのぼりながら現代とも接続させるものもいる。自身と現代のジャズの最大の影響源でもあるバッハを再解釈したブラッド・メルドーや、LAに根付く音楽を意識しつつ、クラシック経由の作曲志向をジャズに反映させたカマシ・ワシントンの音楽も一見全く違うものだが、そこには共通する哲学のようなものを感じるのだ。UKではシャバカ・ハッチングスが自身のルーツでもあるバルバドスをはじめ、カリブ海の島々の音楽をUKに住む移民でもあるカリビアンとしての文脈で再構築していたし、アルメニアのティグラン・ハマシアンのようにかなり前からそういったことを突き詰めているものもいて、そんな流れが世界中に広がっているのも面白いと思う。