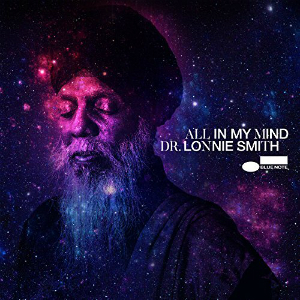柳樂光隆の2018年ジャズ年間ベスト10
柳樂光隆が選ぶ、2018年ジャズ年間ベスト10 ロバート・グラスパーが打ち立てたものの先へ
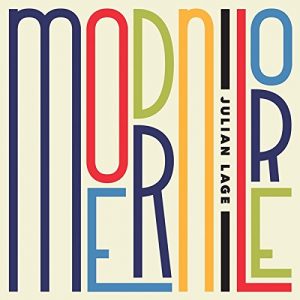




これからどうなるかを示唆しているものはあるかと問われたらいまいち自信がないが、マカヤ・マクレイヴンのようにNY~LA~シカゴ~UKロンドンを結び現在のジャズシーンをドキュメントしてみせたように、コンセプトアルバムみたいなものが目立った気がしている。カマシ・ワシントンもそうだし、ラップと共に長大なストーリーを描いたアンブローズ・アキンムシーレもそうだったが、コンセプトに合わせて作られた複数の曲を並べることでしか表現しえないものが面白いって予感はある。バッハの曲と、そのバッハの曲を基に即興演奏で生み出した自身の曲を交互に並べることでバッハとジャズの関係を浮きあがらせてみせたブラッド・メルドーをはじめ、アントニオ・サンチェスらもその文脈で聴けるだろう。
演奏家としてだけではなく、作曲としての側面も含めたトータルな音楽家として、自分が表現したいものを示すことへの意識がどんどん高まっているように思える。Apple MusicやSpotifyのプレイリストとの相性を考えると時代に逆行しているように思えるのだが、昔から世界中を回りライブでのその場の演奏を日々積み重ねることで生活している彼らにとっては、むしろそういった音源を聴かせるためのプラットフォームの事情に縛られる必要がないとも言えるし、環境に左右されていないという意味ではジャズミュージシャンにはジャズミュージシャンなりの自由さがあるのかもしれないとも思う。
そういえば、日々、世界中で演奏しながら、その合間に様々なジャズミュージシャンとのデュオ動画を定期的にアップする企画「Standards with Friends」が話題になっているベン・ウェンデルはマルチメディアを駆使した活動をしていて、特に今年リリースしたアルバムの『Seasons』に関しては、前年にYouTubeでやっていたプロジェクト(Seasons Project)を総括したような作品で、動画とは違う「アルバム」としてまとめられたことの意味を感じさせる編曲や構成が印象的だった。
前日とは異なるその場限り、その瞬間限りの即興演奏を日々繰り広げるジャズミュージシャンだからこその、「録音作品」へのこだわりみたいなもののためには、アルバムという枠組みが有効であることを感じた一年だったのかもしれない。
■柳樂光隆
79年、島根・出雲生まれ。ジャズとその周りにある音楽について書いている音楽評論家。「Jazz The New Chapter」監修者。CDジャーナル、JAZZJapan、intoxicate、ミュージック・マガジンなどに寄稿。カマシ・ワシントン『The Epic』、マイルス・デイビス&ロバート・グラスパー『Everything's Beautiful』、エスペランサ・スポルディング『Emily's D+Evolution』、テラス・マーティン『Velvet Portraits』ほか、ライナーノーツも多数執筆。