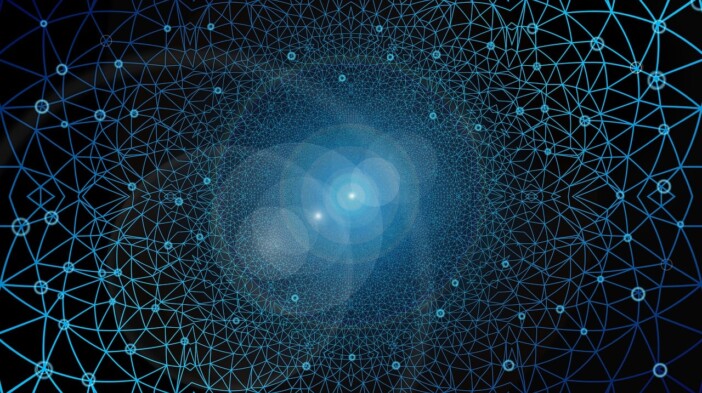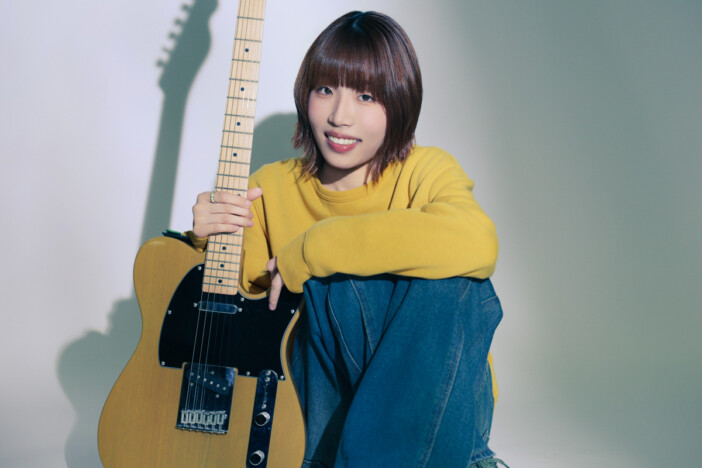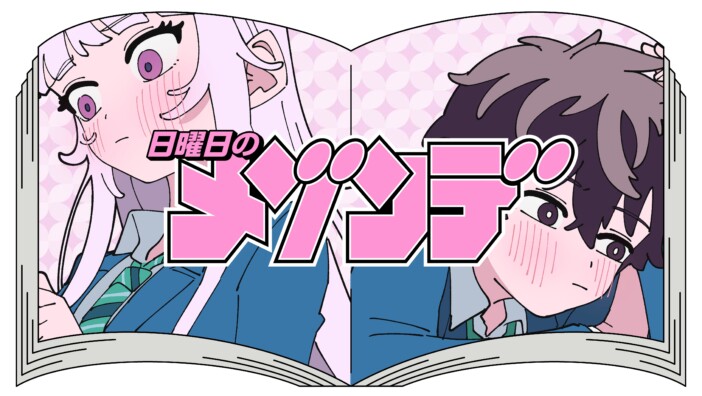生成AIをフル活用した香取慎吾のMVも話題 気鋭クリエイター・YPと音楽、映像表現の原点

香取慎吾の「Circus Funk (feat. Chevon)」MVが話題だ。“香取が所属するサーカス団が住む惑星型のスペースシップに流星群が迫り、緊急事態の中で最後の配信サーカスを決行する”という幻想的なストーリーを生成AIの技術を駆使して映像化したのが、本作の監督を務めたクリエイターのYPである。当時最年少CMディレクターとして手掛けた森永乳業リプトンTVCM「夢を追いかける人編」で脚光を浴びて以降、さまざまなアーティストのMVや動画コンテンツで注目を集めてきた人物だ。
YPを香取に紹介したのは、昨年放送作家を引退した鈴木おさむだった。香取がGENERATIONSのコンサートに出演した際、「ものすごい才能が光ってる子がいる」と言って香取のチームに見せたのが、企画・脚本・監督のすべてをYP自ら手掛けるYouTubeドラマ『呪縛少女バギラちゃん』だったという。そして、その作品を気に入った香取のチームがYPのセンスを信頼し生まれたのが、「Circus Funk」のMVだ。今回のインタビューでは、YP本人に本作にまつわるエピソードから、映像表現のルーツや今後の野望まで幅広く話を聞いた。(編集部)
ディレクションが得意な人は生成AIと相性がいい

ーー香取慎吾さんの「Circus Funk (feat. Chevon)」のMVを制作したきっかけを教えてください。
YP:きっかけは鈴木おさむさんですね。ある日「MVを頼みたいんだよね。香取慎吾という男の作品なんだけど」という電話が突然かかってきまして。その後香取さんのチームと繋いでいただきました。
ーー「Circus Funk」のMVでは生成AIが活用されているとのことですが、従来のMVの制作手法とどのような違いがありましたか?
YP:全くアプローチが違いますね。通常、3DCGを制作する時はモデリングから始めて完成のイメージに近づけていく作業なんですけど、生成AIの場合は、いろんな完成形を作り、そこから選んでいく作業になります。例えば、隕石の画像ひとつにしても、単に“隕石”と指示を出すだけだとイラストの彗星っぽい画像しか生成されないのですが、より具体的な指示を出せば、それに合った画像が生成されます。
ーーつまり、生成AIに指示を出すプロンプトが重要になるということですか?
YP:そうです。プロンプトをどれだけ精度高く入力できるかに左右されるので、言葉のディレクションをする必要があります。だから、隕石を作りたいのであれば、表面のテクスチャーは、〇〇山の画像みたいな感じにしてくれとか、細かく指示しないとダメなんです。それにプロンプトを書き忘れるとただのイラストに戻ってしまうので、プログラミングのような作り方が求められるんです。今回は最初にエンジニアと一緒に生成AIの環境を整え、画像を100枚くらい生成し、その中から一番自分のイメージに近いものを選びました。それからその画像を基に動画化するのですが、必要に応じて「隕石を90度回転させて」などの指示をしていく。この作業を各カットで行いました。これはさきほどもお話ししたように3DCGのモデリングとは手の動かし方と頭の使い方が全く別のプロセスのため、生成された画像を的確に選ぶ能力が求められます。つまり、その良し悪しの判断を的確にやっていかないといけないのですが、その点でもやはり従来のMV制作とはプロセスがかなり違いますね。

ーー「Circus Funk」MVの実写シーンの背景も印象的でしたが、こちらはどのようにして作られたのでしょうか。
YP:ラスサビのサーカスシーンでは生成AIで作った画像を単に背景画像として使っているのではなく、画像を2.5D化しています。つまり、1枚の平面の画像をレイヤーで立体的にしているのですが、ここではカメラが動くとその位置情報をリアルタイムで取得するセンサーにより、背景も同じように動くという技術を使っています。このシーンは横のカメラの動きが多いのですが、画像を2.5D処理することで、そういったシーンが再現可能になっています。
ーー今回のMV制作で生成AIを使ってみて、どのような制作上のメリットがありましたか?
YP:制作期間を短縮できたことが一番大きなメリットです。このクオリティを全部VFXでやると、制作期間が倍近くかかり、コストももっとかかるはずです。ただ、その分難易度は普通に作るよりも高い気がしますし、コストを抑えるにしてもその方法を知らないと難しいですね。特に生成AIはガチャっぽいところがあって、イメージするものになかなか辿り着かないこともあるので、そこが面白い反面、ネックにもなると思いました。
ーーでは、従来のように3DCGを人間が作った方がクリエイターが目的とするものには辿り着きやすいということですか?
YP:場合によってはそうかもしれませんが、一概には言えません。新しいことをしようとすると時間がかかるのは3DCGも同じですしね。実際にやってみて、作業者の負担は両方とも同じくらいですが、使う脳みそが違うというか、大変さの角度が違うんだと感じました。ただ、ディレクションが得意な人は生成AIと相性がいいので、パズルのピースを選ぶように演出がうまくはまればその後もスムーズに進めることができます。でも、そうならないと生成AIを使いこなすのは難しいですね。選ぶ画像を間違えると、作品が良くならないので。
ーーつまり、生成AIを使うクリエイターの底力が問われるということですか?
YP:そうですね。自分の中で蓄積されてきたものと作りたいイメージの繋げ方の話だと思います。それを繋げる時にディレクション能力が求められるし、今までのビジュアルディレクションとは違い、生成AIの場合はロジカルな言語のディレクションが必要になってきます。言語のディレクションが得意な人は、生成AIを使った作品作りに向いていると思います。
「動く香取さんをどんなシーンで観ることができたらみんなのテンションがアガるか」

ーー「Circus Funk」のMVについて「宇宙よりも広いこのインターネットで、もしあなたが偶然この物語を観測することが出来たなら」というコメントをされていますが、視聴者に届けたかった具体的なビジョンについて教えてください。
YP:まずMVの設計で言うと、「動く香取さんをどんなシーンで観ることができたらみんなのテンションが一番アガるかな」ということから考えています。またコンセプトは、今までに発表されてきたMVとは違うテンション感にしようと思いました。サーカス的なニュアンスのものがすでにあった中で、僕がサーカスの舞台を描くのであればどうしようかと考えたのと、生成AIという技術との相性を考えた時、具体的な舞台やシチュエーションよりも宇宙がいいなと思いました。そこから「Circus Funk」の歌詞を読み解いた時に、ただハッピーなだけの歌じゃないことに気づきました。実はこのMVの企画は、最初はもっとハッピーな企画だったんです。でも、歌詞を聴くうちに刹那的な悲しさや混沌とした感情がこの曲に含まれていることに気がついたんです。
ーーそういった感情をどのように表現されたのですか?
YP:映像の流れとしても、最後のサーカスシーンは、終わることはわかっているけど、最後の思い出として楽しくしようというメッセージを込めています。悲しさをはらみながらも、最後に香取さんがまたどこかで会おうというメッセージを送るのが“らしい”というか、そういう香取さんを見たら、みんな心動かされるんじゃないかなと思いました。それで今回は最後のシーンを一番最初に思いついて、そこに繋げるように物語を終わりから構成していきました。
ーーYouTubeのコメント欄には「これは日本の『グレイテスト・ショーマン』だ」というコメントがありましたが、そのような要素も最初から意識されていたのでしょうか?
YP:このMVでは僕の好きな要素と楽曲のテーマをリンクさせて描きました。『グレイテスト・ショーマン』も好きな映画ですし、宇宙やサーカスも好きです。自分が好きな要素と「これなら香取さんの姿をみんなが見て楽しいのではないか」というシーンを融合したMVとして落とし込みました。
ーー「Circus Funk」では香取さんとChevonがコラボレーションされていますが、その魅力をどのように映像で表現しようと考えましたか?
YP:香取さんだけじゃないことが重要だと思いました。最初はChevonのキャラクターがわからなかったんですけど、いろいろと動画を観ているうちに、谷絹茉優(Vo)さんはハッとするフレッシュさのある表情をする方だなと思ったんです。一方、香取さんは大人の余裕というか、「ついてこい」という感じで引っ張っていく。そんなフレッシュさとどしっと構える感じでそれぞれのキャラ分けをMVの中でしました。
僕的には香取さんはずっと子供の頃から見てきた存在ですが、Chevonは後輩世代なので、年齢的に真ん中の僕がディレクションすることで、上の世代のどっしりしたニュアンスと下の世代のいい意味でのワチャワチャしたニュアンスがひとつの映像の中に存在する。そういった映像のコントラストのある演出を考えましたね。