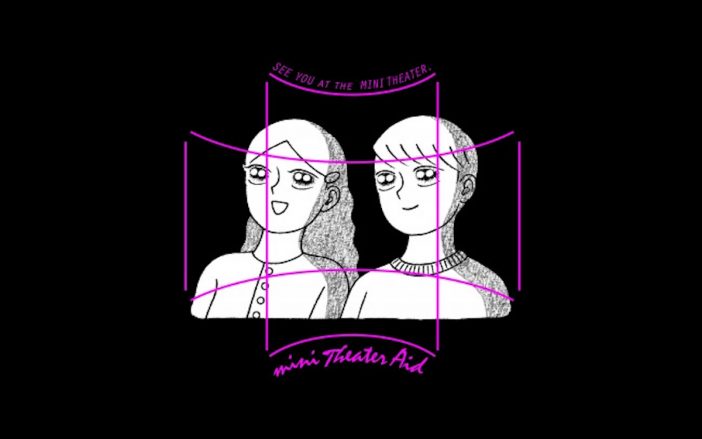「コロナ以降」のカルチャー 現在地から見据える映画の未来
深田晃司×濱口竜介が語る、「ミニシアター・エイド基金」の成果とこれからの映画業界に必要なこと

コロナ禍を経ての作品作り
ーー「ミニシアター・エイド基金」の活動を通して、お二人が得たものは何かありますか?
濱口:コレクターの方々のコメントを読んでいると、本当に一人ひとりにとってミニシアターが人生のかけがえのない場所になっていたことが分かります。映画館で働く方々は、お客さんと劇場で触れ合っても、その思いまでは知ることができません。週の入場者数がどんどんと減少していく中で、自分たちの行っていることが何になっているのか、何の役に立っているのか、こんなことをやって意味があるのかと思っていた方もたくさんいたと思うんです。でも、少くない数の方がミニシアターで得た経験によって人生が豊かになった、それが可視化されたことはものすごい大きな価値だと思います。その一方で、特に劇場関係者の方々に言いたいことは、「逃げてもいいんですよ」ということです。自発的ではない形で誰かのための犠牲になるならば、それは絶対に避けるべきです。「ミニシアター・エイド基金」の分配がいくことで、「映画館をやめられない」と思ってしまう方もいると思うんです。お金以上のものを受け取ってしまったと思う方もたくさんいると思います。でも、それがその人自身の生活を破壊するものであるとすれば、間違っています。お金はお金でしかありません。厳しい話ですが、お金が尽きたら辞める。ないものをなんとかしようとしてはいけないと思っています。個人的には何にお金を費やすべきかと言えば、建物や場所ではなく、人なんじゃないかという気はしています。もちろん場所も物も失われてしまえば取り戻すのは難しい。それでも人の暮らしが保たれれば、映画館という場を作った人たちの志は保たれるわけです。それがあれば、いずれ立て直すこともできますから。
深田:練馬区のとんかつ屋さんの店主が、自殺を疑われる火災によって亡くなられたというニュースがありました。このコロナ禍でお店を休業しなくてはいけなくなったことに、精神的に非常に悩まれていたと聞きます。人はなぜ生きていくのかと考え始めたら哲学の世界になってきてしまいますが、私は本質的には人が生きなくてはいけない理由なんてないのだろうと考えています。でも、それでは生き辛いから生きていくために多くの人がさまざまなものに価値を見出していく。それが仕事の人もいれば、趣味の人もいる。恋人や家族かもしれない。でも、今回の新型コロナウイルスは、さまざま人の価値を大きく揺るがしました。特に映画業界は“不要不急”のものとして扱われ、自分の仕事は、本当は価値がないのではないかと思った映画関係者も少なくないはず。でも、「ミニシアター・エイド基金」を通しても分かったように、そこに生きる価値を見出してくれる人が本当に多くいるんです。繰り返しになりますが、私自身も大きな勇気をもらいましたし、作り手、俳優、スタッフ、映画関係者のすべての方にとって、一日一日を生きていく糧になったのではないかと思います。
ーー最後に、監督としての今後の作品についてお伺いいたします。コロナ禍を経ての作品作りには何か影響がありますでしょうか?
濱口:「変えよう」という思いは一切ないです。今までどおりにそのときどきの作りたいものを作っていくだけですね。感染防止のために、ソーシャル・ディスタンスが必要と言われますが、そもそもカメラは常に距離がないと撮れないものであり、映画製作の根本には“距離”がある。それが前提なわけです。じゃあ、「メイクさんは接触するけどそれはどうするのか」「キスシーンはどうするのか」ということが問題になってくると思いますが、それによって表現が限定されるという考え方はしないほうがいいと思っています。必要なメイクはすべきだし、キスシーンが必要なら撮るべきだし、その目的のために役者さんとの合意プロセスを構築すべきだと考えています。撮られるべき物語に向かって準備をしてそれを撮るだけと思っています。
深田:私もスタンスを変えることはありません。これは自分に限らず、すべからずすべての作家・人間がそうだと思うのですが、あらゆる表現は環境に支配されているものだと思っているんです。これは「自由意志とはなにか」という議論になっていきますが、人間が自由意志だと思っているものも実は環境の反射物でしかないんじゃないかと。自分がどんなに国際人であろうとしたところで、日本で生まれ日本で育ち、日本語という言語を使うことによって制約されているものがあるわけです。コロナ禍や「ミニシアター・エイド基金」の経験や記憶は、反射物として私の中の創作には影響されていくはずですが、それ以上でもそれ以下でもないと思います。今後面白いと思うのは、これだけ世界規模であらゆる国があるひとつの災厄に巻き込まれたのは第二次世界大戦以来だと思うんです。大戦後は、映画をはじめ、あらゆる表現がどうしたって戦後をどう捉えるかと向き合わざるをえませんでした。それと同じように、コロナ禍を経て、どういった作品が現れてくるのか。一人の人間として興味深く感じているところです。
【特集ページ】「コロナ以降」のカルチャー 現在地から見据える映画の未来