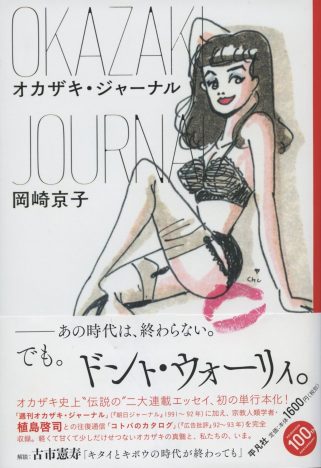【追悼】魚喃キリコの作品はなぜカルチャー好きに愛されたのか? 作品に込められた「誰かに触れたい」という切実な想い

2025年の12月25日、漫画ファンの間に、いや、カルチャーを愛する者たちの間に、大きな衝撃が走った。漫画家の魚喃キリコの訃報が入ったのだ。しかも彼女がこの世を去ったのは、そのちょうど一年前のことらしい。ショックを受け、いまもまだ感情の整理が追いついていない読者もいるのではないだろうか。それほどまでに深く愛される作家だったのだ。
魚喃キリコが遺したもの
1993年、「月刊漫画ガロ」に掲載された『HOLE!!』でデビューした魚喃は、1996年に初の短編集となる『Water.』を刊行。『blue』や『痛々しいラヴ』、『南瓜とマヨネーズ』といった新作を精力的に発表し続け、90年代後半に誕生したこれらの作品はいずれも、「名作」に位置付けられるものとなっている。ゼロ年代に入ってからは発表のペースがゆったりとしていたものの、『strawberry shortcakes』のような名作がやはり誕生している。
一つひとつの作品には、90年代半ばからゼロ年代後半にかけての“あの時代のムード”が収められている。世はインターネット全盛前夜で、オンライン上での他者との交流が当たり前になった現代とは違う。匿名性を帯びたコミュニケーションが生まれつつあった時代の流れに抵抗するかのように、魚喃は生々しい人間関係を描き、心の動きを描き続けた。これらから感じる人間の体温やコミュニケーションの温度感は、いまの感覚からすると少し異質。けれども触れてみるとどこか懐かしい。時代や世代を超えて彼女の作品が広く愛されている大きな理由のひとつだと思う。
やがて2020年の3月末からは9つの過去作が「限定新装版」として連続で刊行され、4月には魚喃自身による『作品解説集』が登場。さらに5月には13年ぶりの新刊として『魚喃キリコ 未収録作品集』が上下巻で発売された。いまとなっては平成という時代が終わって久しいが、当時は元号が変わってからまだちょうど一年というところ。“平成カルチャー”を懐かしみつつ愛情を込めて再評価しようとする平成リバイバル・ブームが話題だが、当時の魚喃作品の動きはまさに、このブームを先取りするものだった。
ここで私と魚喃作品の出会いについて触れてみたい。カルチャーの摂取源は漫画よりも映画だった10代の頃、地元のTSUTAYAで映画『ストロベリーショートケイクス』(2006年)を借りたのが最初だった。あるいは、同じく映画化された『blue』(2003年)のほうが先だったか。いずれにせよ、DVDでの後追いだ。
前者は4人の大人の女性たちの日常を描いたもので、後者はふたりの女子高生の心の動きを繊細に捉えたもの。10代の終わりに差し掛かっていた私には、どちらともえらく刺さったものだった。『ストロベリーショートケイクス』のメインキャストには「岩瀬塔子」の名義で魚喃自身も出演しているし、市川実日子の初主演作である『blue』には原作者としてのポジションから飛び出して魚喃が深く関わっている。いずれも平成の日本映画史におけるマスターピースだ。
こうして10代の終わりに私は魚喃作品に出会った。自然と漫画も手に取るようになり、たまに本棚から引っ張り出してページをめくっては、そこに描かれている人々の心に触れ、その時々の自分の心のかたちをたしかめたものだ。2017年に映画化された『南瓜とマヨネーズ』は劇場で観たし、ふと思い出しては『ストロベリーショートケイクス』のDVDを再生した。魚喃が描く人々の日常は、いつもともにあったのだ。
やがて私は20代の終わりに、彼女の作品と出会い直すこととなった。先述した、2020年の一連の動きがあったときである。そしてこの時期は、私たちの社会にコロナ禍がやってきたばかりの頃だった。他者との間には容易に埋められないほどの距離や壁が生まれ、大切な人たちと次にいつ会えるのか分からない。そんな時期に私は『魚喃キリコ作品解説集』と『魚喃キリコ 未収録作品集』を手に取り、いくつもの過去作のページをめくった。そこに描かれている物語やセリフは変わらないけれど、手触りだけはそれまでと違っていた。
魚喃の作品は、タイトルごとにタッチが違ったりする。『南瓜とマヨネーズ』や『strawberry shortcakes』の質感はドライだが、『ハルチン』などは非常に朗らかだ。私はこれらの作品の共通点として、いずれも「誰かに触れたい」という切実な想いに溢れていることに気がついた。人間の根源的かつ恒久的な欲求である。
あれから5年の時間がとうに過ぎ、他者と触れ合うことのありがたみは消えてしまった。人と人との結びつきに関しては、コロナ禍がやってくる以前の状態に戻ったかのように思える。いや、果たして本当にそういえるだろうか。物理的な距離が消失したいっぽうで、個人の抱える“満たされなさ”や“孤独感”はあの当時より大きくなり、精神的な結びつきは希薄になっている気がする。この原稿を書くにあたって久しぶりに魚喃作品を開き、そんなことを思った。
魚喃キリコの新作に出会うことはもうできないが、彼女の作品は生き続ける。これからも折に触れて、彼女が残した作品を手にしていきたい。私たちが他者と生きていくうえで大切な、根源的かつ恒久的な欲求を忘れないため。そして、他者との心の交歓の際に生じる、あの温もりを忘れないために。