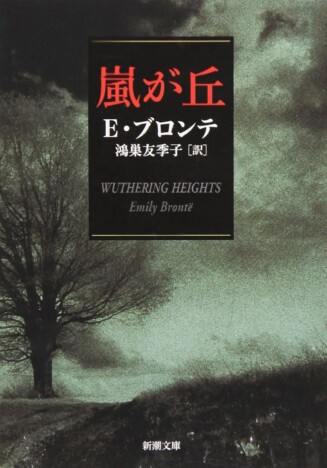久米宏は本当に「反権力」だったのか? 自叙伝が伝える、戦後日本メディア史の一断面
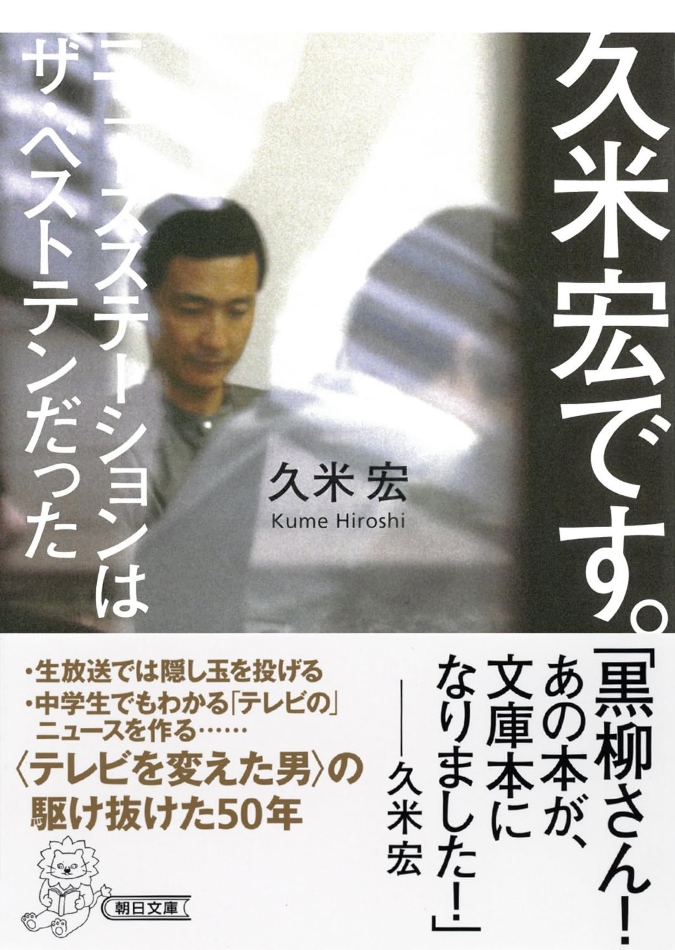
久米宏が亡くなったというニュースが流れた日の深夜、1月13日25時からのTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』でも早速、パーソナリティの太田光が久米の思い出を語っていた。『NEWS23』(TBS)の筑紫哲也が真面目な顔で、命がけで報道番組に向き合っていたのに対し、久米が太田に答えたところによると、彼は『ニュースステーション』(テレビ朝日)をテレビショー、エンターテインメントとして、「視聴者が楽しめばそれでいい」という気持ちでやっていた、という。
エンタメとしてのニュース番組。久米の発言は漫才師に向けられた言葉なのだから本気かどうかはわからない、ということを、太田はあくまで強調していた。確かに、〈政治に忌憚なく物申す反権力のニュースキャスター〉という、没後すぐ盛んに――もっぱら出どころの不確かな切り抜き動画を添えて――広められた久米の社会派イメージに鑑みれば、太田の伝える久米の発言は冗談のように思われるかもしれない。『ニュースステーション』終了時もまだ小学生だった筆者(1991年生)以降の世代であればなおさらだろう。
実際、久米自身も、「初の自叙伝」と銘打たれた著作『久米宏です。』(世界文化社、2017→朝日文庫、2023)で次のように、権力批判というメディアの使命についてはっきり語っている。
メディア、特にテレビや新聞報道の使命とは、時の権力を批判すること以外にはないと僕は信じている。マスメディアが体制と同じ位置に立てば、その国が亡びの道を歩むことは、第二次世界大戦時の大本営発表を例に出すまでもなく歴史が証明している。現政権がどんな政権であろうが、それにおもねるメディアは消えていくべきだ。(227頁)
国内でも世界的にも政治がますますおかしくなっている昨今、このメッセージは素直に力強く響く。
就職面接で重役に「お互い勉強不足ですね」
だが、『久米宏です。』の中でこのメッセージが現れるのはいくぶん後半、全8章のうち第6章にさしかかってのことである。本書を通読して得られる彼のイメージは反権力のシンボルのみにとどまるものではない。むしろより重層的だ。すなわち当意即妙な司会者にしてラジオ・テレビの改革者、そして何より一流のエンターテイナーとしての久米宏である。本書のプロローグが『ニュースステーション』初回の、報道トピックよりも演出の失敗をめぐるエピソードであることにも、それがよく示されている。彼にとって『ニュースステーション』もまた単なる報道番組以上のものであり、そこでの自身の役割もまた単なるキャスターを超えていた。久米の端的な表明を借りればこうだ。
この番組は「久米宏」というタレントの集大成だった。(17頁)
『久米宏です。』という本はこの表明を具体的に肉づけし、説得的に立証することに捧げられている。
演劇青年だった久米はTBSラジオの入社試験からすでに場を演出し、人を楽しませる技術を発揮してきた。目の前の赤電話について話せ、という課題では、その電話で自宅の母親に話しかける、という演技で面接を通過し(有名なエピソードだ)、重役面接では仲代達矢に扮した試験官に、「前の公演はどういう役でしたかね」と答えられない質問をし、「お互い勉強不足ですね」という人を食ったような発言を「サービス精神で」投げかける。入社後も、新たなアナウンサーのあり方や自らの立ち位置について、つまりは役柄について思考していたことを久米は述懐している。これは『ニュースステーション』以降まで一貫したプロフェッショナリズムでもあろう。
本書はまた、久米宏の目――そして耳――を通した戦後日本メディア史の一断面が生き生きと描かれているところも読みどころである。久米が出会い、共演する面々は芸能界オールスター列伝のような様相だ。そして彼はそのそれぞれから、『ニュースステーション』に結実するパーソナリティとしての理念を学び取っている。『土曜ワイド』の永六輔からは自分自身の主張を持つことを、『ぴったしカン・カン』の萩本欽一からはテレビにおける「素」の重要性を、黒柳徹子と司会を務めた『ザ・ベストテン』からはニュース読みの呼吸を、そして横山やすしと共演した『TVスクランブル』からは自由な言葉を(そして少年期のラジオ放送で夢中になった古今亭志ん生の落語からは話術の極意を)、といった具合である。してみると『ニュースステーション』は久米宏の集大成であるだけではない。戦後日本のラジオ・テレビが培ってきた実践知の粋が、彼を通じてそこに流れ込んでもいる。
権力と反権力のクロスオーバー
このようにラジオ・テレビ史と久米宏の遍歴が『ニュースステーション』のソフト面を支えているとすれば、それは豊かな技術と資本、ひいては時代の空気によって物理的に枠づけされ構築されたものでもあった。このことを『久米宏です。』は第4章から第7章にかけて(つまり同書のメインパートとして)詳述している。
建築用資材でセットを作る。ペンの色を服に合わせる。女性アナウンサーの声の高さもコントロールする……『ニュースステーション』のこだわりとして列挙される細部のひとつひとつが、久米のもたらした新しさと創造性を語っている。ミクロの次元がそのように作られているとすれば、マクロの次元で番組を作り上げたのは、TBS独立後の所属事務所オフィス・トゥー・ワンと後発民放のテレビ朝日、そして何より電通だったと久米は言う。平日夜10時台の番組を全て終わらせ、その枠を電通が買い切って『ニュースステーション』は始まった。名声と悪名の双方が轟く大手広告代理店の資本の上で、自民党批判をコアとした自由な言論が展開していたわけだ。これが含意するものはいろいろあるだろうが、少なくとも、権力と反権力、官と民、保守と革新、メインストリームとオルタナティブ、といった対立軸の編成が、現代とはかなり異なっていたのだろうということを実感させられる。
いやむしろ、そうした対立軸を自由に交差させたことに、久米の達成があったのかもしれない。実際、『ニュースステーション』の発明はニュースと娯楽の統合であり、反権力によって楽しませることであり、報道番組の商品化と作品化を同時に達成することだった。本書で強調される、「ニュース番組を作る」「ニュースを番組にする」といった表現の真意はそこにあるのだろう。副題の「ニュースステーションはザ・ベストテンだった」は明快にこの交差を伝えている。
以上のようなことを『久米宏です。』は実に魅力的に語っており、久米宏はすごかったんだなあ、と素朴に思わされてしまう――そう思わされてしまうのはことによると、卓越した演出家としての久米宏の自己演出にまんまと乗せられているのだろうか。放送される言葉のわかりやすさと親しみやすさにも徹底的にこだわった彼の、「生きた言葉」そのものの持つレトリカルな作用にやられてしまっているのだろうか。いずれにせよ、失敗や挫折、擁護の余地なく悪質なセクシャル・ハラスメントの(ショッキングなほどにあっけらかんとした)告白も含めて、彼のストーリーテリングに感服してしまうがゆえになおさら、そのパースペクティブを批判的に捉え返し、描かれなかったことや多面的な解釈に開かれていることを、別の視点から語る必要があるだろう。不謹慎な言い方をあえてすれば、久米宏の死はそのスタートラインとなる。いずれ世に出るだろうさまざまな久米宏論、述懐、検証を聞く準備としても、この自叙伝は読まれる価値がある。