「大谷翔平の影には、打たれたピッチャーたちがいる」 近藤隆夫が語る、近鉄バファローズの「西本イズム」と敗者の美学

「江夏の21球」や「10.19」といった劇的なエピソードで、球史に強烈な印象を残した近鉄バファローズ。球団消滅から20年が経過した今もなお、なぜこのチームはファンを熱狂させ、愛され続けるのか?
スポーツライターの近藤隆夫は、その根源的な魅力を「セオリー通りではない野球」と「敗者の美学」に見出す。伝説の最終戦のドキュメントを収めた書籍『近鉄バファローズ大全 [増補改訂版]』刊行を機に、近藤が語る、愚直さと泥臭さに貫かれた「西本イズム」の魂に迫る。
近鉄バファローズは「不思議な野球をするチーム」

――今回刊行された『近鉄バファローズ大全 [増補改訂版]』(竹書房)は、伝説の「10.19」として知られる88年のリーグ優勝をかけた最終戦のドキュメントをはじめとして、各時代の名プレイヤーのインタビューや貴重な写真も交えながら、近鉄バファローズの魅力と歴史を振り返る本です。どのような経緯で刊行に至ったのでしょうか。
近藤隆夫(以下、近藤):この本は、2013年に洋泉社から出したムックを書籍版にし、さらに新しいコンテンツもいろいろと付け加えたものです。元のムックを出した洋泉社はその後なくなってしまい、ムックの版権もなくなったのですが、あの本を残したいと竹書房の編集者に話したら、企画を通してくれて今回の出版に至りました。
プロ野球ファンは当然どんどんみんな若返っていくし、近鉄という球団が消滅してもう20年以上経ちます。そのなかでバファローズが忘れ去られてしまうのは寂しい。「こんなチームがかつてあったんだ」ということを知ってもらえれば、それだけで今回の本を出せた価値があるかなと思います。
――近藤さんは昔からバファローズファンだったんですか。
近藤:じつはぼくは子どものころから中日ドラゴンズのファンなんです(笑)。ただ、生まれ育った三重県の松阪では、巨人戦のときくらいしか中日の試合がテレビで中継されなかった。

その一方で、パ・リーグの近鉄はいつもどこか気になる存在でした。あるとき、地元局の三重テレビが土曜日に「近鉄バファローズアワー」というデーゲーム中継を始めたんです。それを見てみると、ドラゴンズやジャイアンツとはまったく違う野球がそこにはある。不思議な野球をするチームで、終盤に4~5点差で負けていても、なにが起こるかわからないワクワク感がありました。逆に言えば 大差で勝っていてもやられちゃったりする(笑)。セオリー通りじゃなくて、感情むき出しで、いい意味でプロ野球っぽくない。「このチームは一体なんなんだ」と惹きつけられましたね。
――近鉄はその歴史のなかで、計4回のリーグ優勝を果たしました。西本幸雄監督のもとで初のリーグ優勝を果たした79年は、広島カープとの日本シリーズが最終戦までもつれ、いまも有名な「江夏の21球」として語り継がれていますね。
近藤:あの試合は、当時まだ日本一を経験していなかったほぼ最後のチーム同士の戦いという意味でも熱かったんですよね。最終戦も最後まで緊迫した展開で、広島が最終回に1点差で勝っているなか、リリーフで登板していた江夏豊がノーアウト満塁まで追い込まれるという劇的な流れでした。それを彼が自分で抑えきるまでの一連が「江夏の21球」です。小学生だったぼくはもちろん近鉄を応援しながら見ていたのですが、ノーアウト満塁になったときは「勝った」と思いましたね。そこから代打・佐々木恭介の3 球目、内角のボールを引っ張ったのがサードの頭上を抜けて「やった、サヨナラだ!」と思ったらファールで(笑)。いまでもあれを見ていたときの気持ちは忘れないです。
――そこで負けてしまい涙を飲んだ翌年の80年も、リーグ連覇はしたけれど日本一には届きませんでした。
近藤:それもまた「らしさ」というか、「近鉄って最後はこうなるんだよな」というある種の感慨があって、それがまた妙に感情移入につながったりする。「江夏の21球」でも近鉄はあくまで引き立て役ですしね。
「すごい作品を見たな」と思わされた、伝説の「10.19」
――『近鉄バファローズ大全』のなかでは、88年にリーグ最終戦で優勝を逃した「10.19」を近鉄の最高傑作だと書かれていました。近藤さんは当時現場で試合を見ていたとのことですが、とくに印象に残っていることはありますか。
近藤:あの年は昭和最後の年でした。天皇陛下の病状が悪化しているということで、セ・リーグで優勝したドラゴンズはビールかけもできなかった。他方、パ・リーグでは10月18日に近鉄がロッテに大勝して、あとは19日のダブルヘッダーで2つとも勝てば優勝というところまできた。ぼくは格闘技雑誌の編集部で仕事をしていたのですが、当日職場に1回行ったものの、「こんなところにいる場合じゃない」と思い、廊下でたまたま会った同じ会社の野球雑誌の編集長といっしょに川崎に行きました。第1試合が近鉄の勝利で終わって、ちょっと外へ見に行ったらとにかくすごい人の数なんですよ。いつもガラガラの川崎球場がこんなになるなんて、これはすごいことになったと思いました。
――結局「10.19」は最終戦で引き分けてしまい、優勝できずに終わってしまいました。そのときの球場の雰囲気はどうでしたか。
近藤:球場はロッテの本拠地ですが、当日は近鉄ファンで埋め尽くされていたので、優勝を逃したときはとにかくシーンとしていましたね。集まっていたファンが三々五々帰っていくなか、ぼくは悲しいというよりは「すごい作品を見たな」と思いながらしばらくそこにいました。もちろん残念なのですが、近鉄ファンはある意味「残念慣れ」もしているので(笑)。
――翌年の89年はその雪辱を果たしてリーグ優勝を果たします。
近藤:「10.19」でダメだったときから、「これはもう来年行くな」と思っていました。あそこであんな悔しい思いをしたのだから、チームが変わるだろうと。『近鉄バファローズ大全』にも収録している、当時のエース阿波野秀幸さんのインタビューでも同じことを言っていました。彼は責任感が強いので、「10.19でやられたのは自分が打たれたせいだ。絶対に来年はやり返す」と思ってキャンプにいったら、自分だけじゃなくチーム全体がそう思っていて、雰囲気が完全に変わっていたと。
――その年の日本シリーズでは、初戦から幸先よく3連勝するものの、その後4連敗で敗れるというこれまた劇的な展開でした。いまでは、3連勝後のインタビューで近鉄の加藤哲郎さんが「巨人は(パ・リーグで最下位だった)ロッテより弱い」という発言をしてしまって巨人が燃えたという語られ方もします。
近藤:もちろん3連勝したときは今度こそバファローズが日本一になると思いましたよ。ただ、加藤さんの件は彼がそうともとれるニュアンスの発言をしたのが、新聞紙上で大げさに書かれてしまい、それがのちのち面白おかしく語り継がれているという感じですね。あれはシリーズ後半で巨人・原辰徳のバッティングが蘇ったのがすべてだったと思います(笑)。
大谷翔平の影には、打たれたピッチャーたちがいる
――最後に近鉄が優勝したのは、2001年の「いてまえ打線」のときです。
近藤:あれはちょっと異様でしたね(笑)。防御率はリーグ最下位で、先発ピッチャーの防御率も軒並み4点台というチームが優勝するんですから。とにかく打たれても打ち返して勝つという豪快な野球で、何点取られていてもタフィ・ローズが打って中村紀洋が打って礒部公一もまた打つという。
大阪ドームで優勝を決めた日もぼくは現場にいたのですが、9回表が終わって3点差で負けていたので、当時仕事をしていたスポーツ雑誌の編集部に電話して、「今日は優勝ないから、明日の試合の取材申請とカメラを用意しておいて」と言っていた。そうしたら、直後に北川博敏が有名な「代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームラン」を放ったんです。やっぱりあの意外性が近鉄ですよね。ただ、そういうチームだったので、ピッチングコーチだった小林繁さんはちょっと気の毒でした(笑)。
――近藤さんは彼の生涯を書いた『情熱のサイドスロー 小林繁物語』(竹書房)という本も出されています。小林さんといえば、78年に球界を揺るがせた「空白の一日」事件で最終的に巨人から阪神へとトレードされた悲劇のエースとして知られていますよね。小林さんにせよ近鉄にせよ、近藤さんが取り上げるものに通底するテーマに「輝かしいものの裏側」のようなものがあるのかなと思いました。
近藤:かなりあると思います。たとえば、いま大谷翔平がすごいじゃないですか。「大谷が先発で10個三振をとって、バッターとしても3発ホームランを打った」といったことがクローズアップされますけど、その影には3発打たれたピッチャーたちがいるわけですよ。ボクシングの井上尚弥もめちゃくちゃ強い「モンスター」で、みんなが彼のKO勝ちを期待する。でも、その影にはもしかしたら井上選手以上に必死にやってきたけど倒されてしまう人がいるかもしれない。ぼくはスポーツを見ていて、どうしてもそちらに目がいってしまう。それが近鉄好きにつながっているのかもしれないですね。
近鉄バファローズの魅力は、愚直さと泥臭さ
――近鉄バファローズは2004 年に消滅し、球団の歴史に幕を下ろすこととなりました。
近藤:ぼくのなかでは、球団身売りの報道が出たときにすでになんとなく受け入れる心の準備ができていました。球団がなくなってもちろん寂しいのですが、時代の流れでいろんなことが変わっていくなか、近鉄バファローズはもうその役割を果たしたかなという気持ちもあった。97年からきれいな大阪ドームが本拠地になって、昔からのファンから見るとなんとなく近鉄らしくなくなってきていたというのもありましたね。
――時代の流れですか。
近藤:いまの球場はどこもスタイリッシュないわばエンターテインメントパークで、女性や家族連れも含めてみんなが楽しめる空間になりましたよね。でも、昔はもっと「野球場」だったんですよ。つまり、汚い野次が飛び交う、荒っぽくてある種異様な空間。特にパ・リーグはそうでした。
もちろん、そこから野球の楽しみ方の枠が広がっていまのかたちになったことは全然悪いことではないですし、時代の流れの必然です。ただ、自分が映像を見返そうと思ったときに見たくなるのはやっぱり昭和のプロ野球ですね(笑)。
――ありがとうございます。あらためて、近鉄バファローズという球団の魅力をまとめるとしたらどのようなものになるでしょう。
近藤:近鉄バファローズの魅力は、やはり88年の「10.19」に象徴されるような愚直さですね。そして、それに直結しているのが74年から81年まで監督をした西本幸雄さんの存在です。いわば球団の歴史をとおして受け継がれていった「西本イズム」のようなものが、ぼくにとっての近鉄の魅力です。
「10.19」のときの監督はのちにイチローを見出したことでも知られる仰木彬さんですが、彼も西本さんのもとでずっとコーチをやっていたひとです。西本監督時代の近鉄は、弱いし給料も渋いしで、選手が行きたがらない球団でした。だからいつも戦力が揃わないのですが、西本さんはそれを言い訳にせず、入ってきた選手をとことん鍛え上げて強くしていく。練習もめちゃくちゃ厳しかったのですが、それでも選手たちは西本さんのことを「親父」と呼んでついていく。決してスタイリッシュではなく、あくまで泥臭い。
――その愚直さと泥臭さが、「西本イズム」として受け継がれていったものだと。
近藤:「10.19」そのものだって、本当は相手のロッテにとっては消化試合ですよ。だから近鉄は相手を刺激しなければさらっと勝つこともできたはずなのに、ちょっとしたストライクかボールの判定に全力で抗議しにいったり、逆に相手の抗議には「そちらと違って俺たちは優勝がかかっているんだから早くしてくれ」というような態度をとったりして相手を怒らせてしまう。だからロッテも本気になって近鉄を潰しにきて、感情と感情がぶつかり合うガチンコの勝負になってしまうわけです。
2001年の優勝監督の梨田昌孝さんも、選手時代に西本監督に鍛えられた人でした。しかも、「10.19」で優勝を逃したときに選手を引退して、89年の優勝を経験していない。だから2001年のときは「なんとしても梨田さんに優勝を」という気持ちはありましたね。
西本さん本人とも仲良くさせてもらってよく取材もしました。怖い監督としても知られた人ですが、その一方で感情に裏表がなくて、人間の気持ちを信じる人でした。その人が「われわれは優れたチームじゃないんだから、とにかく練習をやり続けないと強い奴らには勝てないんだ」という姿勢を貫いた。ぼくにとっての近鉄は、ある意味その姿に尽きているのかもしれません。
■書誌情報
『近鉄バファローズ大全[増補改訂版]』
著者:近藤隆夫
価格:2,750円
発売日:2025年10月9日
出版社:竹書房
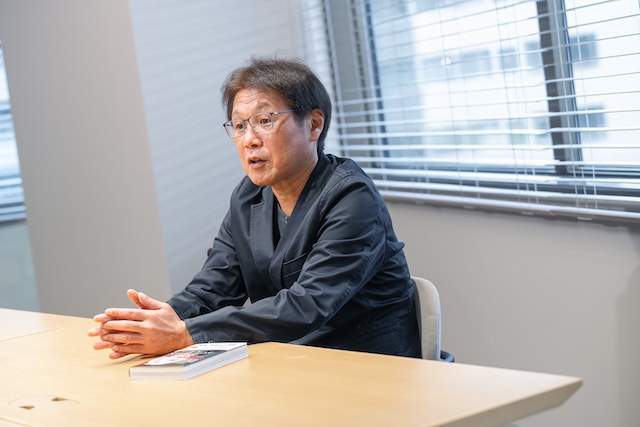

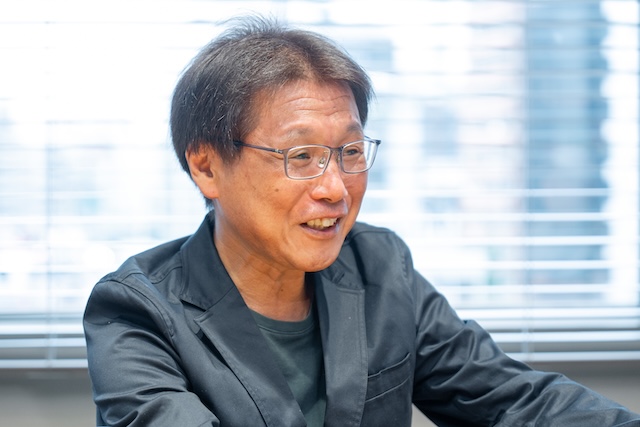
![近鉄バファローズ大全[増補改訂版]の商品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/918i7fwlm9L._SL500_.jpg)























