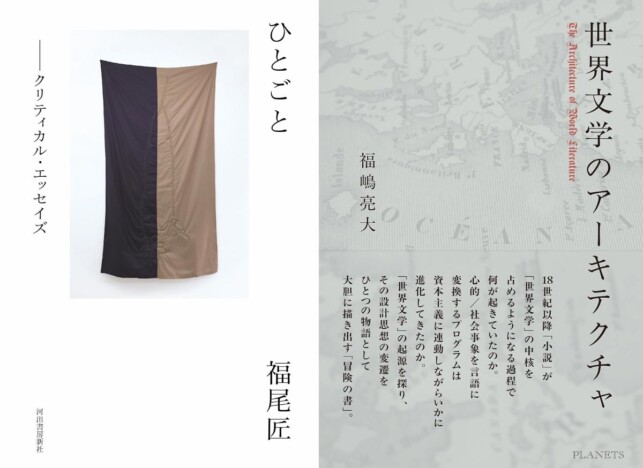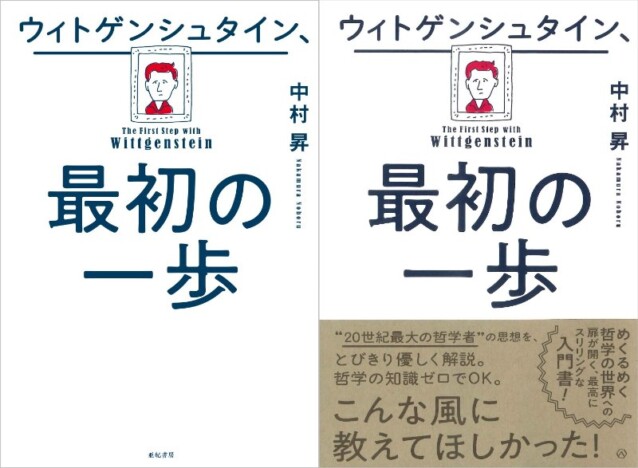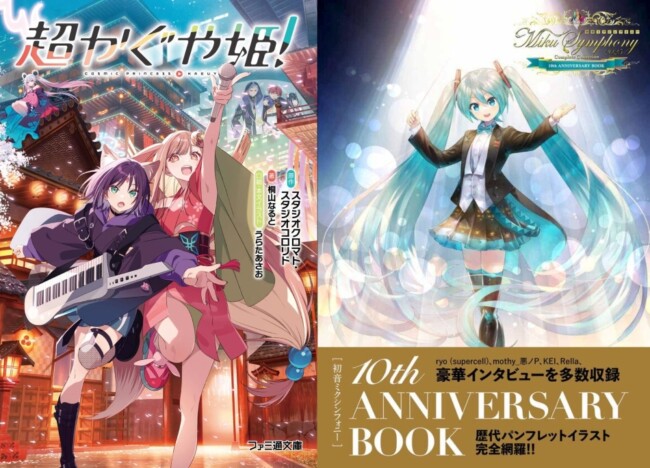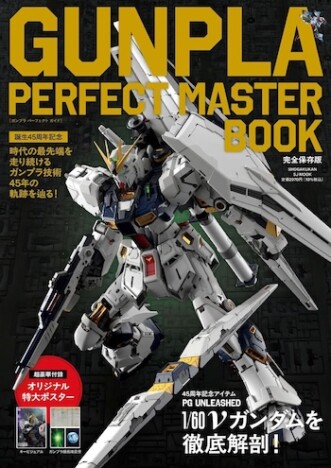「哲学本」ベストセラー相次ぐ背景は? キーワードは「身近」と「切実」
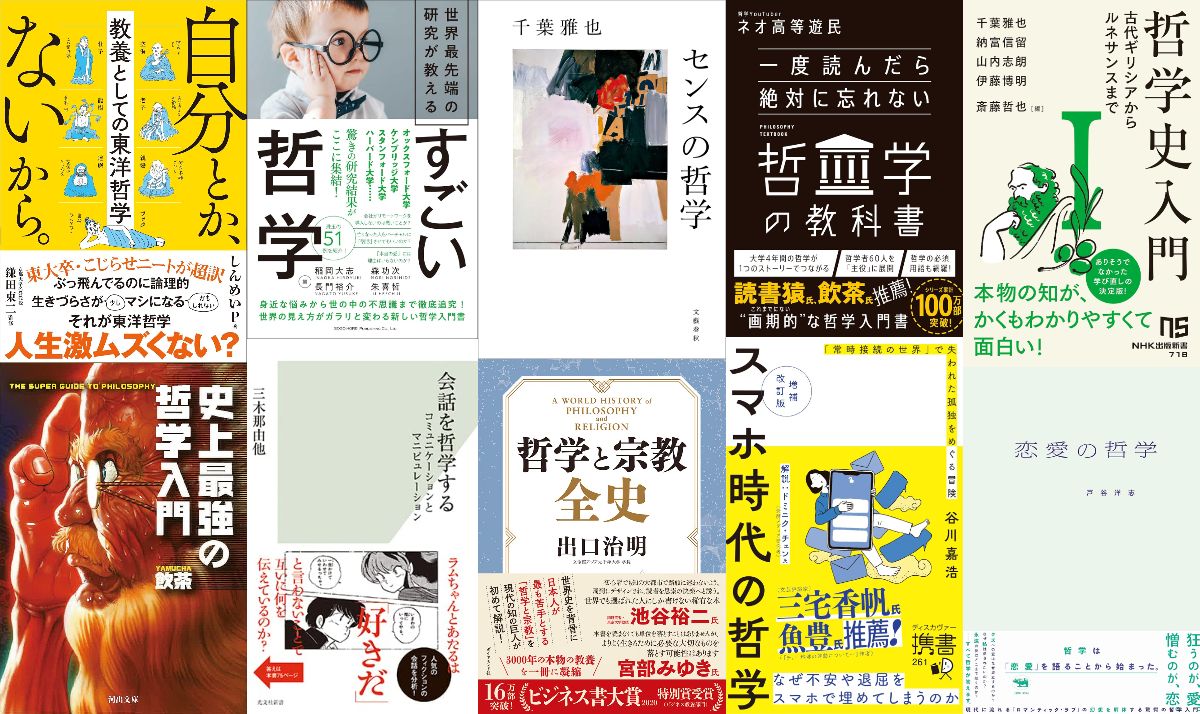
ハードルが高いイメージがある「哲学本」が書店で賑わいを見せている。
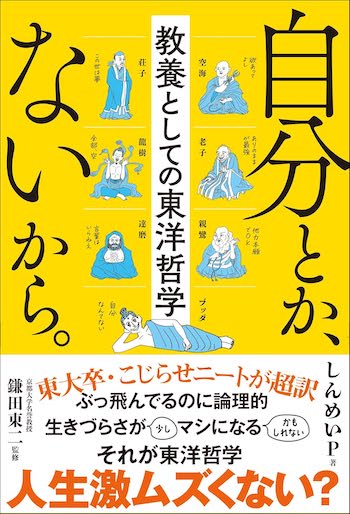
東大卒の”こじらせニート”を自称するしんめいP氏による東洋哲学の超訳本『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』(サンクチュアリ出版)は20万部のベストセラーに。また『グラップラー刃牙』の板垣恵介氏による表紙が目をひく『史上最強の哲学入門』(河出文庫)シリーズの飲茶氏の著書は累計部数68万部を超えるヒット。その他、哲学者の千葉雅也氏による昨年4月の『センスの哲学』(文藝春秋)が5万部を記録するなど、話題の作家が増えているのが「哲学本」ジャンルだ。
哲学は書店では人文コーナーに該当する。だが、近年のヒット作はいわゆる堅苦しい印象はなく、タイトルも表紙もポップなものが目立つ。ビジネス書や自己啓発書、さらにはエンタメコーナーなど、ジャンルの垣根を超えてさまざまな棚に置かれることで、幅広い層の読者との出会いを作っている。
「より身近に」「より切実に」書かれる近年の哲学本
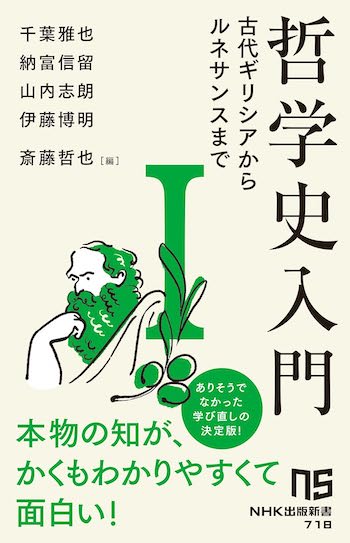
こうした哲学本の中ヒット・大ヒットについて、『哲学史入門』(NHK出版新書)シリーズの編者である人文ライターの斎藤哲也氏は「過去を振り返ってみても、その時々で大ヒットした哲学本がいくつかある」と解説する。
「たとえば80年代であれば浅田彰さんの『構造と力』や、90年代であればヨースタイン・ゴルデルの『ソフィーの世界』など。2000年に入って以降は池田晶子さんの『14歳からの哲学 考えるための教科書』などがヒットしましたし、これまでも大ベストセラーとなった哲学書や哲学入門書はあったんです。ただ、2010年代以降の売れている本を見ると、少し傾向が違う印象がある。それまでの哲学書のような“啓蒙”のイメージというよりは、もっとより身近で、切実なところを主題としたようなものが多い。たとえば千葉雅也さんの『勉強の哲学』とか、東浩紀さんの『観光客の哲学』など、自分や社会の具体的な問題を哲学的に考察していく本が読者に求められている印象があります」(斎藤氏)
ビジネスパーソンの中には、やはり学ぶためのアイテムとして入門本を手に取る人も多いだろう。
昨年3ヶ月連続で刊行された斎藤氏による『哲学史入門』は、「聞き取り形式」によって最前線の研究者たちが語る本格的論考が学べる哲学本で、現在シリーズ累計7万部を超えるヒットとなっている。その他にも、出口治明氏の『哲学と宗教全史』(ダイヤモンド社)や、哲学YouTuber・ネオ高等遊民氏の『一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書』(SBクリエイティブ)など、入門書ひとつでも数多くの話題作がある。
こうした傾向について、山本貴光氏とともに人文系YouTubeチャンネル『哲学の劇場』を主宰する文筆家・編集者の吉川浩満氏は「ここまで来たかというぐらい小さくコンパクトに収められており、いずれも完成度が非常に高い。“教養としての知識”が勢いを失っておらず、より今風の形になっているのが近年の哲学本です」と語る。
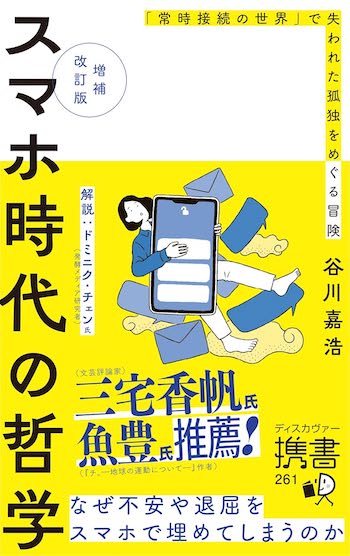
「“より身近に”という部分では、特に若手から中堅の非常に優秀な哲学者の活躍が大きい。千葉さんの『センスの哲学』だけでなく、『スマホ時代の哲学』の谷川嘉浩さんや、『恋愛の哲学』の戸谷洋志さん。そして、『水中の哲学者たち』の永井玲衣さんや『会話を哲学する』の三木那由他さん。また、『世界最先端の研究が教えるすごい哲学』の朱喜哲さん、稲岡大志さん、長門裕介さん、森功次さんも注目されています。こうしためちゃくちゃ優秀な若手・中堅クラスの作家が、それまでの“教養”とはまた違う、より実践的な、あるいは昔の言葉で言う“アクチュアル”な哲学の本を書いており、それが現代の人に受けているのでは。少なくともこの10年20年で、哲学というのは“特別な知識”というよりは、社会で何かをやっていく中での”必須な方法のひとつ”という立ち位置になっているかなと思います」(吉川氏)