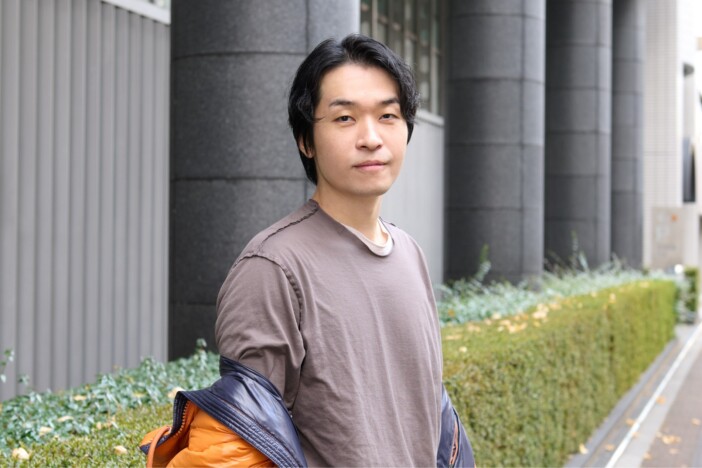「ささやかな嘘を重ねていました」高瀬隼子 芥川賞受賞から3年を経て感じる心境の変化

「まるっと暴かれたようで、ずっと居心地が悪いです」

――執筆されていくなかで、書きやすい/書きにくいといったものはあるのでしょうか。
高瀬:内面のシーンは書いていても筆が進むのですが、例えばお店の描写などは時間がかかってしまいます。自分で「ここに座席があって、店員さんはこの辺にいる」といったようなメモを作るのですが、考えるのが苦手なのか面倒くさいと思ってしまって。反対に内面をフォローするシーンは30分くらいで書けたりするので、我ながら差があるなと感じています。
――高瀬さんといえば、内面描写の豊かさだと個人的に感じています。自分が普段抱いているけれど言語化できなかった感情に言葉を与えてくれる感覚があって、毎度「これだ!」と快感をおぼえつつ、痺れてしまって該当箇所を何回も反復するためなかなか先に読み進められないジレンマがあります(笑)。
高瀬:嬉しいです。ありがとうございます。私自身、小説に書いているような内面のフォローを人に言ってきませんでしたが、書いているぶんには気持ちが良いので好きなのだと思います。
飲み会や友だちとお酒を飲むのが好きでよく行くのですが、その場では広い話に終始して1つを掘り下げる会話はそこまで行いません。ただ、一人になった帰りの電車やお風呂に入っているときなど、「あのときに友だちが言っていたのはこういうことだったのかな」と遅れて考えることが前々からよくありました。自分の頭の中にいる空想上の友だちと話しているような感覚が、内面でぶつぶつ言っている主人公の在り方に似ているのかもしれません。
――高瀬さんは社会人になってからも新人賞に10年ほど応募されていたと伺いました。先ほどお話しされていたように、会社員との両立は体力的に相当ハードですよね。
高瀬:会社員のときは、帰宅後に30分くらいでご飯を済ませて、夜中の1時くらいまで3~4時間はパソコンに向かっていました。ただ、集中して書けていたのは実質1時間くらいでした。いまは専業状態なので書こうと思えば12時間くらい続けられるでしょうが、結局集中できているのは2~3時間なので残業が少ない仕事や週に3・4日のアルバイトだったらダブルワークできていたのかも、とは思います。
――そんな中でも執筆稼働を続けられた理由は、幼少期から小説家に憧れていた想いの強さでしょうか。
高瀬:あとは、無趣味というと語弊があるかもしれませんが、本を読むのは大好きですが滅茶苦茶遊びに行くタイプでもなかったので、夜9時くらいに家に帰ってきてからも特にやることがなかったという事情もあります。書いていた方が落ち着くという想いもありました。
今現在もそうですが、1日2日小説のことを頑張れなかった状態が続くと、「なんで私は生きてるんだろう」と自分を責め始めて、体調が悪くなってしまうんです。ちゃんと小説に向き合い続けた方が心身が健康でいられるため、それがモチベーションかもしれません。デビューしてから編集者の方が担当でついて下さったり〆切が設定されたりといったものが乗っかってきましたが、大元の「書かないと体調に響いてくる」は変わっていないように思います。
――となると、変化はむしろ周囲の方が大きそうですね。
高瀬:小説家になってからも周囲にはほとんど言わず、家族や小説が好きで書いている友だちくらいに明かしていましたが、芥川賞を受賞したタイミングで職場にも親戚にも近所の人にもバレてしまいました。私=高瀬隼子という小説を書いている人、というのが公になったことで自分の中で秘密が一個消えた感覚があります。それまでいつも外の世界に対して持っていた秘密が失われたことで、自分がまるっと暴かれたようで、ずっと居心地が悪いです。
本来、小説家を目指すのは恥ずかしいことではないはずですが、自分に限って言うとそもそもなれると思っていなかったこともあり、なかなか人に言う気になれませんでした。だって「小説家になりたいんだ」と友だちに言っても「頑張ってね」しか返せないじゃないですか。頑張れのカツアゲをするのもなぁという想いがあったため、例えば「土日何してるの?」と聞かれたときも実際は〆切前だから必死に小説を書いているのに「動画とか見てる」などと、ささやかな嘘を重ねていました。
――高瀬さんの作品の登場人物には、人前ではいい子を演じてしまうけれど脳内にはうるさい本音があって――というギャップがありますよね。いまのお話を聞いて、ご本人にも通じる要素なのかな、と思いました。
高瀬:そうかもしれません。デビューした後も職場で小説のことを言わなかったのは、私がイメージする“働いている私”は小説を書いていなそうだったからでもあって、自分が考える私像を勝手に演じていました。そこそこ真面目にやって、飲み会に誘われたら楽しそうにして、土日はNetflixで海外ドラマを観ているんだろうなというふわっとした私のイメージは、「小説家」から外れているように感じていたのと、「小説家をやっています」と言ったときの反応が面倒くさくて避けていたのかもしれません。芥川賞受賞後も職場の元同僚とご飯に行ったりしていますが、「新刊出たね」と言ってくれたり「作家業を頑張っていると聞いたよ」とエールを送ってもらえると、そうさせている申し訳なさを感じてしまいます。