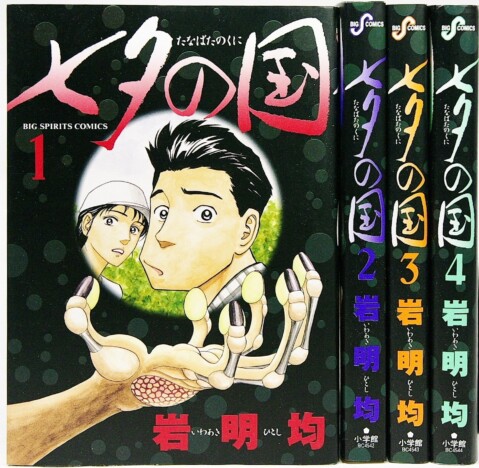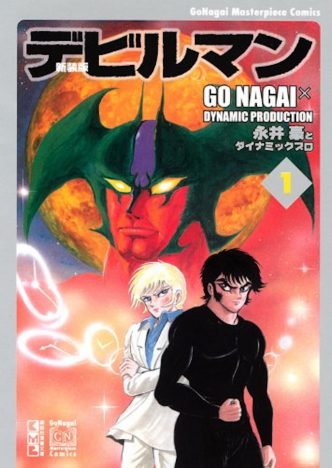岩明均『ヒストリエ』が描く「本」の力と「自由」の意味 長期休載も見届けたい旅の結末

未知の世界への憧憬と守るべきもの
なお、一連の暗殺事件の首謀者は、失脚した第4王妃のオリュンピアス(アレクサンドロスの実母)であったが、エウメネスが“現場”に駆けつけた時、すでにエウリュディケは瀕死の状態に陥っていた。
最期の瞬間、彼女はエウメネスの腕に抱かれてこんなことをいう。「……旅に……行けるといいねえ……」
むろんここでいう「旅」とは「自由」のメタファーであるが、死が目前に迫っているエウリュディケにとって、この言葉は叶わぬ願望であると同時に、何物にも縛られないエウメネスへの熱いエールでもあるだろう。
『本の神話学』(中公文庫)の中で、文化人類学者の山口昌男はこんなことを書いている。
一つの文化のダイナミズムは多かれ少なかれこうした〈旅〉に出かけて来た人間によって再生産されつづけるのである。旅、何処へ? 自分が属する日常生活的現実のルールが通用しない世界へ、自ら一つ一つ道標を打ち樹(た)てて地図を作成しつつ進まなければ迷いのうちに果ててしまう知の未踏の地(ノーマンズ・ランド)へ、書の世界へ、自らを隠すことに知の技術の大半を投じている秘教の世界へ、己れが継承した知的技術を破産させるような知識で満ちているような知の領域へ、である。
つまり、「自分が属する日常生活的現実のルール」が通用するような範囲での移動は、本当の意味での「旅」ではないのだ。「未踏の地」へ足を踏み入れることを恐れていては、いつまで経っても新しい文化を生み出すことはできないし、「自由」を手にすることもできない。そのことを、幼少期以来「書の世界」の旅人であり、また、現実の世界でも命がけの移動を続けてきたエウメネスは肌で知っているのだ。
ただし、いますぐ彼が未踏の地へ旅立つことはないだろう。なぜなら、予期せぬ形でかつての恋人(エウリュディケ)と恩人(フィリッポス王)との間にできた小さな命を託されてしまったからだ。
果たしてこの命は、エウメネスの未来にとって、「柵」となるか、否か。
作者の岩明均によると、本作は今後、連載再開を前提とした長期休載に入るらしい(その間、自分のペースで原稿を描き貯めていくとのこと)。いつになってもかまわないから、エウメネスという漢(おとこ)の旅の結末を見せてほしいと思う。