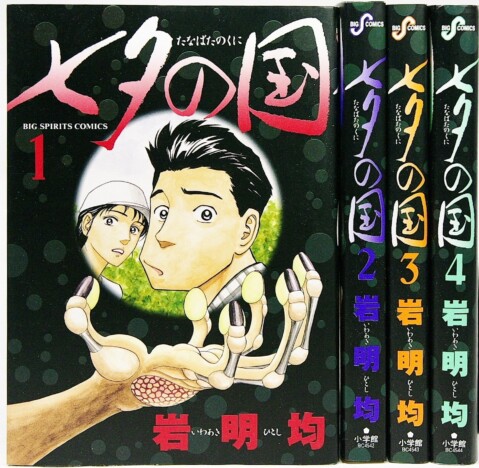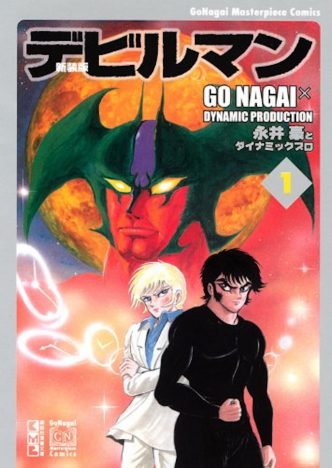岩明均『ヒストリエ』が描く「本」の力と「自由」の意味 長期休載も見届けたい旅の結末

去る6月21日、およそ5年ぶりの新刊となる岩明均の『ヒストリエ』第12巻(講談社)が発売され、あらためて同作への注目度が高まっている。
岩明均の『ヒストリエ』は、アレクサンドロス大王の書記官・エウメネスの生涯を描いた歴史漫画の傑作である。
時は紀元前4世紀――アテネへ奴隷を送るための中継基地として知られる都市カルディアで、その地の有力者の次男として育てられたエウメネスは、のちに「日誌」の中でこう書いている。「今ふり返ると……全てのはじまりはその“図書室”であったように思う」
そう、裕福なエウメネスの家には「図書室」があり、そこで彼は、膨大な「本」(パピルスでできた巻物)に触れることで、“自己”を形成していったのである。「読書」という行為は、何も情報を得るためだけにあるのではない。ましてや、時間潰しのためにあるのでもない。偉大な先人たちが著した複数の書物を読み比べることで、多角的な視点と独自の考えを育むことができるのだ。また、人生の窮地に立たされた時、目の前の壁を乗り越えるための“選択肢”を増やすこともできる。
実際、少年時代のエウメネスは、人とは違った視点で世界を見つめており、自由市民と奴隷たちを“区別”することはなかった。それは一重に、無数の「本」が彼に、人間とは何か、社会とは何か、正義とは何か、自由とは何か、ということを教えてくれたからに違いない。
※以下、『ヒストリエ』のネタバレあり。同作を未読の方はご注意ください。(筆者)
過酷な人生をサヴァイヴしていくための「読書」
だが、エウメネスの幸福な少年時代は突然幕を閉じることになる。ある時、強靭な肉体を持ったスキタイ人奴隷が街で大量殺人を犯し、その騒動の陰で彼の父親(ヒエロニュモス)が暗殺されてしまうのだ。そしてその事件をめぐる裁判の過程で、エウメネスが実はヒエロニュモスの実子ではなく、拾われたスキタイ人であったということが判明する。
その後、彼の人生は一変するのだが(何しろ「裕福な家の次男」から「奴隷」の身に転落するのだ)、彼の心が折れることはなかった。それはやはり、エウメネスが数多くの「本」を通して多角的な視点を身につけた少年であり、どんな辛い境遇に陥っても“自分の頭で考えること”を忘れなかったからだと思われる。
なお、エウメネスがスキタイ人(の奴隷)であったというのは作者の創作だが、このあと彼は、旅の商人に高値で買われたものの、海上で起きた他の奴隷たちによる反乱がきっかけとなり、すぐに「自由」の身となる(そして、いくつかの冒険を経て、アレクサンドロスの父親であるフィリッポス王にその才を認められ、マケドニア王国の文官として成り上がっていく)。
「自由」とは大きな責任を伴うもの
ちなみに、「自由」という概念について、多くの人々は漠然と良いイメージを抱いていることだろうが、真の意味での「自由」とは、孤独で厳しいものなのだ。そのことは、エウメネスの生き方を見ていれば、よくわかる。
なるほどこれまでの人生の岐路において、彼は運だけでなく、出会った人々にも恵まれていたともいえよう。しかし彼は、時に「自由」を貫くため、そんな人々に背を向け、あえて“憎まれ役”を演じなければならないこともあったのだ。
繰り返しになるが、「自由」とは孤独の代償であり、かつてサルトルらがいったように、大きな責任を伴うものなのである。
地平線まで続く「自由」とは
さて、注目の第12巻では、「フィリッポス王の暗殺」という歴史を揺るがす大事件が起きるのだが、その陰で、第7王妃のエウリュディケも殺されてしまう。
実はこのエウリュディケ、短い期間ではあったが、エウメネスと恋仲だったこともあるのだが、ある事情から(詳しくは第85話を読まれたい)フィリッポス王の妻になっていた。
かつてエウメネスに別れを告げた夜――彼女はこんなことをいっている。「誰もが憧れている“自由”は……結局は柵に囲われた『庭』なんだと思う/広い狭いの違いはあっても 地平線まで続く“自由”などありえない」
一方、これまでも「行く手を遮る敵は倒して」きたエウメネスはこう答える。「今度さ……少し遠くまで旅行しない? 本当に囲いがあるのか 見に行ってみようよ」
言葉は柔らかいが、真の「自由」を知っているエウメネスは、そんな「囲い」(柵)などハナからない、あるいは、あったとしても壊してしまえばいい、と考えているのだ。しかしこの時代にそこまで考えられる人間は稀である。
最終的にエウメネスは、「王妃なんかやめちまえって!!」とまでいうのだが、前述のようにエウリュディケはフィリッポス王の第7王妃となり、やがて男女の双子を出産する――。