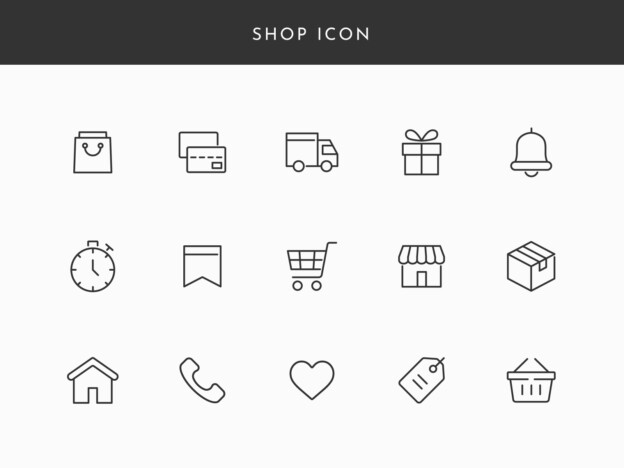リプトン ミルクティーの生成AI小説「恋AI小説」の狙いは? 小説とPRのさまざまな関係性を考察

森永乳業が「リプトン ミルクティー」発売40年記念して、AIで執筆した恋愛小説「恋AI小説」を発表した。この件に限らず、企業が小説を発信するケースは少なくない。クリエイティブな活動に理解があると好印象を持ってもらったり、小説を通してブランドを浸透させたりしようとしているのだろう。「リプトン ミルクティー」の「恋AI小説」はどのような効果を発揮しているのか。また、他の企業が発信している小説にはどのような狙いがあるのか。
リプトン ミルクティー「恋AI小説」は、「リプトン ミルクティー」“旧”発売後にお客さまから寄せられたメッセージ約65,000字からAIが文章を生成した日本初の小説です。約65,000字を平仮名や数字に分解し、1文字ずつ使用回数をカウント。恋愛小説の章ごとに、あらすじや使用可能な文字、文字数を指定し、AIを用いて文章を生成しました。最後に未使用の文字を使用してAIでストーリーを補完し、「恋AI小説」が完成しました。
「恋AI小説」を照会する森永乳業のプレスリリースを読む限り、小説の相当な部分をAIが生成していることが伺える。小説にとって大切なあらすじについては人間が指定しているようだが、登場人物の心情や背景などをつづる文章は、読んでいて違和感がないものに仕上がっている。
高校時代を共に過ごした5人が、10年経って高校がなくなると聞いて改めて集まることになった。成長して自分の道を歩んでいる5人は、再会をきっかけにして高校生だった時、それぞれに起こった出来事を振り返っていく。5者5様の青春と恋愛のストーリーがつづられて、自分の高校時代を思い出して懐かしくなる。そして同時に、今を一生懸命生きていこうという気持ちにさせられる。そんな小説だ。
本当によく出来た恋愛小説で、作品の中に「リプトン ミルクティー」が登場して何かの役割を果たし、商品を印象づけるようなこともない。青春時代の甘い思い出だけが引っ張り出される作品で、これを森永乳業が発表する意味がどこにあるのかと思う人もいそうだ。映画やドラマで行われるプロダクトプレイスメントという手法を小説に持ち込んで、具体的な商品名なり同じカテゴリーのアイテムを小説内に登場させるPR小説が存在していることも、「恋AI小説」の立ち位置を謎めかせる。
NEWSのメンバーとして活躍しながら小説も執筆し、直木賞候補にもなっている加藤シゲアキが、繊維メーカーの東洋紡から依頼され、東洋紡の事業を紹介する小説を執筆したことがあった。「フィルム」「ライフサイエンス」「環境・機能材」という各事業で働く人たちに取材し、それぞれの経験や思いを含んだストーリーを紡いで企業への関心を抱かせるとともに、社会で働く人たちの共感を誘った。加藤シゲアキのアイドルとしての認知度だけでなく、小説家としての力量も加味した企画で、「恋AI小説」とは逆の立ち位置にあると言える。
『桐島、部活やめるってよ』でデビューし、『何者』で第147回直木賞を受賞した朝井リョウも数々の企業PR小説を書いてきた。『発注いただきました!』(集英社文庫)という作品集には、そうした作品がまとめて収録されている。例えば「タイムリミット」は森永製菓の依頼で書いた作品で、3つの掌編にそれぞれキャラメルが登場して、登場人物の成長と変化を暗喩するアイテムとして使われている。
「あの日のダイアル」はアサヒビールの依頼で、ビールの「エーデルピルス」が高貴な香りを持ったビールであることを感じさせるという指定で書いた掌編。海外の企業からプレゼンの結果が届くのを、ビールを飲みながら待っている企業戦士が、注ぎ方が丁寧で香りも違う「エーデルピルス」に感情を刺激され、奮い立つといったニュアンスが感じられる作品になっている。
宣伝コピーのように直接の効能を謳っているわけではなく、短いながらも登場人物の情動が感じられ心を揺さぶられる小説になっているところはさすが朝井リョウ。書かれた経緯を知らずに読んだら、PR小説だとは気づかないかもしれない。それでも、ステマだ何だと言われがちな現代において、単独の小説とするのははばかられたのだろう。同じような経緯で生まれた作品を、『発注いただきました!』にまとめ、発注の経緯とそこへの対処法を添えて、作家としての矜持を示している。
「恋AI小説」からはそうした商品PRの意図は感じられない。誕生したそもそもの経緯は、2年前に「リプトン ロイヤルミルクティー」に切り替わった商品の味を、1年前に以前の「リプトン ミルクティー」に戻したことにたくさんの声が寄せられたから。これに敬意を払い、届いた声にこめられていた商品への深い思いを小説の形にしようとした。
穿った見方をすれば、商品を改良したはずが失敗に終わってマイナスの印象がついてしまったため、ただ味を戻すだけでなく、消費者から寄せられた声を小説にすることで感謝の気持ちを示し、印象をプラスに持っていこうとしたとも想像できる。なおかつ生成AIによる小説執筆という話題を乗せることで、改めて「リプトン ミルクティー」が高い支持を集めていることを知ってもらえる。こうした意図が本当にあったとしたら、企画した担当者はなかなかの策士だ。
もっとカジュアルに、寄せられた声から感じた愛を世の中に小説としてお裾分けしてみたかっただけかもしれない。どちらにしても話題になった段階で、「リプトン ミルクティー」の存在もいっしょに広まっていく。企業として取り組んだ意義はあったということだ。