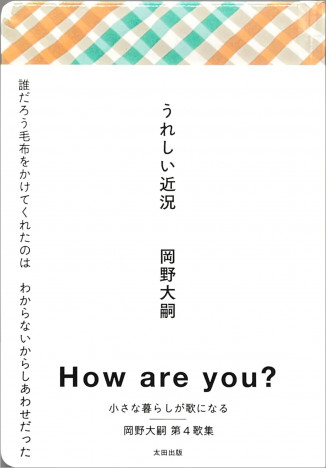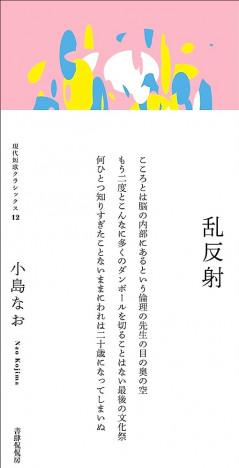本屋大賞ノミネート 津村記久子『水車小屋のネネ』ーー少しの勇気をもって誰かを思いやることの大切さ
2024年本屋大賞にノミネートされた、津村記久子さんの小説『水車小屋のネネ』(毎日新聞出版、2023年)は、毎日新聞夕刊で2021年7月1日から2022年7月8日まで約1年間連載された。連載が始まった頃の紙面には、新型コロナウイルスによる東京都の4回目の緊急事態宣言、そして間近に控えた東京五輪の話題が取りあげられていた。
「第1話 一九八一年」と冒頭で示され、読者はちょうど40年前に引き戻される。コロナはもちろん、携帯電話さえ無い時代だ。
どこに行くの? とホームで律に訊かれて、田舎の方かな、と理佐は答えた。
18歳の理佐と、8歳の律。姉妹は両手に持てるだけの荷物を持って、ふるさとを後にする。母親とその婚約者から逃れるためにーー。
おしゃべりなヨウム・ネネ
物語は第1話から第4話、そして1つのエピローグで構成されている。それぞれちょうど10年ずつ隔たりがあり、つまり1981年から2021年までの40年間が描かれる。津村さんがこれまで手掛けた作品のなかで、最も長い。
第1話では、理佐の視点からふたりの暮らしが語られる。
山間の蕎麦屋で働きはじめた理佐は、店のホールと水車小屋の仕事を任される。水車の動力を利用した石臼で、そばの実を挽くのだ。石臼の上のじょうごにそばの実を補給するのが理佐の仕事で、そのじょうごを見張っているのがヨウムのネネだった。ヨウムはオウムに似た鳥で知能が高く、人間の言葉をよく覚える。そばの実が少なくなってくると「からっぽ!」と言って、理佐に教えてくれるのである。
蕎麦屋を営む守さん・浪子さん夫婦をはじめ、周囲の人々(とネネ)に少しずつ助けられながらなんとか生活していた姉妹だったが、ある日、一人で下校していた律の前に母親の婚約者が現れる。走って逃げたものの、また別の日、今度は水車小屋の近くに姿を現す。そのとき水車小屋には、律とネネだけ。咄嗟に律は、ネネに映画の台詞を大声で喋らせる。
「クイズごっこする?」「テレビは?」「言ってること、わかる?」
少し前に姉妹が観た、映画「グロリア」の台詞だった。「グロリア」は、ギャングに家族を殺され生き残った少年フィルが、同じアパートに住む女性グロリアとともに逃避行する物語である。この台詞は、子供嫌いのグロリアがやむなくフィルを自分の家へ匿った際のもの。
「強くなれ 誰も信じるな いいな」
これはフィルの父親が別れ際、フィルに送った言葉。
「あんたは僕のママで パパで 家族だ それに親友だね 恋人でもある」
これは逃亡中、フィルがグロリアに言った言葉。
ネネが知っている様々な人の声色でこれらの台詞を言わせていると、やがて律の母親の婚約者は水車小屋の近くから去っていった。
律がこれらの台詞を覚えていたのは、どこかで印象深く思っていたからだろう。「クイズごっこする?」などは自分が子供扱いされたくないからだろうし、「強くなれ」は自分に向けられたように感じたから、「あんたは僕のママで パパで 家族だ それに親友だね 恋人でもある」というのは自分と姉との関係に重ね合わせたから。そして律は、「グロリア」の台詞を借りることで、闘う勇気を得ようとしていたのだろう。
勇気を持つこと
第2話は1991年が舞台となり、18歳になった律、そして28歳の聡という青年の視点から語られる。聡は過去に事情を抱えながら、この町に仕事を得て移り住んだ。「何でもどうにでもなったらいいと思ってた」と言う。しかし水車小屋で姉妹をはじめとした町の人々(とネネ)に出会い、徐々に気持ちに変化が起こる。そして少しずつ姉の理佐に惹かれていく。
「きみが近くにいると、自分はたぶん勇気を持つことかできる。(中略)そのことについて、感謝を伝えたかった。どうもありがとう」
理佐は勇気のあるひとだ。でなければ18歳で小学生の妹を連れて、知らない町で生きていこうとしたりしないだろう。進学するはずだった短大の入学金を母親が婚約者に渡してしまっても自暴自棄にならず、たびたび家から閉め出されていた律を守るために勇気ある決断をすることができた。だから、そんな理佐の近くにいると、聡も勇気を持つことができるのだろう。
2022年2月25日、現実の世界では、ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まった。その日の新聞の「水車小屋のネネ」は第3話(2001年)で、ネネはいつも通り水車小屋でラジオを聴きながら歌を歌っていた。そのことに、筆者は束の間、安心したことを覚えている。以後、新聞紙面はつらい話題が多くなっていくが、この小説を読んでいる間だけは、ほっとすることができた。そして、人間の良心を信じることができた。一人ひとりができることはどうしたって限られているけれど、無理のない範囲で、少しずつの勇気をもって誰かが誰かを思いやることが、ユーモアとともに淡々と書かれている。そういう小説を読むことができてよかった、と静かに、強く思った。