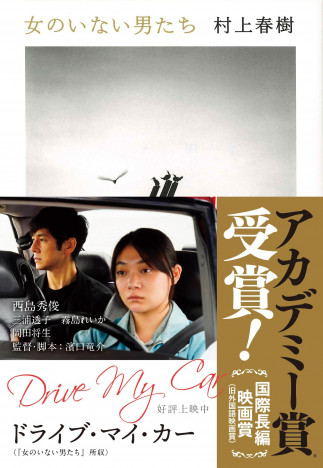村上春樹、新作との関連が囁かれる幻の中編「街と、その不確かな壁」とはどんな作品なのか? 文芸評論家に訊く
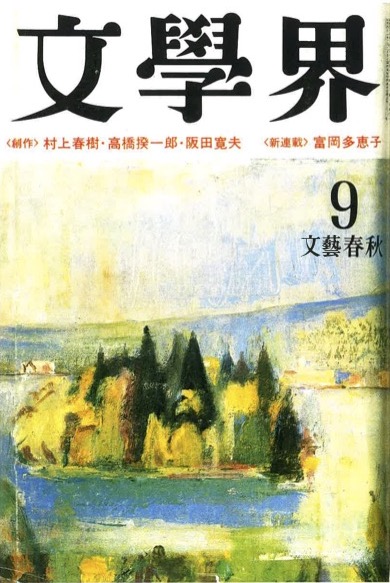

村上春樹の新作長編のタイトルが『街とその不確かな壁』に決定し、新潮社より4月13日に刊行されることが発表された。2017年に刊行された『騎士団長殺し』(新潮社)以来6年ぶりの書き下ろし長編となる。
『文學界』1980年9月号に掲載されたものの、書籍化されていない幻の中編「街と、その不確かな壁」とタイトルが類似していることから、関連性を指摘する向きもある。初期作品の『1973年のピンボール』(1980年刊)と『羊をめぐる冒険』(1982年刊)の間に書かれた作品で、1985年刊行の長編『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のもとになったことでも知られている。
秋、獣たちの体は輝くばかりの金色の毛に覆れる。そして額に生えたしなやかな一本の角はどこまでも白い。彼らは冷ややかな川の流れでひづめを洗い、首を伸ばして秋の赤い実をむさぼる。
素晴らしい季節だった。
僕は西の壁に沿って設けられた古い望楼に立ち、午後五時の角笛を待つ。角笛は長く一度、短く三度、それが決まりだ。柔かな角笛の音が暮れなずむ街角をまるで古い思い出のようにゆっくりと通り抜けていく。
(『文學界』1980年9月号掲載「街と、その不確かな壁」より)
「君」の想像上の街を訪れた「僕」は、図書館の書庫で古い夢の整理をする予言者の仕事をすることになる。壁に囲まれた街には一角獣が住んでいる。「僕」は影を切り離して、この街にやってきたーー『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』読者にとっては馴染みのある設定であろう。
文芸評論家の円堂都司昭氏に、本作の位置付けを訊いた。
「村上春樹は村上龍との対談集『ウォーク・ドント・ラン―村上龍vs村上春樹』(1981年)にて、『街と、その不確かな壁』について言及していました。この対談の中で、龍は『西瓜糖の日々』の著者であるリチャード・ブローティガンに『処女作なんて体験で書けるだろ? 二作目は、一作目で習得した技術と想像力で書ける。体験と想像力を使い果たしたところから作家の戦いは始まるんだから』と言われたことを話し、春樹もその話に共感するような形で三作目のことを話していました。
龍の三作目は、1980年10月に発表された初期代表作『コインロッカー・ベイビーズ』で、春樹の『街と、その不確かな壁』とほぼ同時期に世に出たものです。ただ、春樹にとって『街と、その不確かな壁』は、単行本の三作目として刊行するには納得のいく仕上がりではなかったのでしょう。
龍の『コインロッカー・ベイビーズ』が、前二作(『限りなく透明に近いブルー』『海の向こうで戦争が始まる』)の主人公の傍観者ぶりとは打って変わって、主体的に行動する小説となったように、実際に春樹の三冊目として刊行された『羊をめぐる冒険』もまた主人公が『冒険』する話となっていました。『街と、その不確かな壁』はその後、1985年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に結実しますが、そこに至るためにはまず『羊をめぐる冒険』で、断章形式だった前二作とは異なる、ストーリーテリングに取り組んだ長編をものにする必要があったのかもしれません」
龍に三作目についての助言を与えたリチャード・ブローティガンだが、彼の影響は春樹の方が大きかったのではないかと、円堂氏は続ける。
「『街と、その不確かな壁』は、リチャード・ブローティガンの『西瓜糖の日々』に近い手触りを感じる作品です。『西瓜糖の日々』はコミューン的な場所であるアイデス〈iDeath〉と〈忘れられた世界〉が舞台となっていて、言葉を話せる虎たちが登場しました。それに対し『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は、『西瓜糖の日々』のようなファンタジーである『街と、その不確かな壁』を発展させた「世界の終り」パートに、近未来SF的な「ハードボイルド・ワンダーランド」を付け加えたことで飛躍した小説で、その意味で転機となった作品といえるでしょう」
一方、「街と、その不確かな壁」が『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』とは異なる結末となっているのも注目すべきポイントだ。