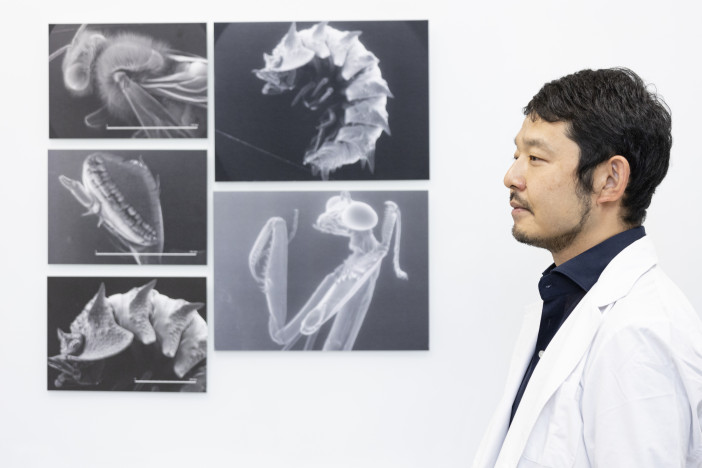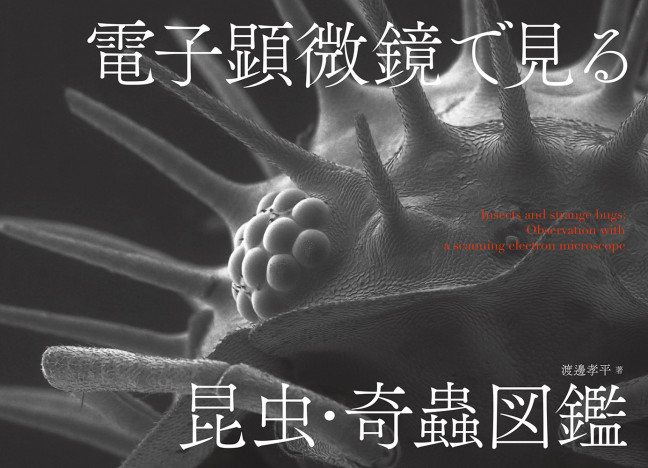昆虫食はもはや当たり前? ウジ虫チーズ、かたつむり水、ウツボの内臓……世界の奇食事情

奇食なんて厳密には存在しないのではないかとも思えてくるが、どうポジティブに考えてもオエッとなってしまうグロテスクな料理も、本書では紹介されている。表面の窪みにたかったウジ虫の排泄物によって独特の質感と風味の生まれる、イタリア・サルデーニャ島の「ウジ虫チーズ」ことカース・マルツゥは、そのビジュアルに口よりまず目が拒否反応を示してしまいそう。アイスランドの糞で燻製したクジラの睾丸ビールや、カナダのバーで生まれた「足の指カクテル」、健康増進を謳うイギリスの「カタツムリ水」は、一杯いかがと言われてもご相伴に預かる気にはなかなかならない。

ローマ帝国の皇帝ともなると、奇食は行き着くところまで行っている。ヘリオガバルスは己の富を誇示するために、あらゆる生物を捕獲して贅沢な宴会を開いた。そこではウツボの内臓、フラミンゴの脳みそ、ラクダの足や生きた鳥から切り取ったとさかも出されていた。ここまでくると料理よりも、権力者のエゴと残酷さの方がグロテスクに見えてくる。
こうした人間の飽くなき食欲によって食べ尽くされ、絶滅していった動物たちの悲劇が、奇食の一種として本書には収められている。捕獲が禁止された稀少種に対しても、ハンターによる密猟は後を絶たない。持続可能な食生活が求められる中で、養殖品の味に文句を付けて野生の生き物の味を欲する人々に、〈料理通たちは、責められるべきは暴飲暴食、そして暴飲暴食を行う人間だけだということを認識するべきだ〉と著者は警告する。
現代において奇食とは、人間の浅ましさが露わとなる食べ物を指すのだとも定義できそうだ。