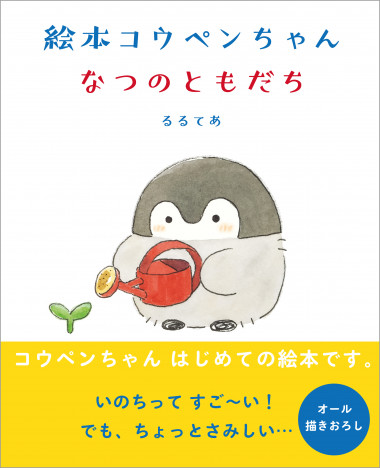大人にこそ読んでほしい、アニメ映画のような絵本ーー小野寺系が読み解く『ドクターバク』の魅力

絵本といえば、小さな子ども向けのもの……というイメージも今は昔。昨今は見た目もかわいくてつい飾りたくなるような絵本や、読むほどに味わい深く心に染み入るような絵本など、大人の趣味として楽しめる絵本が数多く刊行されている。ユニークな発想に唸らせられるヨシタケシンスケの代表作『りんごかもしれない』(ブロンズ新社)や、詩人の谷川俊太郎が人気イラストレーターのNoritakeとともに手がけた反戦絵本『へいわとせんそう』(ブロンズ新社)、子どもに読み聞かせた親も癒されると評判のいぬいさえこ『きみのことがだいすき』(パイインターナショナル)などがその代表例と言えるだろう。
そんな中で注目したいのが、発売前からAmazonの【絵本部門1位】になるなど注目を集めている『ドクターバク』(サンマーク出版)だ。まるでアニメーション映画のような印象を受ける本作は、どんなところが画期的なのか。アニメにも詳しい映画評論家の小野寺系氏に読み解いてもらった。(編集部)
充実する“大人が楽しむ絵本”
エドワード・ゴーリー著の『うろんな客』や『ギャシュリークラムのちびっ子たち』が日本で2000年代に発売され話題を集めてから、“大人が楽しむ絵本”のジャンルは、とくに活況を呈してきた印象がある。
ここで紹介する新作絵本『ドクターバク』も、子どもを楽しませるのはもちろん、大人だからこそ気づける、さまざまな魅力がつまった一作だ。

最初に目に飛び込んでくるのは、緻密にコントロールされた陰影と光や、繊細な色彩感覚。一冊を読み終わると、海外のアニメーション映画を一本観たようなスケール感や満足感を与えられる。そう、この絵本は、まさに大人も大好きなピクサーなどのアニメ映画の世界がそのまま本になっているという印象なのだ。そんな異色といえる本作の内容や、作者の背景を紹介しながら、その魅力の裏にあるものを考えていきたい。
アニメのような絵はどう描かれた?
この、絵本なのにアニメを観てるようなユニークな仕上がりについては、絵を担当した、イラストレーター長砂ヒロの経歴を知れば、納得できるところがある。
彼の師匠といえる存在は、ブルースカイ・スタジオ、ピクサー・アニメーション・スタジオと、アメリカのアニメーション界でもトップといえるスタジオに所属し、『アイス・エイジ』(2002年)、『ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ』(2008年)、そしての『トイ・ストーリー3』(2010年)、『モンスターズ・ユニバーシティ』(2013年)など大きなタイトルで、色彩や照明、美術などのディレクションを務めた、“ダイスケ・ダイス・ツツミ”こと堤大介だ。
美術背景スタッフとして日本のアニメーション作品に参加していた長砂は、ピクサーを退社した堤が独立して、若手アニメーターを求めていたことを彼のブログで知ると、単身アメリカに行って直接コンタクトをとったのだという。同じくピクサーで背景美術監督などを担当していたロバート・コンドウとともに堤が監督した『ダム・キーパー』(2014年)は、アメリカで複数の映画賞を獲得し、アカデミー賞短編アニメーション賞にもノミネートされた。
『ダム・キーパー』は、のちに絵本版が発表されたように、アニメーションでありながら絵本のような、あたたかい質感が大きく評価された作品だった。そこで活躍したのが、ペイントスタッフたち。そのアメリカ人を中心とした顔ぶれのなかで、リード・ペインターを務めたのが、長砂だったのだ。
その後も長砂は、『ダム・キーパー』の製作スタジオ「トンコハウス」で、短編『Moom』(2016年)のコンセプトアートを手がけるなど、アニメーション製作に従事した後に独立。Netflixで配信中の子ども向け教育アニメ『Go! Go! コリー・カーソン』で、リード・カラー・アーティストを務めたり、表現者が協力できる場所となるオンラインコミュニティ「ゴキンジョ」を運営するなど、現在、様々な分野で活動している状況だという。
ここで知っておきたいのが、日本とアメリカのアニメーションスタジオの製作手法の違いだ。アメリカの製作現場では、基本的に日本よりも専門分野が細かく分かれている場合が多い。3DCGアニメーションのトップを走るピクサー・アニメーション・スタジオでは、照明、美術、色彩設計などの分野に、多くの才能ある人員が投入され、それぞれが職人的な技術を発揮するとともに、その後のアニメ製作の常識を更新するような革新的な試みを行っている。出来上がる作品は、そんな総体としての、気が遠くなるような“巨大な芸術”なのである。そこまでやるからこそ、新興の勢力がその完成度に追いつくのは非常に難しいのだ。
ただ、ディズニーやピクサーのスタッフ、アーティストたちに、どれほど才能があろうと、人間一人のやれる範囲はそれほど大きいものではない。業界をリードする作品が巨大化していくに従って、それぞれのアーティストたちの個人的なクリエイティブは、その巨大なプロジェクトに吸収され、個人一人ひとりの才能はなかなか作品として形になっていないのも事実だろう。だからこそ、今回の『ドクターバク』のように、そういったアニメーション業界の個人的才能が作品として楽しめるのは歓迎したいところだ。

『ドクターバク』の絵に見るべきポイントは、まずペイント・アーティストとしての「タッチ」だ。長砂はYouTubeで公開している数々のイラストの制作過程から分かるように、デジタルペイントのブラシで描画するという手法をとっている。近年は、絵本業界でも新しい世代を中心に、画像編集ソフトやペイントソフトを使用することが多くなってきているという。
その利点は、何度も塗ったり消したりを繰り返しながら、画材の限界を意識せずに、一枚の絵にどこまでも手を入れていけるというところ。さらに、何層もペイントした後で、フィルタ機能によって照明効果を出すこともできる。従来の絵本といえば、アクリルガッシュやパステルなどによる“マット”な仕上がりが魅力であり、それは今も変わることはない。だが、デジタルネイティブは、ここに自分たちの世代以降にしかできない特徴を追加することもできるのだ。
アニメーション映画のような構成
主人公のドクターバクは、患者の“こころの世界”に入り込み、そこを汚そうとする「クラヤ実」を食べることができる、お医者さんのキャラクター。“人の夢を食べる”という伝説の幻獣「獏(ばく)」から着想されているという意味では、西洋的な世界観に東洋の要素が加味されたものになっているといえる。
『ドクターバク』からアニメーション映画のような印象が与えられるのには、その構成が影響していると考えられる。冒頭部でドクターバクが患者の「クラヤ実」を食べ、活躍を見せた直後、すかさず作中にタイトルが表れる。これは、映画でいう、タイトルを表示させる前に印象的なシーンを見せる「アヴァンタイトル」にあたる演出である。

そこから、ドクターバクの住む町では不穏な事態が発生する。「クラヤ実」を食べたことで、元気になったはずの住民たちの多くが、さらに大きな「クラヤ実」を抱えて、病院に列をなすこととなるのだ。住民たちに笑顔を取り戻させるため、ドクターバクは「クラヤ実」の謎を解き明かそうとする。この展開に従って、全体のカラートーンにも変化が表れる。
明るい色調から、次第にダークな印象に変わり、暗闇のような世界でドクターバクは奮闘することとなる。そして、試行錯誤しながら彼は、また明るい世界へと上昇していく。心の動きに従って、色彩も変転していくのである。近年のアメリカを中心としたアニメーション、また実写映画でも、この手法は多く見られる。シーンの意味や雰囲気によって、画面の色彩をコントロールし、“色”の面から観客の心理に影響を与えるのだ。ここが、「色彩設計」の技術が発揮される部分なのである。

ドクターバクの辿るストーリーにおける感情は、冒頭の活躍を経て下降していき、クライマックスで一気にどん底まで落ちる。そこから彼は新しい価値観を得て上昇するが、これもまた、映画におけるオーソドックスな脚本の展開である「三幕構成」を基調にしたものだと考えられる。本作から与えられる、娯楽映画的な印象は、ここからもきているのである。