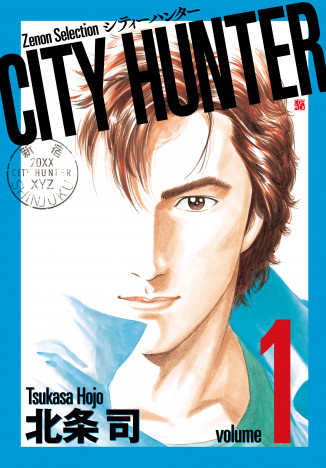「21世紀の映画の可能性」を探る 『明るい映画、暗い映画』刊行記念・渡邉大輔×石岡良治トークショー

批評家・映画研究者である渡邉大輔氏の初の評論集『明るい映画、暗い映画 21世紀のスクリーン革命』(blueprint)が発売されたことを記念し、2月に批評家・表象文化論研究者の石岡良治氏とのトークイベント「21世紀の映画の可能性」が下北沢・本屋B&Bでオンライン開催された。
『明るい部屋、暗い部屋』は、インターネット、スマートフォン、SNS、Zoom、VR、AR、GoProなど、新たなテクノロジーによって21世紀の映画はどのように変容したのかの考察を主眼としている。「明るい画面」と「暗い画面」という見立てでこれからの映画の可能性を読み解く画期的論考から、『君の名は。』『天気の子』『鬼滅の刃』『ドライブ・マイ・カー』など、話題のアニメ・映画を鋭く論じた批評まで、幅広い内容が収録された。
『視覚文化「超」講義』(フィルムアート社)、『「超」批評 視覚文化×マンガ』(青土社)などで、ポップカルチャーを「視覚文化」の側面から鋭く論じてきた石岡氏は、『明るい映画、暗い映画』、ひいては現代映画をどのように見ているのか。公の場ではじめて語り合うというふたりの間からは、映画批評・視覚文化の最前線をめぐる熱い言葉が次々と生まれてきた。本稿ではそのトークショーの一端を紹介する。(若林良)
「変わりゆく映画へのまなざし」
渡邉大輔(以下、渡邉):今回はお越しいただき、ありがとうございます。私は、映画批評や映画史研究のほかに、アニメを含めた映像文化論やメディア論を専門領域としています。それらの分野とも近く、かねて畏敬していたのが石岡さんのお仕事でした。『明るい映画、暗い映画』の第一部においても、石岡さんの過去の議論を参照しました。今回、石岡さんと自分の著書の発売イベントではじめてご一緒できることとなり、とても光栄に感じています。
石岡良治(以下、石岡):ありがとうございます。私自身は視覚文化論、つまりテレビゲームやスマートフォンなども含め、「目で味わう文化」全般が研究領域になるのですが、映画はその中でも特別な位置を占める存在であると思います。ただ、渡邉さんは映画を特権的なものとみなすよりは、その概念がいまどのように変動しているかということに着目して、『明るい部屋、暗い部屋』を書かれていると感じました。
少し長くなりますが、本書から考えたことをあれこれと述べます。映画は1895年に生まれて、すでに2世紀目に入って久しいわけですね。その間には当然ながら、さまざまな技術革新やそれに伴う映画観のアップデートがありました。2020年にはじまったコロナ禍も、「映画」の変化を大きく後押ししたでしょう。北村匡平さんの『24フレームの映画学 映像表現を解体する』(晃洋書房)や、伊藤弘了さんの『仕事と人生に効く教養としての映画』(PHP研究所)のような、映画についての新しい見方を問う本が話題を集めたのも、そうした変化を象徴していると思いますし、『明るい映画、暗い映画』もまた、映画のアップデートに呼応した本の中に位置づけられるのではないかと思います。
映画の変化ということに関して言えば、たとえば本書で触れられているのはアニメーションの変化です。宮崎駿さんと歴史家の半藤一利さんの対談が参照されますが、そこで宮崎さんは、「画面が明るくなった」ことに言及されています。1974年に放映された『アルプスの少女ハイジ』をデジタル化、すなわち、手描きの背景画をコンピュータに取り入れてカラー調整をしたところ、ハイジの赤い服が「強烈な蛍光色」になってしまったことに触れ、こうした激しい色調がいまのアニメーションの主流になっていることが示唆されます。
2020年に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が日本映画の歴代興行収入を塗り替えるメガヒットになったように、現在いわゆる国民的映画の多くのポジションは、アニメーション作品が担っています。そう考えると、アニメーションの変化は一ジャンルの変化に留まらない、映画そのものを揺るがす変化ではあるでしょう。『明るい映画、暗い映画』は宮崎さんの指摘を起点として、映画における明るさ、ひいては新しい映画のあり方について考察していきますが、そのいっぽうで、従来の映画に対する価値観も尊重しています。映画のオーセンティックな見方も尊重しつつ、映画の新しさをとらえようとしていて、それが魅力だと感じます。
渡邉:拙著の要点を的確にまとめていただき、とてもありがたいです。いま、いくつか論点を提示してくださったように思いますので、お答えしていきたいと思います。
まず映画の変容という話ですね。20世紀はしばしば「映画の世紀」と呼ばれていました。20世紀においては、ざっくり言えば、さまざまなメディアの中でも映画は、その時代、あるいは社会に固有の表象秩序を体現する象徴的なメディアだという議論があったんです。ただ、21世紀になると、少し状況が変わってきます。分岐点となったのは、石岡さんの「2世紀目の映画論」という評と関わりますが、1995年ですね。この年は、映画の誕生からちょうど100年のメモリアルな年というだけではなく、「映画」の変動を考える上でも大きな年でした。まず映像分野では、第3次アニメブームの大きなきっかけとなった『新世紀エヴァンゲリオン』や、世界初のフルCGアニメーション『トイ・ストーリー』が公開されたのがこの年でした。またメディア史的にはWindows95が発売され、インターネットの存在が幅広く認知されるようになったのもこの年です。また、Yahoo!やAmazonが生まれたのも1995年ですし、こうした変動を受けて、「画面」の多様化が進んでいくようにもなりました。近年で言えばVR、インターフェース、スマートフォンなどが21世紀に新しく生まれた「画面」に当てはまりますが、そうした過程では映画も当然変化を促されますし、映画が表象の秩序を体現するというよりも、むしろコンピュータやインターネットがモデルとなって、新しい「画面」が生まれるようにもなっていったんです。書き手としても、時代の変化を受け、映画の立ち位置を問い直さなくてはならないと思いました。
そうした問題意識は私のみではなく、先ほどおっしゃられた北村さんや伊藤さんのご著書にも通底されていると思いますし、石岡さんの著作『視覚文化「超」講義』にも変わりゆく映画へのまなざしが感じられます。映画を取り巻く環境が激変し、これまで映画を理解する際の足場になっていたものに頼れなくなったときに、映画を問い直す機運が生まれてくる。大御所で言えば、蓮實重彥さんが2020年に上梓された『見るレッスン 映画史特別講義』(光文社新書)の内容も印象的でした。蓮實さんは良くも悪くも、教養主義と言いますか、「この映画を見ていなければ映画について語る資格はない」といった物言いに特色があったのですが、この本は今までの蓮實節ではなく、「自由に映画を観ましょう」といった軽い語り口になっている。蓮實さんも時代の流れを意識されたのかなと思います。
そしてもう1点、第1部の主要なコンセプトである「明るい画面」についてです。本書では新海誠さんを中心に論じていますが、この概念の着想のきっかけは実は『ミッドサマー』(2019)でした。白夜の村が舞台になるため、画面はずっと明るいのですが、その「明るさ」は『ミッドサマー』のみならず、いろんな映画に敷衍させて考えることができるのではないかと感じ、そこから本書の着想が見えてきました。ただ、「明るい画面」や「暗い画面」については、本書ではそこまで厳密に定義してはいません。それよりは余白を残して、読者の方が自由に意味付けをできるようにすることを意識しています。たとえば先日、このリアルサウンド映画部の鼎談でアニメ評論家の藤津亮太さんとご一緒したのですが、そこでは『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』(2021)の話をして、あれは暗い画面ですよね、みたいな話になりました。こんな感じで、ゆるく抽象的に設定して考えてくれればいいと思ったんです。
「シリーズ」と「ジャンル」について
石岡:『閃光のハサウェイ』で言えば、私はもともとガンダムのファンなのですが、本作はそれを抜きにしても驚きました。戦闘シーンをはじめ、これまでのアニメの定石を離れた、かつ魅力的なシーンが次々と展開されます。アニメーションの場合、見る人が期待するであろうポイントを意識し、その点の魅力を際立たせるように演出が行われるケースが多いのですが、『閃光のハサウェイ』はむしろ、これまでとは異なった視点を観客に提示しつつ、かつ観客がしっかりと満足できる作品になっています。
そして、『閃光のハサウェイ』は単体で完結している作品ではなく、続編も予定されています。もちろん、シリーズものの作品自体が珍しいわけではありませんし、現在ではむしろそちらの方がメジャーではあります。興行収入ランキングで上位になる作品は、先ほど指摘したアニメーションに加え、シリーズものが多いわけですね。映画が持つ特権性として、一つの完成された世界を提示するとか、時間や空間が切り離された感覚を味わえるといったことが語られますが、人気の作品は単体で完結していないケースが多いですし、テレビで再放映される機会も多い以上、その鑑賞において、時間や空間が切り離されているとも言い難い。ただそれでも、映画を見たという感覚もどこかにある。不思議ですね。
渡邉:シリーズものが強いというのは、『アベンジャーズ』(2012-19)然り、『鬼滅の刃』然りですね。おそらくこうした変化を受けて、過去の映画の見方も変わってくる可能性があります。例えば私は最近、マキノ雅弘の『次郎長三国志』(東宝版1952~54年〈全9作〉、東映版1963~65年〈全4作〉)を見ています。『次郎長三国志』は日本のシリーズものを考える上では外せませんが、あれを今見るといわゆる20世紀の古典的映画のモデルからはみ出す要素があって面白いです。例えばあの映画では次の作品でメインとなるキャラクターが、ラスト15分で唐突に現れたりもする。こうした作り方は、いわゆる古典的映画からは完全にかけ離れたものですが、今のシリーズものやスピンオフの想像力に繋がるものがあり、そこに面白さもあります。
私の映画批評は、主に今の映画を対象としています。ただ、私の興味や関心は単純な新しいものにあるというよりかは、既存の文法からかけ離れたものとしての「新しさ」にこそあるんですね。その意味では、『次郎長三国志』も新しい作品と言えると思います。
石岡:なるほど。ただ、続編であるかどうかは別として、どのような作品であっても、先行する何らかの作品、またジャンルの影響を受けないということはありえないですよね。漫画の世界でも『ONE PIECE』も言ってしまえば「やくざもの」とか「アウトローもの」とか、過去のジャンルとしての蓄積の中から生まれてきた作品になりますし。
ジャンルがあれば、その継承もできますし、または伝統に背を向けるところから、新しいものを作ろうという動きもあります。映画史における大きな変革は50年代から60年代ですよね。ハリウッドで言えばアメリカン・ニューシネマ、フランスで言えばヌーヴェル・ヴァーグがそれに当てはまりますが、同時代の日本の変革については、渡邉さんはどのように考えていらっしゃいますか。