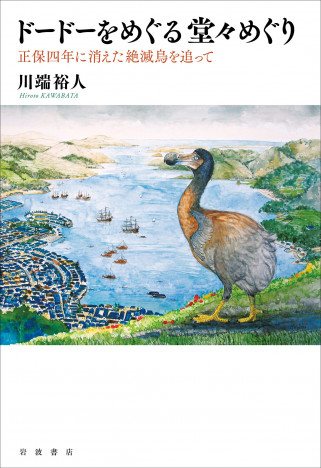『無理ゲー社会』橘玲が語る、自由な社会の生きづらさ 「自分らしく生きられる世の中になったからこそ、利害が対立する」
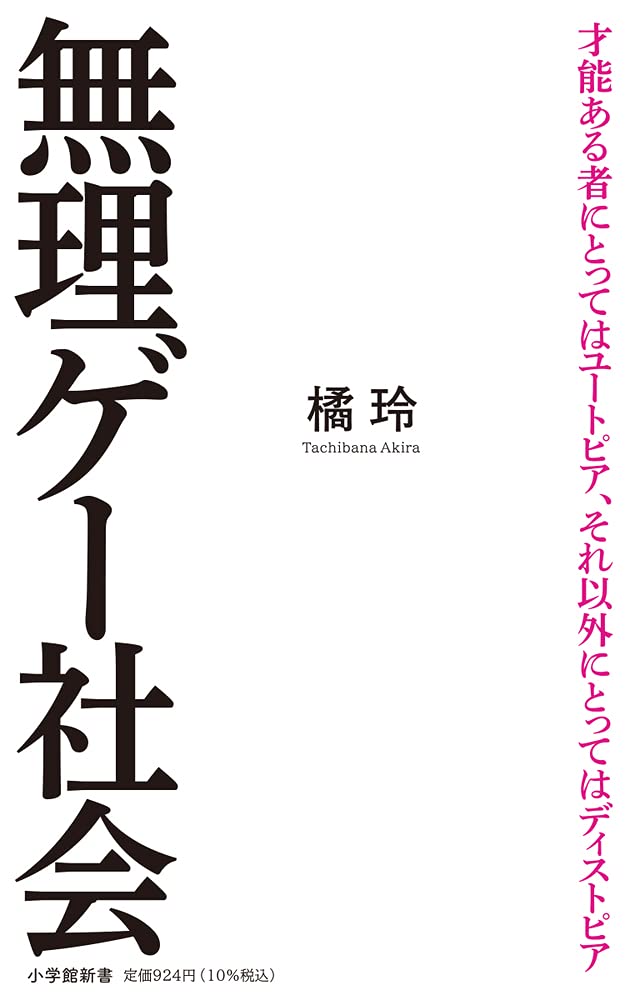
現代社会は誰もが困難なゲームを生き抜くことを強いられているーー。作家の橘玲氏の『無理ゲー社会』(小学館新書)は、リベラルで自由な社会における競争や格差の残酷さを論じている。世界各国で深まる分断の背景には「自分らしく生きる」価値観があった? 知能格差によって開く経済格差、さらに新たに加わる評判格差とは? 橘氏に「無理ゲー社会」論について聞いた。(篠原諄也)
自由な社会の残酷さと生きづらさ
ーー「無理ゲー社会」というテーマにしたのはなぜでしょう?
橘玲(以下、橘):この本は2019年に刊行した『上級国民/下級国民』(小学館新書)の続編の位置づけです。現代社会の生きづらさがさかんに語られますが、昔と比べて客観的には生きやすくなっている。豊かさや安全性、スマホのようなテクノロジーなど、どんどん便利で快適になっていますよね。それにもかかわらず、生きづらさを訴えて、ある種のルサンチマンをぶつける人たちが増えている。これはどういうことなのか。これまで「リベラル」を自称する人たちは、「資本主義」や「新自由主義(ネオリベ)」という悪があって、それを打倒すれば問題は解決すると言ってきた。でも、本当にそうなのかと思いました。
みんなが自分らしく生きられる世の中になったからこそ、社会のあらゆるところで利害が対立して、生きづらくなっているのではないか。たとえば、恋愛が典型的です。昭和30・40年代の日本は婚姻率が100%に近く、相手のことをよく知らないままお見合いで結婚するのもごくふつうでした。当時は貧しく、男女の雇用格差も今よりずっと大きかったので、女性は生活を成り立たせるために20代で適当な相手を見つけて結婚するしかなかった。
今の若い人はお見合いなんて想像できませんよね。仕事を自由に選べるように、自由に結婚相手を選べるようになれば、当然、「自分らしい」相手を探すようになります。そうなると、良し悪しはともあれ、男性の場合は年収、女性の場合は年齢(若さ)で選ばれる傾向が強くなり、結婚したくてもできない人が出てくる。
こうした傾向はとりわけ男性に顕著で、2020年の国勢調査では、50歳時点の男性の未婚率は28.3%で3~4人に1人になりました。それとともに女性の未婚率も上がっていますが、それでも17.9%で6人に1人。この差が生まれるのは、結婚と離婚を繰り返して複数の女性と性愛関係になる男がいるからで、これは「時間差の一夫多妻」と呼ばれます。
このような状況において、自分の力では攻略できない「無理ゲー」のなかに放り込まれてしまったと感じる若者がかなりいるのではないか。あるニュースサイトのインタビューでそんな話をしたところ、そのあと会った20代男性の編集者やライターから「すごく刺さった」と言われて、「無理ゲー社会」というタイトルを思いつきました。
ーー今の社会は誰もが「自分らしく生きる」ことを強いられていると論じています。橘さんはそのことについて否定も肯定もしていないように感じましたが、その価値観をどう考えていますか?
橘:「自分らしく生きる」というのはひとつのイデオロギーというか、1960年代にアメリカ西海岸の若者たちが言い出したまったく新しい価値観です。それ以前はずっと戦争がいつ起きてもおかしくない時代で、自分が戦場に送られる、あるいは家族を戦争で失うというリアリティを誰もが抱えていた。ところが第二次世界大戦のアウシュビッツとヒロシマ・ナガサキのあとでは、もはや大国同士の戦争は不可能になって、人類史上はじめて「長い平和」の時代が到来しました。国家が戦争で植民地を拡大することも全否定され、「国家は何のためにあるのか」の理由が「国民を幸せにするため」に変わった。植民地主義国家から福祉国家への大転換です。
そんな「とてつもなく平和で、とてつもなく豊かな」社会で生まれ育ったベビーブーマーたちが、20代になって、「自分らしく生きることに価値があるんだ」と自然発生的に言いはじめた。60年代末の「セックス、ドラッグ、ロックンロール」ですね。それがパンデミックのように、またたく間に世界じゅうの若者を虜にしていく。
『無理ゲー社会』では、アメリカ西海岸の文化革命(カルチャーレボルーション)のイデオローグ、チャールズ・ライクを紹介しました。著書『緑色革命』でライクは、自分の内面を探検(インナートリップ)し、“ほんとうの自分”を見つける「意識の変容」こそが60年代カウンターカルチャーの本質だと論じました。ライクはイェール大学の法科大学院を首席で卒業し、30代で母校の法学教授になったエリート中のエリートですが、同性愛者として、保守的なエリート文化のなかで「自分らしく」生きることができず、ずっと苦しんでいた。ライクにとって「自分探し」は、大学教授の地位や名誉を捨て、全身全霊をかけるに値するある種の「宗教体験」だったんです。
これはキリスト教やイスラームに成立に匹敵する決定的なパラダイム転換ですが、私たちはそのパラダイムのなかに生まれて生きていくしかないので、その影響の大きさがわからなくなっている。「誰もが自分らしく生きる社会を目指すべきだ」というリベラリズムは強固な共同幻想になっていて、もはや保守派ですらそれを否定できない。だとしたら、そういう社会で生きていくことを前提に、自分の人生を考えるしかない。1万円札はただの紙ですが、それに価値があるとみんなが信じているから実質的な価値が生まれる。そのとき、「1万円札は紙切れだ」と叫んでも意味がないのと同じですね。