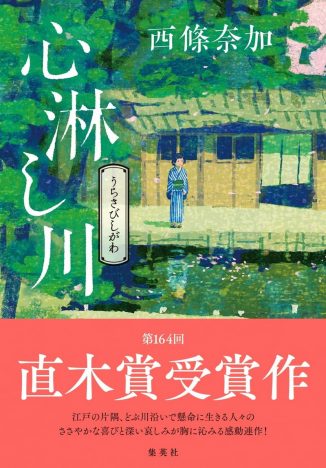NEWS 加藤シゲアキの作家としての強さとは? 『オルタネート』担当編集者が語る才能と魅力

2020年11月に新潮社から出版された加藤シゲアキの長編小説『オルタネート』は、3月14日現在、17万8000部が発行されている人気作品だ。高校生たちを中心とした爽やかな青春群像劇で、SNSのコミュニケーション世界や音楽、料理、園芸、恋愛などのモチーフが、優れた心理描写や情景描写をもって構成・表現されている。まさに加藤シゲアキ渾身の著書と言える同作品は、直木賞をはじめ、本屋大賞、といった複数の文学賞候補に挙がっており、吉川英治文学新人賞を受賞し業界における評価も高い。また連載した「小説新潮」を創刊以来初の重版に導くなど大きな話題となったことからも、従来のファンのみならず多くの読者に受け入れられていることが分かる。
今回、そんな話題の作品を担当した編集者、新潮社 出版部文芸第二編集部の村上龍人氏にインタビュー。ジャニーズの人気アイドルグループ・NEWSのメンバーとして多忙な日々を過ごす加藤シゲアキの、作家としての強さ・魅力について、また『オルタネート』が本になるまでの舞台裏について訊いた。なお村上氏は、新卒入社後9年目の30歳。「週刊新潮」の記者を経験し5年目から文芸担当へ異動した。33歳の加藤シゲアキと年齢が近いからこそ共有できる同時代のリアリティや世界観は、この作品に携わるなかで大きな追い風になったという。

書き下ろしの予定から連載へ。目まぐるしい1年間
ーー『オルタネート』を担当することになった経緯についてお聞かせください。また加藤シゲアキさんにはどのような印象をお持ちでしたか?
村上龍人(以下、村上):加藤さんがこれまでいくつかの出版社や編集者とお仕事をされてきたなかで、今回初めて新潮社でご執筆の機会をいただいたのですが、その際、上司から「村上は年齢も近いだろうし担当しないか?」と声をかけてもらいました。それまでに加藤さんの本を読んで作家としてもとても才能のある方だなと思っていたので、迷うことなく手を上げました。
加藤さんの小説デビュー作である『ピンクとグレー』は私が大学生のときに出版されたのですが、当時「タマフル(ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル)」というラジオ番組を聴いていたときに『ピンクとグレー』が出版されるにあたって特集されている回があったんです。最初は「アイドルでありながら本を書くなんて、世の中にはたいそうな人がいるものだ」というくらいの印象でしたが、その後『Burn.(バーン)』を読んだとき、衝撃を受けました。作品として完成されているなと。「天才子役」と称されるがゆえに、孤独を抱えていた主人公が渋谷を舞台に、ホームレスやドラァグクイーンとの交流を通じて成長を遂げていくストーリーなのですが、この作品は構成面が非常によく練られていて、この年齢とキャリアで書けるとは本当に力のある人だなぁと思いました。そうして他の作品も読み、加藤さんはエンタメの小説を書く素質がもともと備わっている、将来性ある作家だと確信しましたので、担当させてもらえるのは率直に嬉しかったです。
ーー実際に担当してお仕事をするなかで感じた"作家・加藤シゲアキ"の特徴や強みについてお聞かせください。
村上:まず感じたのは、作家的な体力のある人だということです。どんなベテラン作家さんでも、作品をより良くするためには編集者との意見交換を通じた改稿作業が必須となりますが、この作品も、完成するまでに幾度も打ち合わせをして直しました。加藤さんに第一稿をいただいてから、「小説新潮」で連載をスタートするまでに5〜6回直していますし、連載にあたっても、毎号、数回にわたって改稿しました。そして単行本化するために、連載していた内容を再度点検し、全体の整合性を見ながら、さらに細かいブラッシュアップを図っていきました。
改稿能力は、作家の実力が表れる重要なポイントのひとつだと考えています。たとえば、直すアイデアを1つ提案したものに対して10返してくれることが、編集者としては嬉しいんです。所詮、編集者が出せるアイデアには限りがありますし、1を10にも100にも膨らませられるのが作家さんのすごいところだと思いますので。加藤さんとのやりとりでは、改稿の原稿をいただく度にどんどん内容が良くなっていくのを実感しましたね。作家としてもそうですが、アイドルとして歌やドラマ、舞台などをやっていますし、創作というものへのフィジカルの強さがもともと備わっているんだな、と感じました。
『オルタネート』は2019年の冬くらいに原稿が書き上がり、その後に「小説新潮」で連載をすることが決まりました。かなりイレギュラーな進行になりましたし、刊行直前の時期はスケジュールがすごくタイトでしたので、そうしたなかでここまで妥協なく作品のクオリティを最大限引き上げていただいた。あらゆる点で、やはり並外れているなと思いました。
そんな力のある加藤さんだからこそ、無茶な相談をいくつもしたと思います……。例えばラストシーンの描写について、すでにこのまま校了しても差し支えのないクオリティであったのですが、細かい表現や言い回しなど、「もしかしたらさらに良くなるのでは?」と欲が湧いてきてしまい、翌日の昼が本当にギリギリの校了のタイミングなのにもかかわらず、さらなる改稿の相談をしました。その後深夜までメールのやり取りを続け、最終的に朝9時頃に完成原稿をいただきました。ただ、加藤さんのように馬力があって、改稿能力の高い作家さんだからこそ対応できたという側面もあり、実際にかなりの無理を強いてしまいましたし、率直に反省もしております……。とはいえ、この頃には直しを繰り返すたびに原稿のクオリティがあがっていくことに快感を覚えていたこともまた事実。加藤さんや私、「小説新潮」の担当編集者はもちろん、校閲の担当者や装幀のデザイナーを含め、『オルタネート』に関わっている皆が、ここまできたら最後まで妥協なく良い作品にしよう、と半ばムキになっていたように思います。

ーーほぼ同世代ということで、作品をつくり上げていくなかで意識したことはありますか? またこの作品への思い入れについてはいかがでしょうか。
村上:どんな作家さんとの付き合いでも、最初はお互い手探りなところがあります。やはりコミュニケーションが仕事の基本にあるので、まずは信頼関係を築けないと、どこかでボタンを掛け違えたりして改稿作業はなかなか上手くいかないかもしれません。その点では、私や「小説新潮」の担当編集者もみな、加藤さんと年齢が近く共通言語として「あの映画のアノ感じ」みたいな話ができましたし、同じ方向を向いて改稿ができました。加藤さんはアイドルであり、「演じ手」側にいる人なので、もちろん経験してきた濃さや密度は違うでしょうけど、通ってきたカルチャーは割と共通の部分がある印象も受けました。
そのなかで、お互いに「もっと良くなるのではないか」という意識を常に持っていましたね。この作品は本来オルタネートというSNSのマッチングアプリがストーリーの軸にあるのですが、連載時の原稿は、より学園ドラマとしての趣が強くなっていました。ただ、最終的に一冊の本として読んでもらうときは、もっとオルタネートという存在をそれぞれの登場人物と密接に関わらせ、その上で「SNSやコミュニケーションへの向き合い方をどう捉えるのか」「どう意識が変化していくのか」を見せていったほうが、物語の強度は高くなると感じたんです。そこで、「小説新潮」の担当編集者とともに、加藤さんにそのことを伝えました。すると加藤さんも同様の考えを抱いていたようで、さらに面白いアイデアをたくさんいただき、その後の改稿もスムーズに進みました。
このような改稿を重ねていくなかで、いつしか私も登場人物への思い入れが生まれてきて、「彼らの親戚のおじさん」になったような目線で作品を読むようになっていきました。「この子たちが幸せになるためには、いいエンディングを迎えるためには、どうしたらいいんだろう?」と。そうしたやりとりを経て、登場人物たちがどのような決断をするのかを、より自然に想像しながら、改稿のご提案をするようになっていったと思います。
加藤さん自身、年齢的なものを含めて10代の青春小説を登場人物に寄り添って書けるのはこれが最後かもしれないと考えるなかで、「10代のショーケースを目指した」とも仰っています。誰が読んでも、登場人物の誰かしらに共感してほしいとの想いで、いろいろなキャラクターを自分の経験に寄せながら書いていたようです。