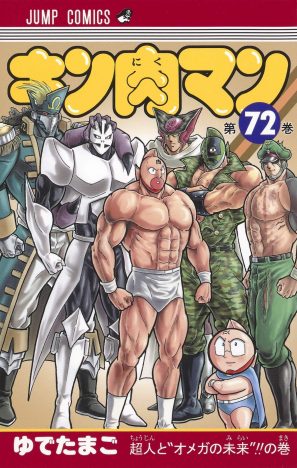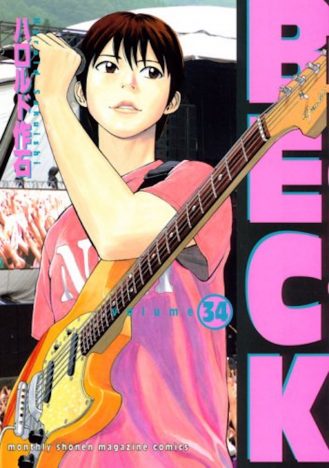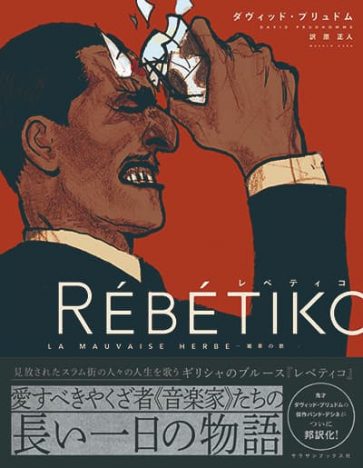『キン肉マン』名勝負ブラックホールvsジャック・チー戦に見る、“別人格ギミック”の面白さ

プロレスとギミック
プロレス的視点から『キン肉マン』の各シリーズのベストバウトを紹介する本コラム。第一回では、“名タッグ”として語り継がれる2000万パワーズのベストバウトを紹介した(参考:『キン肉マン』2000万パワーズ、“名タッグ”として語り継がれる理由 プロレス視点のベストバウトを考察)。第二回では、「完璧・無量大数軍編」(コミック38〜45巻)の中から選出。2011年から連載開始した本シリーズは名勝負揃いで正直選出するのに悩んだ部分もあったが、プロレスならではの醍醐味を感じられる試合として、以下の試合を取り上げることにした。
ブラックホールvsジャック・チー戦。
プロレスラーの特徴として、同一人物が自身のビジュアルに何かを加えることによって別のキャラクター、人格となることがある。例えばマスクを被ればそれは素顔のレスラーとは別のレスラーとして認識される。例えば2代目タイガーマスクが試合中に自らの意思でマスクを脱ぎ去った試合があったが、脱いだ瞬間から彼はタイガーマスクではなく、三沢光晴になった。もはや目の前の彼にタイガーコールを叫ぶ客はいない。会場に響くのは三沢コールである。

同様の別人格ギミックとしてフェイスペイントがある。代表的なところでは、ナチュラル・ボーン・マスター、武藤敬司とグレート・ムタの関係だろう。絶対的ベビーフェイスの武藤が、顔にペイントを施すことによって、最凶ヒールのグレート・ムタになる。善と悪の顔を巧みに使い分けて、武藤は世界中のレスラー、ファンからリスペクトされるレスラーになった。武藤とムタは同一人物でありながらまったくの別人格キャラクターとして扱われており、試合中、武藤で対戦していた際に相手から「ムタで来い!」と言われ、場外乱闘の最中に控室に戻り、ペイントを施してムタとしてカムバック、壮絶な狂乱ファイトを繰り広げ、なぜか試合もそのまま成立してしまったということもあった。
このようにプロレスにはギミックを施すことで別人格に”変身”し、それによるバラエティあふれるファイトをお客さんに提供することができるレスラーが存在する。彼らの存在はプロレスというジャンルの大きな魅力の一端を担っている。
その”変身”ギミックを思わぬ形で試合に生かしたのがこの試合である。ダルメシマンとの戦いのダメージを残すブラックホールは完璧・無量大数軍の”完流”ジャック・チーとの連戦に挑む。其の名前から容易に想像がつくと思うが、両腕、両足の蛇口から熱湯、冷水を射出して戦う、いかにもキン肉マンらしい、10歳の子どもが考えたかのような”完璧な”ギミック超人である。攻防どちらにも使えるボイリング・ショットの前にブラックホールは大苦戦。己の四次元殺法をことごとく封じられて、起死回生の吸引技、「至高のブラックホール」を発動するも、それすらジャック・チーには通用せず、万事休すかと思ったタイミングで、どこからともなく声が聞こえてくる。そしてその声に呼応してブラックホールが放った最初で最後の禁断の必殺技が……。
黒いブラックホールの体がめくれ返ったら、白いペンタゴンになった。
ここに新たなゆで伝説が生まれることになった。そもそも先の超人タッグトーナメント編でキン肉マン、キン肉マングレートのマッスルブラザーズの一回戦の相手を務めたのが、ブラックホールとペンタゴンの「四次元殺法コンビ」であった。ブラックホールの四次元感はわかるが、超人オリンピック、ザ・ビッグ・ファイトでウォーズマンになんのいいところもなく惨敗したペンタゴンのファイトには、何一つ四次元感はなかった。
しかしこのペンタゴン、当時の小学生の間ではカルト的に人気があった。理由はただ一つ、”顔が描きやすいから”。実は子どもにウケるキャラクター要素の一つとして描きやすさというのは重要な要素を占めており、意図してそれがデザインに組み込まれていることは往々にしてある(余談だが、仮面ライダー555はまさにそれを意識したデザインだという話を聞いたことがある)。当時の子供たちの間でラーメンマンやロビン、ウォーズマンに人気があり、テリーマンやブロッケンJrの人気があまり振るわなかったのは、間違いなく顔の描きやすさが影響していた。
そして言わずもがな、ブラックホールもそっち系の超人である。おまけにボディのカラーがそれぞれ白と黒。並べてみたらシックリきたのだろう。ゆで先生がペンタゴンにサラッと謎の四次元ギミックを後付けで付与することで、本来なんの接点もなかった二人の超人は、あたかもそうなることを運命付けられていたかのように完璧なタッグチームとなってしまったのだ。