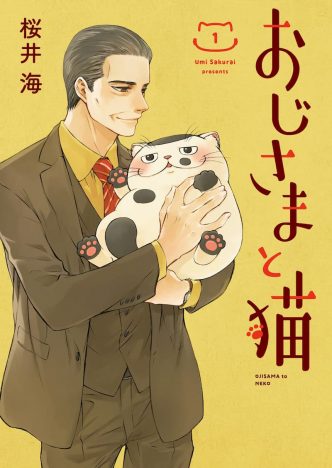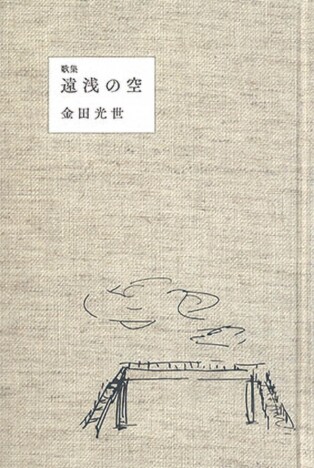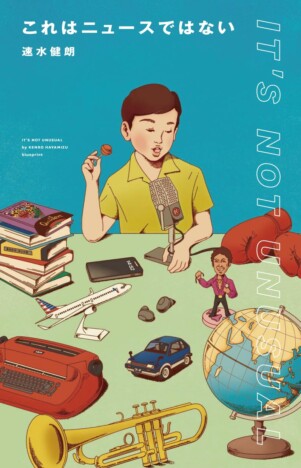亡くした猫も、貰われていった猫も、すべて愛おしい……猫歌人が詠む「猫の短歌」

猫と暮らす年月が長くなるにつれ、自分がどんどん「猫好き」から「猫バカ」に変わっていっているような気がする。引っ掻かれると喜び、噛まれるたびにニヤニヤする筆者はきっと、はたから見たらただの変人だ。
猫は、わがままで懐かないというイメージを持たれることが多い。だが、筆者は「無意識に幸せを振りまいている動物」だと思う。『猫のいる家に帰りたい 』(仁尾智:著/小泉さよ:絵/辰巳出版)は、そんな想いをより強固なものにしてくれた一冊だった。
何気ない日常で感じる幸せを短歌に
本書には著者・仁尾氏が猫雑誌にて連載してきた「猫の短歌」が、エッセイと共に記されている。なにげない日常の中で感じた「猫と暮らす幸せ」がたっぷりと詰め込まれていて、そういえば自分もこんな風に思ったことがあるなと笑えてしまう。
愛猫と暮らしていると、この瞬間、自分は世界一幸せ者なんじゃないかと思う時がたびたび訪れる。例えば、いつも気ままな愛猫がなぜかぴったりとくっついてきてくれたり、ちょんちょんと手足を触ってきてくれりすると、もうそれだけでその日1日が幸せ。それが猫たちの巧みな「おねだり大作戦」であることが分かっていても……だ。
そんな風に、愛猫に翻弄させられながら感じる尊い幸せを仁尾氏は短歌に込める。中でも、心に染みたのが猫の舌にまつわる一首。
〈愛に似て生温かくやや痛い 猫におでこを舐められている〉
ザラザラの舌で舐めてくれる愛情表現は嬉しいが、痛い。その狭間で葛藤した結果、「嬉しい」を優先し、「痛くない」を諦めてしまう猫好きあるあるが代弁されているかのようなこの短歌には深く共感した。
また、短歌だけでなく、仁尾氏のエッセイにも「その気持ち、分かる」と言いたくなってしまう。特に印象的だったのが、単身赴任から戻り、久しぶりに猫がいる暮らしを体感した日の記録。愛猫たちの重みに、幸せの意味を見出した文に涙した。
〈幸せは、重さだ。一年半の一人暮らしで実感としてわかったのは、このことだった。今わずらわしく感じている重さだって、いつかきっとそれが愛おしいものであることに気づく。重さとはそういうものだ。猫が眠るひざの重さは、まぎれもなく幸せとイコールだと思う。〉
お金や名誉など、幸せを計る材料はこの世にたくさんある。けれど、一緒に暮らす者の重みを噛みしめるという幸せはお金では決して買えず、名声を得ることに勝る。だから、愛猫から雑に踏まれるたび、筆者は自分が手にしている幸せの形を尊く思う。自分よりもはるかに軽いこの体を、生涯かけて守り抜く……。そんな幸せの形があってもいい。