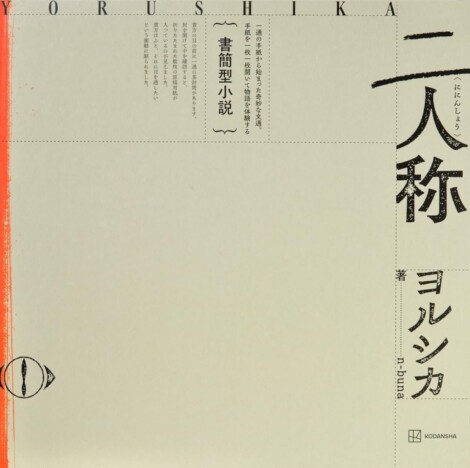「結婚して、今と違う自分になれたら、何かが変わる」は幻想か――『婚活迷子、お助けします。』第十二話

婚活迷子、お助けします。 仲人・結城華音の縁結び手帳
ケーキ、食べません? ……本当は好きなんじゃないですか
「引っ越すことになったんです」
と、ホテルのラウンジで席につくなり、志津子は、申し訳なさそうに幸次郎に告げた。
「ご連絡が遅くなって、本当にごめんなさい。はやく会ってお詫びしなきゃって、思ってたんですけど……」
納期の厳しい仕事が入り、残業も増えて、なかなか予定を決めることができなかったのだという。三週間ぶりに会う志津子は、たしかに疲れているようで、珍しく目の下にクマができている。このあとも出社しなければならないのだと、いつも着ているパステルカラーのふんわりした服ではなく、グレーのパンツスーツに身を包んでいた。衣装とは、かくも影響力のあるものか、と幸次郎はひそかに驚く。控えめで優しい印象だった志津子が、今日は妙にきりっとして頼もしく見える。けれど、
「そんなに謝らないでください。僕は気にしてませんから。会ってもらえただけで、嬉しいです」
そう言う幸次郎に、ほっとしたように表情をほころばせるのを見たとたん、心にぽっと灯りがともったようにあたたかな気持ちになった。どんな姿をしていても、志津子は志津子だ。会えて、うれしい。自分が存外に強く彼女に惹かれていることに驚き、かえって緊張感が増すのを幸次郎は感じた。
今日指定された京王プラザホテルのラウンジは、志津子と初めて会った場所だ。待ち合わせ時間も、同じ11時。なんだか、振り出しに戻ってしまったような気がするのは、心配しすぎだろうか。けれど幸次郎は今日、志津子にお断りをされるのではないかと予感していた。ふつうなら仲人を通じてあとくされなく終わるところだけれど、律儀な志津子は対面してけじめをつけようとしているんじゃないかと。
その覚悟をもって、ここにきた。残念だけど、しかたがない。ちょっといいなと思っていたくらいだし、縁がなかったと諦めるしかない。ゆうべから何度もそう言い聞かせていたし、ふしぎと落ち込むこともなかった。それなのに、志津子を前にして、浮き立つ自分を自覚したとたん、断頭台に載せられたような絶望が襲ってくる。
「ケーキ、食べません?」
振り切るように、幸次郎は笑った。
「甘いものはそんなにっていつも言うけど、本当は好きなんじゃないですか」
「どうして……そう思うんですか」
「だって、志津子さんが薦めてくれるカフェって、どれもケーキとか甘いものがおいしそうな店ばかりだから。まあ、女性はダイエットとかいろいろあるんでしょうけど、たまにはいいじゃないですか。今日くらいは遠慮せずに、注文してください。2個でも、3個でも。あ、モンブランとか旬ですよね。うまそうだなあ。俺も食べようかな」
あ、俺って言っちゃった。と思ったが、ふりかえれば前回も、気が緩んで言葉遣いは雑になっていた気がする。まあいいか、どうせ断られるんだし。と、思い込みを決定事項に変えて、幸次郎は肩の力を抜いた。酒飲みではあるが、甘党でもある幸次郎も、以前からラウンジのケーキは気になっていたのだ。志津子以外の女性とも、初回の面談はたいていホテルのラウンジなので、都内のさまざまなホテルのメニューはすっかり覚えてしまっている。
じゃあ、と志津子がモンブランを選んだので、幸次郎はチーズケーキを頼むことにした。心なしか、志津子の緊張もほどけたようで、ほっとする。うん。やっぱり志津子さんがリラックスしてくれたほうが、俺もうれしい。最後なんだから、せめて楽しいお茶の時間にしよう。そう思って朗らかな笑みを向けると、
「……え?」
志津子の目が潤んでいることに気づいて、幸次郎はひどく狼狽した。――えっ、え? 俺、なにかした? なんか変なこと言った!?
「ご、ごめんなさい。やっぱり食べたくなかったですか!?」
「違うんです。……こちらこそ、ごめんなさい。なんか、もう、……申し訳なくて」
「え、なにがですか」
「だって田中さん、こんなにいい人なのに。私、ずっとご連絡もしていなくて、それだけでも失礼なのに、久しぶりに会ったと思ったら母はあんなで。しかもまた音信不通になったのに、こうして会ってくださるし……」
「い、いやあ。俺、あんまり細かいことは気にしないんで……」
振り回されるのには慣れている、なんて言うといろんな誤解を生みそうなので、黙っておく。だが、待っていたのは決して“いい人”だからではないのは、確かだ。もしほかに見合いの順調な女性がいたら、また会いたいと思うことはなかっただろう。あるいは、婚活を始めたばかりのころなら、別だったかもしれない。待ったのは、単純に、他にいいなと思える人がいなかったから。そして、志津子に“恋”をしているわけではなかったからだ。
度重なる“お断り”に、幸次郎は心をくじかれていた。俺はこのまま一生、誰にも選ばれないのかもしれないという諦めが、卑屈さ抜きで去来していた。ようするに、近頃の幸次郎にとって婚活は惰性だった。がむしゃらにがんばる熱意も、相手に期待する気力も、失われていた。志津子から返事が来てまた会えたらラッキー、というくらいにしか思っていなかったからこそ、待てたのだ。好意が育ち始めてはいたので、残念ではあるのだけれど。やっぱりな、という投げやりな気持ちも同じくらい強いのだった。
「あ、ケーキ。運ばれてきましたよ。食べましょう、とりあえず。ね?」
うわあ、うまそうだなあ、なんてわざとらしい声をあげて、テーブルに置かれたケーキにフォークを差し込む幸次郎を、しばし見つめたあと志津子はくすりと笑った。そして、モンブランをひとかけら、いつもながら上品なしぐさで口に運ぶと、その笑みがますます、大きくなる。
「おいしい。……もっとはやく、食べておけばよかった」
「じゃあ次は」
ケーキ屋さんめぐりでもしますか、と言いかけて幸次郎は口をつぐむ。そうだ、次はないかもしれないんだったと、しゅんとした幸次郎の態度から考えを読まれたのか、志津子はフォークを置いて、ただでさえぴんと伸びた背筋を、もう一度しゃんと立て直した。
「今日は、田中さんに聞いていただきたいことがあって、来たんです」
「……はい」
幸次郎も、半分だけ残して、フォークを置く。膝にのせた手が自然と握りこぶしになる。
志津子が語りはじめたのは、そうだろうとは思っていたが、母親のことだった。母は私がなにをしても気に入らないんです、と気を遣った物言いをしてくれてはいたが、単純に幸次郎のことが気に食わなかったのだろう。会ったときの値踏みするような視線で、それはわかっていたことだ。失礼というほどではないが、尊重する意思はなさそうなまなざし。本人はとりつくろっているつもりでも、向けられたほうがすぐわかる。
気分がよかった、わけがない。ただ、母親とはそういうものだと思っていたから、あまり気にならなかった。兄がはじめて義姉を連れてきたときも、姉が結婚を決めたときも、「別にいいんだけど」と言いながら悪口にならないギリギリのラインでぶつくさ言っていたのを見ていたからだ。義姉のことも義兄のことも決してきらっているわけではない。むしろ今は、実子よりもほめそやす勢いで気に入っている。最初はいちいちたしなめていた幸次郎だったが、さみしかったし、心配だったのだろう、と次第に了解していった。
ただ、志津子の母親はどうやら、幸次郎の母親よりも心配性らしい。というのが、話を聞いていくうちにわかった。あのあとブルーバードに乗り込み退会を迫ったと聞かされたときは、さすがに仰天したのが表情に出て、志津子に苦笑されてしまう。
「私、ずっと母の言うとおりにしてきました。そのほうが面倒も少なかったから。……ケーキも、特別な日以外は食べちゃだめって言われてたんですよ。太るし、身体に悪いし、ふだんは我慢していたほうが、幸せが増すからって」
「守ってたんですか、それ」
「まじめっていうより愚直だなって自分でも思います。……姉は、こっそり食べていたし、私だって母の見えないところでうまくやればよかったのに。でもなんだか……できなくて」
「いい子、だったんですね」
「もちろん守らなかったこともたくさんあるんですよ。でも……母の言うとおりにできないことのほうが多いから、守れるところでは守ろう、って思っていたのかも。ケーキを食べるかどうかなんてたぶん、どうでもいいことなのに。母だって、そんなこと言ったなんて覚えてないかもしれないし」
淡々と語る志津子に、悲壮感はなかった。いつもよりきりっとしている、と思ったのは、服装のせいだけではなかったのかもしれないと幸次郎は思う。根津で食事をしたあと、母親と対面した志津子は、事情を知らない幸次郎でも何かあると察するくらい、うろたえていた。その面影が、今はない。
「引っ越すことを決めたのは、お母さんと離れるため?」
聞くと、志津子はうなずいた。
「家を出るのはお嫁に行くときでいい、って言われていたんですけどね。母の言うとおり、結婚にはこだわらず仕事をがんばりたい。そのためにも打ち込める環境を整えたい。実家にいると、どうしても甘えてしまうから……って、説得しました。なにか言いたそうでしたけど、仕事が本当に忙しくなってきたところだし、ちょうど帰省していた姉も後押ししてくれて。なにか、察してたのかな。うまくやんなさいよ、ってあとでこっそり言われました」
「もう家は決めたんですか」
「ええ。ちょうど、実家と職場の中間にいいところが見つかって。入居は来月ですけれど」
よかったですね、と微笑みながら、幸次郎は胸がつきんと痛むのを感じた。家を出るのはお嫁に行くとき。ではなくて、自立して生きる道を志津子は選んだ。ということはやっぱり、幸次郎と結婚するという選択肢は、志津子にはないのだ。
「……私、たぶん、逃げたかったんです。結婚して、今と違う自分になれたら、何かが変わるんじゃないかって思ってた」
それはわかる、と幸次郎は思う。
素敵な人と出会って、結婚する。それはある意味、人生の仕切り直しだ。この先の人生には、入学も卒業もない。昇進や転職をしたところで、働いて家に帰るだけの日々がそう大きく変わるわけじゃない。でも、結婚して、子どもをもつことができれば、ライフイベントが自然と増えていく。今の凡庸な自分から抜け出せるかもしれないと、幸次郎も思った。だけど。
「ちがうんだって思いました。結婚したら私はきっと、母にしていたのと同じように、夫となる人にも依存する。ちょっと窮屈かもしれないけど、そのほうが面倒も失敗も少ないし、なにより楽だからって、相手の言うとおりにする。……そんなのはもうやめたいなあ、って思っちゃったんです」
「……うん」
「だから、まずは、ひとりで生活してみたい。……今すぐは、結婚できません。ごめんなさい。田中さんのことは、とても素敵だなって思ったんですけど、でも……」
「うん。大丈夫。……わかった。すごくよく、わかったから」
幸次郎は、握るこぶしをゆるめて、冷めたコーヒーをすすった。不思議と、気分は落ち着いていた。
申し訳なさそうに、志津子はうなだれている。
本当に、不思議だった。どうしてこんなに気持ちが落ち着いているのだろう。不安も、絶望も、諦念も、緊張も。なにもかもが吹き飛ばされていた。ただ、これだけは言わなきゃ、という言葉が脳裏にちかちかとひらめいていた。
咽喉を、潤す。顔をあげてください、というと、志津子は潤んだ瞳を、幸次郎に向けた。
「小川志津子さん。僕と、結婚を前提にお付き合いをしてくれませんか?」
そう言うと、志津子の目がまんまるに見開かれ、「は?」とらしからぬ声が漏れたのが聞こえて、幸次郎は思わず笑った。
(イラスト=野々愛/編集=稲子美砂)
※本連載は、結婚相談所「結婚物語。」のブログ、および、ブログをまとめた書籍『夢を見続けておわる人、妥協を余儀なくされる人、「最高の相手」を手に入れる人。“私”がプロポーズされない5つの理由』などを参考にしております。
結婚相談所「結婚物語。」のブログ
『夢を見続けておわる人、妥協を余儀なくされる人、「最高の相手」を手に入れる人。“私”がプロポーズされない5つの理由』
※本連載は、結婚相談所「結婚物語。」のブログ、および、ブログをまとめた書籍『夢を見続けておわる人、妥協を余儀なくされる人、「最高の相手」を手に入れる人。“私”がプロポーズされない5つの理由』などを参考にしております。
『夢を見続けておわる人、妥協を余儀なくされる人、「最高の相手」を手に入れる人。“私”がプロポーズされない5つの理由』