尾崎世界観が語る、人からの影響とコロナ禍の音楽活動 「今はいらないものに気づく時間」
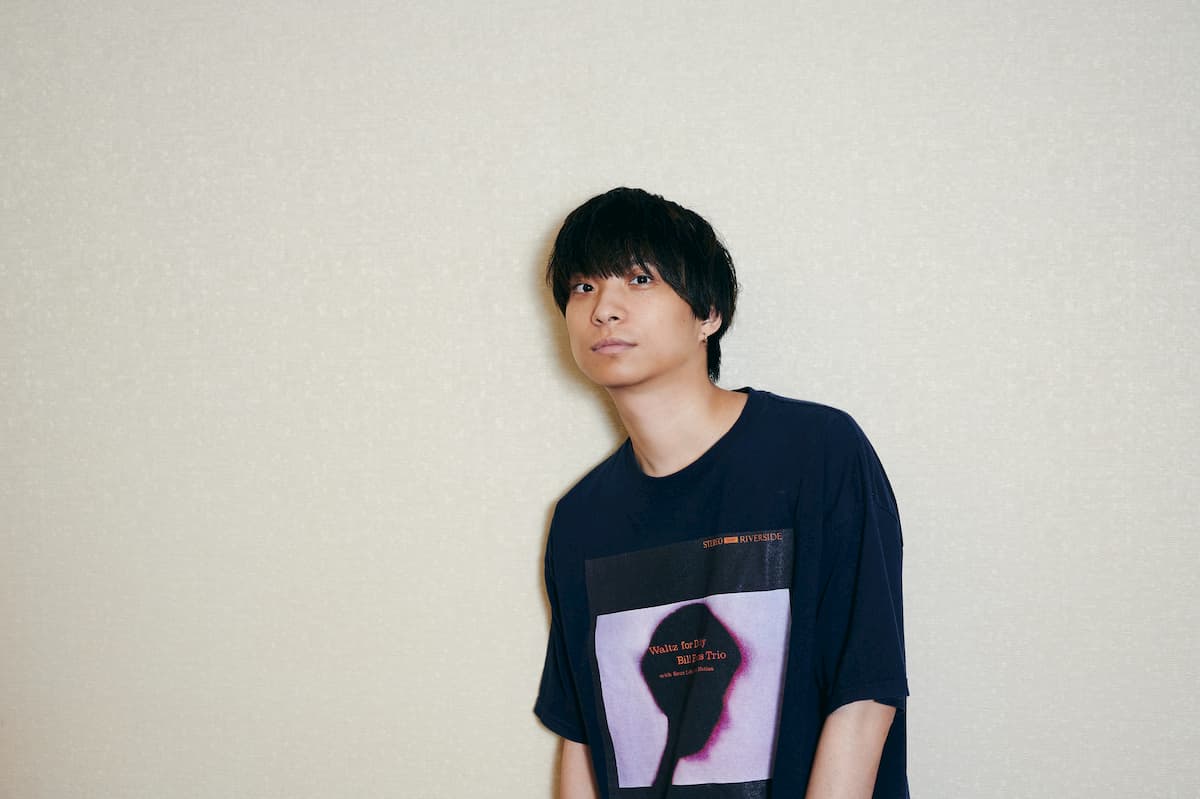
尾崎世界観の対談集『身のある話と、歯に詰まるワタシ』(朝日新聞出版)の帯の文には、「言葉」という補助線を引く――という一節がある。ロック・バンド、クリープハイプのボーカル・ボーカルで大部分の作詞作曲を手がける一方、小説やエッセイなどを執筆する尾崎らしく、本書では「言葉」の意味や声のパフォーマンスに関する話題が軸になっている。
加藤シゲアキ(アイドル)、神田伯山(講談師)、最果タヒ(詩人)、金原ひとみ(作家)、那須川天心(格闘家)、尾野真千子(俳優)、椎木知仁(ミュージシャン)と多彩な面々との対話で尾崎がなにを考えたのか、そしてコロナ禍の今思うことについて聞いた。(円堂都司昭)
最少人数で濃密に聞いたからこそ聞けたこと

尾崎:朝日新聞出版の編集者の方を紹介していただいて、本を作れたらいいですねという話になったんですけど、その頃はすでにエッセイを連載していて、小説や日記も書いていました。それで、考えたのが対談をすることです。対談はもともと好きだったけど、いつもいいところで終わる印象があって、いいことを話していたのに文字数の関係で使われていないとか、歯がゆい思いがありました。文芸誌である『小説トリッパー』なら時間をかけて対談ができるだろうし、話せることも増えるのではということで始めました。
――確かに音楽誌の対談とはテイストが違うし、ボリュームもあって読み応えがあります。
尾崎:毎回1時間半から2時間くらい喋ります。でも、それくらいやらないと出てこない話もあるし、不思議な感覚でした。最初に言葉を交わした時と最後では感覚が違うし、相手のみえかたも変わります。
――様々なジャンルの方が登場しますが、人選はどうされたんですか。
尾崎:まずは、自分が気になっている人にお願いしていきました。
――本には連載順に収録されていて1回目が加藤シゲアキさん。初回からシリアスな話をしています。震災直後のこと、尾崎さんがライブで声が出なくなった時期のこと、加藤さんの所属するNEWSのメンバーの脱退のこと……。
尾崎:対談の場所にはスタッフさんは入らず、相手の方と自分とライターさんの最少人数でやっていました。
――そういう濃密さは出ています。
尾崎:まず自分の弱みをみせたいという露出狂みたいな変な願望が出てくるんです。せっかくの機会だから早く自分を知ってもらわなければいけない。その時に早いのは、自分の弱点を話すこと。だから、最近の悩みとか後ろ向きな話から始めることが多かった。そうすると相手の方も悩みを話してくれることが多かったです。
――対談のほか、ラジオのパーソナリティ、ライブのMCなど仕事で話す機会は多いですが、もともとお喋りは得意だったんですか。
尾崎:言葉を使って感情を相手に伝えること自体は、子どもの頃から好きだったと思います。
――神田伯山さん(対談時は松之丞)の講談を見に行った際、彼は派手な芸風だけれど、他の出演者の淡々とした芸風のほうがむしろ本来の講談ではないかと思ったという話が出てきます。私も、歌舞伎や文楽の若手の芸風とベテランの芸風の違いをみて似たことを感じたことがあったので、興味深く読みました。
尾崎:松之丞さん(当時)に魅かれて観に行って、彼が尊敬する師匠や大御所の方が出てきた時、意外に淡々としていて渋い、この落差に、講談が好きな人と最近好きになり始めた人の間で距離がありそうだと感じました。長く続いてきた歌舞伎や文楽の“わかりやすくなさ”も大事なところですよね。子どもの頃からいろんなエンタメに触れた若手は、今時のリズム感や知識があって伝えることに特化しているのではないか。自分もそうだと思うし、今はものごとがすぐ伝わる世の中なので、伝統芸能がそことどうむきあうかに関心があります。
――クリープハイプが含まれるロックというジャンルも発祥は1950年代で、現在のローリング・ストーンズなどは伝統芸能のように語られます。
尾崎:伝統芸能は基本的に、もともとあるものを伝えていきますよね。音楽に関しては新しく一から作る、そこが大きな差だと思います。最近は、以前にも増して伝統芸能の自分なりに受け継ぎ、自分を通して伝える凄さを感じています。人が出るというか、差がわかりやすいですね。
――歌の世界でもカバー集が多くなりました。
尾崎:伝統芸能だったら受け継がれて箔がつく印象なのに、音楽でカバーをするとちょっと劣る感じがある。可愛くなってしまうというか。その差はなんだろうと不思議に思います。
「影響されるのは大事」

尾崎:人に影響を受けるんです。自覚はありましたけど、対談のゲラを読んでいてより強くそれを感じました。最初はもっとブレていたんです。自分ではそのブレが面白かったので、極力変えないようにしました。本でまとめて読むとあまり時間の経過を感じませんが、掲載誌は季刊だから、対談は3カ月おきくらいと間隔が開くんです。ホストとして相手に聞いているんだけど、自分で答えている感じもある。いろいろな人の話を聞いて、心情の変化がありました。ブレることをネガティブにとらえていなくて、影響されるのは大事だと考えています。そこは柔軟でいたい。それに普段はもっとうがった見方をするけど、相手は自分が興味を持って来ていただいた方だったので、いつもより肯定的に話を聞けました。
――時おり、皮肉っぽい言い回しが出てきますよね。最果タヒさんにライブのことを話していて、Aメロ、Bメロ、サビで「どうせまたここでみんな手をあげるんだろうな」とか。
尾崎:おかしな話ですけど、ミュージシャンとして別の職業の方と対していたので、なんかすみませんうちの子がという感じで音楽のことを話してしまって。こいつ調子乗っちゃって、というような(笑)。なんでお前が音楽を背負っているんだと自分でツッコミたくなりますけど。読み返すと、フェスに対して思うことがあるんだと自分でわかりました。フェスがないとやっていけないんですけど、感謝しているからこそ、家族に対するように一言いいたくなる。コンプレックスなんです。フェスに出ないとバンド活動が成立しないところに自分がいるという情けなさと、ありがたさを感じている。
――フェスだけでなく、自分をとり巻く業界のなかでの立ち位置といった話が出てきます。加藤さんだったらアイドル界、尾野真千子さんだったら映画界など。
尾崎:その他にも講談、格闘技、小説、どの回も業界の話になっていました。決していいことばかりではないと肚をくくっている方々だし、悩み相談というか愚痴のいいあいのようになる時は自分のなかをみせようとする時だと思います。うちはこんなに調子いい、勢いがあってこれからが楽しみと、互いがいいあう対談なんて面白くない。そうならなかったのは、少人数で濃密にやれたからだと思います。
――対談相手で少し異質なのは、格闘家の那須川さん。
尾崎:最低限の言葉で、返しが早かった。すごく肉体的な言葉ですよね。
――「イメージが先で言葉が追いつく」とか「擬音で会話するのがいい選手」とか。
尾崎:面白いですよね。普段は言葉で伝える方ではないのに、少ない言葉で伝えられるのは、痛みを知っているからだと思います。嬉しかったことを人に伝える時より、悲しかったり、腹が立ったことを伝えるほうが饒舌になる。格闘技は勝った時の喜びがあるとしても、そこに苦しさや痛さがつきまとう。
――那須川さんの擬音のくだりが出てくる箇所の小見出しが「身体と言葉と、その間にある音」となっていて、それをみて音楽とも関連する話だなと思えたんですけど、見出しはライターの方がつけたんですか。
尾崎:はい。対談の中から抜き出してくれました。
――上手い抜き出しかただと思いました。
尾崎:本を構成した山田宗太朗さんは、歳が一緒で、昔からよくインタビューをしてもらっていました。そこも大きかったです。自分は相手について調べすぎないようにしていました。調べすぎると、どうしても話がそこばかりになってしまう。それはもう絶対にどこかで話していることだし、触れた作品を介して話をするとなぞることになる。だから、相手の方がまだ聞かれたことがない質問を投げかけたい。そこは意識しました。ビート板は使わずに、溺れて無茶苦茶にもがいている時のほうが、面白い質問が出てくるかもしれない。カナヅチなりにそんなことを考えていました。
――私は怖いので調べますけど、調べきれないのが前提です。ただ、予習すると答えあわせするみたいな感じになるんです。
尾崎:インタビューで「こうですよね」といわれ「違います」といってもどうにかしてその方向に持っていこうとする人がけっこういます。違うといっているのに(笑)。
――対談集では尾崎さん定番のエゴサーチの話題も出てきます。
尾崎:インタビューで毎回聞かれます。どんなにやめていても定期的に見てしまう。5日間くらい我慢したら5日後に5日分を見る。エゴサーチのリバウンドでいっそう落ちこむという。
――連載は初めからこの時期に本にすると決まっていたんですか。
尾崎:なんとなく決まっていました。本になる数を目指して、当初は自分が好きな野球にかけて9人にしようかという話もありました。でも、季刊だから2年程度でちょうどよかったです。この2年でもだいぶ変わったと思います。最初の加藤さんから最後の椎木まで、インタビューをしている感覚が違っていった。本にするための校正でこんなことまで話していたのかと思う部分が、特に前半の回にありました。最果さんくらいからだいぶ今の感覚で喋っているんですけど、伯山さんには引っぱられましたね。どんどん乗せられて喋らされちゃう(笑)。
――なにやら尖ったほうに。
尾崎:気づいたら自分ばかりがいっていて、伯山さんはいっていない。上手いんです(笑)。





















