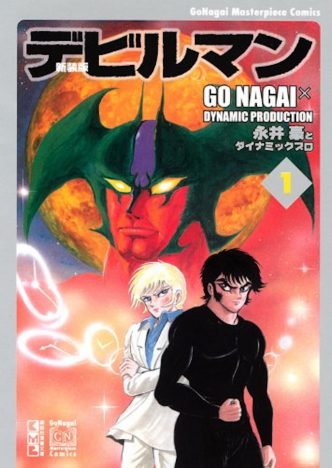『映像研』のルーツ? 細野不二彦の80年代映研漫画『あどりぶシネ倶楽部』が伝える普遍的な想い

名作漫画の遺伝子
時代を越えて読み継がれる不朽の名作漫画に改めて光を当てるとともに、現代の漫画にその精神や技法が、どのように受け継がれているのかを考察するリレー連載『名作漫画の遺伝子』。今回は手法を変え、現在連載中の作品に興味のある読者に、過去の同じような舞台・テーマの過去作を紹介する。(編集部)

湯浅政明監督によるアニメ版に続き、英勉監督、乃木坂46の齋藤飛鳥・山下美月・梅澤美波主演の実写ドラマ版も好評のうちに放送終了した大童澄瞳の『映像研には手を出すな!』だが、5月に公開予定だった実写映画版は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け延期、現時点でも正式な公開予定日などは公表されていない。だが前述のドラマ版を見るかぎり、同じ監督・主演による映画版も、漫画とアニメと実写の“良い部分”が融合した完成度の高い「映像作品」になっているのは想像に難くなく、公開が決定した暁にはぜひ劇場に足を運びたいと思っている。
ちなみに原作の『映像研には手を出すな!』についての私見は、以前こちらに書いたとおりだが(『映像研には手を出すな!』は“アニメを漫画でやろう”としているーー革新性な手法を考察)、この時は主に漫画の技法的な部分を掘り下げたため、キャラの魅力についてはほとんど触れられなかった。当たり前だが、記事で書いたようないわゆる「映画的手法」だけでは、“おもしろい漫画”を描くことはできないだろう。そう、あくまでも大童澄瞳が生み出した3人の少女たち――アニメの制作に魅せられた、浅草、金森、水崎というキャラが立っているから、この漫画はおもしろいのである(3巻目以降は音響部の百目鬼を加えた4人で物語を動かしていく)。
さらにいえば、私が同作のキャラクターについて個人的におもしろいと思っているのは、彼女たちがお互いのことを「友達」ではなく「仲間」だといっているところだ。この「仲間」という概念は、別に彼女たちの強い絆を表しているわけではなく、むしろ、「才能の切れ目が縁の切れ目」になるかもしれないという、クリエイター同士なら誰もが理解できるシビアな感覚を言葉にしたものだと考えたほうがいい(「金森氏」風にいわせてもらえば、「利害の一致」というやつだ)。だがもちろん彼女たちの間に友情がないというわけでもない。たとえば浅草にとって、「プロデュース能力」や「キャラクターの作画能力」という“自分にはない才能”は、昔から欲しくて欲しくてたまらなかったものだろうし、それが「仲間」という形で手に入った喜びもまた、この言葉には込められているといっていいだろう。そう、浅草にとって金森や水崎、そして百目鬼という異才たちは、(当たり前だが)かけがえのない存在ではあるのだ。
『映像研』より前にあった映研漫画
さて、この『名作漫画の遺伝子』というシリーズ連載は、基本的にはまず過去の名作を紹介し、次に、それがどのような形で現在の漫画に影響を与えているのかを考察するものなのだが、今回はちょっと変則的だが、逆のパターンでいかせてほしい。つまり、以下に紹介するのは、いま『映像研には手を出すな!』にハマっているような若い漫画読者にお薦めしたい、80年代半ばに細野不二彦が描いた大学の映研を舞台にした青春漫画の傑作である。
細野不二彦の『あどりぶシネ倶楽部』が、読切の形で『ビッグコミックスピリッツ』に掲載されたのは、1983年のことだった。主人公の名は神野高史。帝王大学の映研「あどりぶシネ倶楽部」の監督だ。スティーヴン・スピルバーグを崇拝するエンターテインメント志向の彼は仲間たち(といってもこの時点では、プロデューサーの片桐と俳優の原田の2人だけ)とともに新作映画を撮影しているのだが、ある時、佐藤道明というボランティア(?)のスタッフを片桐から紹介される。美少女と見まがうような美形の彼は、神野にはないアーティスティックなセンスの持ち主であり、やがて「あどりぶシネ倶楽部」の名カメラマンとしてその才能を発揮するようになる。
この、「自分にはない才能の持ち主と出会う」展開は、まさに先に述べた『映像研には手を出すな!』のそれと重なる部分もあるのだが、順調に進んでいくように思われた撮影は、予期せぬ形で頓挫しかかる。偶然、片桐の部屋で神野が道明の“正体”を知ってしまうのだ。
そう――道明は、昨年の「『ぽあ』フィルム・フェスティバル」に弱冠18歳で入選した天才映像作家だった。かつて同フェスティバルに落選したことのある神野は、嫉妬と怒りから、道明の正体を隠して「あどりぶシネ倶楽部」に引き入れた片桐に切れる。だが、片桐にも異なるふたつの才能をぶつけてコンビにしたいというプロデューサーなりの思惑があり、道明もまた、神野の才能に刺激を受け、「あどりぶシネ倶楽部」に自分の居場所を感じ始めている、ということが次第に明らかになってくる。
そして確執を乗り越えた3人(と俳優の原田)が、朝のラッシュ時の駅でゲリラ撮影に挑むところで、物語はクライマックスを迎える。このわずか26ページの読切は、まさに1本の良質な映画を観終えたかのような味わい深い読後感を残し――おそらくは読者の反応も良かったのだろう――同作はのちに『ビッグコミックスピリッツ』で不定期連載されることになった(最終的に全9話が描かれ、単行本1冊にまとめられた)。
ちなみにこの『あどりぶシネ倶楽部』という漫画のことを知っている人は、それほど多くはないかもしれない。少なくとも、細野の他の代表作――『GU-GUガンモ』や『さすがの猿飛』、『ギャラリーフェイク』ほどには知られていないだろう。というのも、いくら当時は今関あきよしや手塚眞など、自主映画出身の監督たちが注目されていた時代だったとはいえ、大学の映研を描いた物語などは、メジャーな漫画誌ではあまり求められている題材ではなかったからだ(何しろ、バンド漫画ですら、「マイナーすぎる」、「売れない」と敬遠されていた時代だ)。だが、それでもあえて自分が興味を持っているもの(=学生映画の世界)を漫画にした細野の「先見性」を買いたいと思うし(細野には、これとは別に、いまや売れ線のジャンルのひとつになった感さえある「ジャズ漫画」の先駆的作品である『BLOW UP!』という長編もある)、マイナーな世界を描きながらある程度の数の(少なくとも単行本を1冊出せるくらいの)読者がついたという面も高く評価したい。また、本作はそれまで少年漫画を主に描いていた細野が、青年漫画に移行するきっかけとなった作品でもあり、そういう意味でも重要な細野作品のひとつだといえるだろう。