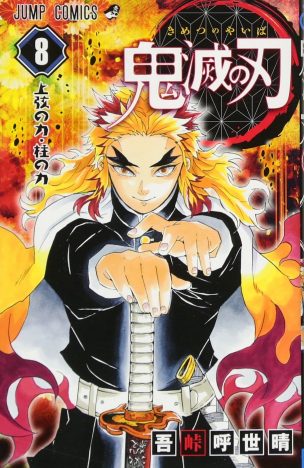『鬼滅の刃』作者が描きたかったのはダークヒーロー? 『吾峠呼世晴短編集』を考察

処女作にはその作家のすべてがある――先ごろ見事な大団円を迎えた『鬼滅の刃』の作者、吾峠呼世晴の初期短編集(『吾峠呼世晴短編集』)を読んでみたら、そんな手垢にまみれた言葉がふと頭に浮かんだ。そう、同書に収録されている『過狩り狩り』、『文殊史郎兄弟』、『肋骨さん』、『蠅庭のジグザグ』という4編のダークファンタジーには、『鬼滅の刃』というのちの怪物的大ヒット作に通じるテーマやモチーフがふんだんに織り込まれているのだ。
吾峠呼世晴が描き続けてきたテーマ

ではその吾峠呼世晴作品ならではのテーマとはいったいなんだろうか。具体的にいえば、人と人ならざる者の境界線――それを踏み越えてしまった者と、こちら(人間)側に踏みとどまっている者との戦い、ということになりはしないか。たとえば本書に収録されている4編では、順に、「異国の吸血鬼」、「警察の力が及ばない裏社会の重鎮」、「邪氣(じゃき)に憑かれた女」、「言霊(ことだま)を操る呪殺屋」といった、法で裁くことのできない“境界線を越えた者”たちが登場し、それを「狩猟者」、「文殊史郎兄弟」、「浄化師」、「解術屋」といった異能を持った人間たちが、彼らなりのやり方で“始末”する。
巻頭に収録されている『過狩り狩り』は、第70回JUMPトレジャー新人漫画賞佳作受賞作。本書掲載の自作解説で作者も書いているとおり、『鬼滅の刃』のベースとなった作品である。ただし本作では、日本の鬼と異国から来た吸血鬼、そしてそれを狩る者の三つ巴の戦いが描かれ、その点は『鬼滅の刃』と少々異なる物語の構造だといえるかもしれない。また、これは作者自身も認めていることだが、(編集者のアドバイスもなしに描いた投稿作ゆえ)客観的に見て意味不明な場面が要所要所に出てくる。たとえば、冒頭で薄汚れた少年に握り飯を差し出す男の姿が描かれるが、この場面などは、のちに発表された『鬼殺の流』[注]のネームを見ないと、いったいそこで何が行われているのか、本当の意味を誰も理解することはできないだろう。
[注]『鬼殺の流』は『鬼滅の刃』のパイロット版的な作品で、『鬼滅の刃』公式ファンブック『鬼殺隊見聞録』に3話までのネームが収録されている。
だが、実はこの、「わからない感じ」が吾峠呼世晴の漫画の魅力のひとつになっているのも、まぎれもない事実である。『鬼滅の刃』を通読すれば一目瞭然だが、同作には、作者だけはわかっているが読者は想像するしかないような設定が山ほどあり、逆にその「行間を読ませる」ような作りが、吾峠が描く漫画の世界をより豊穣なものにしているのだ、というのはいささか強引な見解だろうか。いずれにせよ、何かと説明過多になりがちな現代の少年漫画シーンにおいては、なかなか稀有(けう)な才能だとはいえるだろう。
『文殊史郎兄弟』は、裏社会の重鎮に父親を殺された少女が、奇怪な“虫”の力を操る殺し屋の兄弟を雇うという、復讐の物語だ。非力な少年や少女が、法で裁けぬ悪を倒すためにアウトローめいたプロを雇うというのは、エンターテインメント作品のひとつの“定型”ではあるが、この漫画はラストシーンにひと捻りつけ加えられている。文殊史郎兄弟が父の仇を討ったことをテレビのニュースで知った少女が、泣きながらこう叫ぶのだ。「ざまあみろ、ざまあみろ。悪い奴には必ず罰がくだる。(略)あんたなんか、死んでたって、生きてたって、どうだっていいから、お父さんを返してよ……」。この言葉はある意味では、文殊史郎兄弟が彼女のために行った正義の裁きすら否定しており、なんともいえない読後感を読み手に与えることだろう。
『肋骨さん』は、邪氣に憑かれた人間を祓う「浄化師」の物語だが、そこで描かれているのは、『文殊史郎兄弟』と同一世界のようだ(その証拠に「マミコさん」というなかなか味わい深い女性がチョイ役で両作に登場する)。主人公の名は、アバラ。アバラは、かつて善而という浄化師に命を助けられたことがあるのだが、(善而がそのとき命を失ったため)彼の代わりに浄化師になった。アバラはいう。「親も兄弟もいない僕が一人で死んでいたなら、それでお終(しま)いで良かったんじゃないのかな?」。だから、「僕は浄化師になるよ。邪氣を浄化して、邪氣憑きを倒す。できる限り、できる限り……。一人でも多く倒して、一人でも多く助ける。そうやって死ぬ」。そうでなければ、善而が死んで自分が生き続ける意味などないというのだ。だがアバラは、ある囚われの少女を救出したことにより、命の価値や、これから自分が進むべき「方向性」を知ることになる。最後に彼が見せるこぼれるような笑顔と、「ごめんね、ありがとう」というセリフも清々しい。