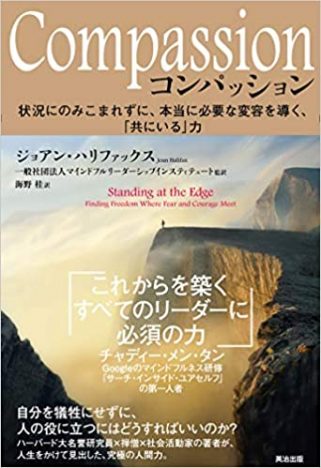UFO目撃情報が多発、その社会心理とは? 2020年のUFO像を考える

2020年4月27日、アメリカ国防総省が、海軍パイロットが2004年と2015年に撮影した「未確認の現象」の動画を公開した。これが「UFO映像」公開だとしてニュースとなり、日本では河野太郎防衛大臣が「自衛隊がUFOに遭遇した際の手順を定めたい」と記者会見で発表。にわかに話題となった。
もっとも、アメリカではトランプが2019年6月にABCに出演した際「最近、米海軍でUFOの目撃が増えているがどう思うか?」と聞かれて「まあ、信じないね」と一蹴しているのだが――興味深いことに、1994年に著名なUFO懐疑論者であるカーティス・ピーブルズが著した『人類はなぜUFOと遭遇するのか』によれば、大統領選挙の年にUFO目撃報告が増えてきた、という。奇しくも本年2020年もアメリカ大統領選の年である。
ピーブルズ本では「輪郭がはっきりしないような、あやふやな危機感」がUFO目撃事件を引き起こしている、として、キューバ危機のような具体的な危機が目の前にある場合にはUFOには人々の目が向かないと結論づけている。
COVID-19に対する危機感は、具体的な感染に対する身体的恐怖と、経済的な打撃がもたらすあやふやな将来への不安が入り交じったものだろうが、2020年のUFO像はいったいどんな社会心理の産物となるだろうか?
アメリカ現代文学の研究者・木原善彦が2006年に書いた『UFOとポストモダン』(平凡社新書)を手がかりに、このことを考えてみよう。
UFO/エイリアン像はどう変化してきたか?
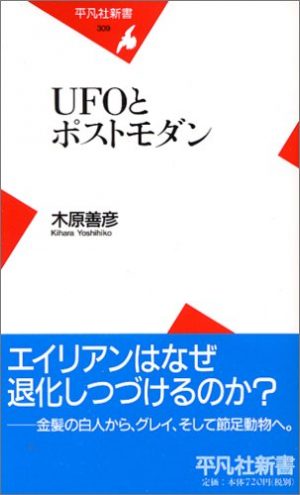
1.理想的な科学文明の担い手として描かれたUFO/宇宙人[1947-1973]
まず、最初に「空飛ぶ円盤」の目撃談が報告された1947年から1973年までの「前期UFO神話(空飛ぶ円盤神話)」の時代においては、UFOの目撃者や研究家は「私たちの世界から遠く離れた向こうの世界(外宇宙)にはすばらしい宇宙人のユートピアがある」と語っていた。地球人と宇宙人とは、物理的にも時間的にも遠く隔てられ、UFOには理想的な科学文明が託されていた。このころの宇宙人像は白人男性に近いものが多く、対話可能な存在として描かれていた。
2.陰謀の担い手として描かれたグレイ[1973-1995]
次に来る1973年から1995年までの「後期UFO神話(エイリアン神話)」の時代には、UFO/エイリアンを語る人たちには陰謀論者が目立つようになり、「私たちの世界のすぐ壁の向こう側で恐ろしいことが仕組まれている」と語っていた。家畜をさらって大量死させたり外科手術を施すキャトルミューティレーション、あるいは人体実験のために人間をさらうアブダクションが大量に報告されるようになる。
宇宙人(スペースマン)ではなく異星人(エイリアン)と呼ばれるようになり、その外見は、灰色の皮膚をした釣り目の「グレイ」に変化する。UFO/エイリアンは陰謀の担い手であり、人類を家畜のように扱う存在となる。
3.UFO/エイリアン像の衰退=“異質なもの”の非人間化と遍在化[1995-]
そして最後に来る1995年以降の「ポストUFO神話」の時代には、UFOやグレイの姿はパロディ、コメディとしてハリウッド映画などにポップカルチャーのアイコンとして登場することが増える一方、理想や陰謀の投影物ではなくなっていく。
かわって「私たちのすぐそばのそこらじゅうに“異質なもの”(エイリアン)がある」という感覚が強まっていく。いつまで経っても現れない「異星人」の時代から、いつまでたっても消えない「異質なもの」(環境ホルモンや電磁波など、人間のかたちをしていない微小な、目には見えないがそこにあるらしい恐怖)の時代へと切り替わった。「どこかで誰かが企んでいる陰謀」の影は薄れ、「今ここに迫っている危機」に対する不安が強まっている――というのが木原の見立てだ。
つまり、もはやUFOやエイリアンは影響力を持つ都市伝説(現代の神話)としては機能しないだろう、と木原は2006年時点で語っていたのだ。
では、2020年のUFOはどう捉えたらよいだろうか?