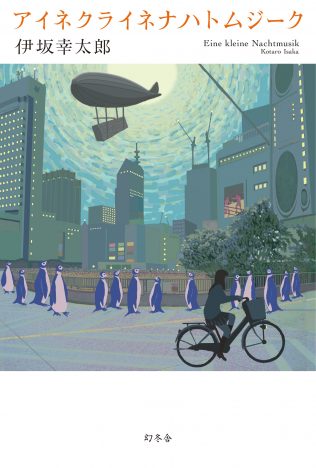束縛され、がんじがらめで働く男たちの悲哀 Twitter文学賞国内編1位『黄金列車』は今こそ読みたい一冊だ

買い置きできる限りのものを買い置き、窓もカーテンも閉め切り、外の世界を締め出して、全てがすっかり変るまで家に閉じこもる。新しい世界が来るまで、二人とも部屋から出ない。できるような気がした。(中略)こんな世界はもう見たくもないし、聞きたくもないのだ。(『黄金列車』,角川書店,佐藤亜紀,P301)
まるで、今、我々が置かれつつある現在にぴったりな言葉だなと思いつつ、主人公・バログの言葉を読んだ。家にこもっていなければならない状況を無理やり「好機」と捉え、どっぷりと本の世界に耽ろうではないかと決意した読書家のあなたに、第10回Twitter文学賞国内編第1位を受賞した『黄金列車』(佐藤亜紀著)をオススメしたい。
「日本人の作家が書いたとはとても思えない外国文学の傑作」とは、佐藤亜紀のデビュー作であるウィーンの一つの身体を共有する兄弟の幻想的な物語『バルタザールの遍歴』(新潮社)から既に言い尽くされてきたことではある。しかし、やはり凄い。臨場感が尋常じゃない。佐藤の、余計な説明や感情の吐露を一切省いた、潔くクールで確かな筆致が、読者を瞬く間に第二次世界大戦末期のヨーロッパの鉄道車両や居酒屋、あるいは薔薇の花が食卓の上で咲き乱れる、主人公の記憶の片隅にあるアパートの一室へと連れて行ってくれる。
決して今の鬱々とした状況を吹き飛ばしてくれる明るい本ではない。心躍らせる、銃弾飛び交う冒険譚でもピカレスクロマンでもない。
主人公は、やれと言われたことを淡々とこなしている、至極地味な、役人のおじさんたち。第二次世界大戦末期のハンガリー王国大蔵省の官吏であり、ユダヤ資産管理委員会の現場担当として国有財産の保護・管理を命じられ、「黄金列車」に乗り込んだ男たちだ。黄金列車が運ぶ「国有財産」とは、当時、枢軸国の一員だったハンガリー王国にとっての迫害対象であるユダヤ人から政府が没収した資産のことである。
彼らは、悪党でもないが、善人でもない。しれっと裏切り者を見殺しにする冷酷さも持ち合わせているし、報酬の大きさに心動かされて便宜を図ろうとすることもある。黄金列車という、子供たちから見れば夢とロマン溢れる「海賊船」も、彼らからすれば、とっくの昔に破綻していて、道義的にも間違っていることがわかっているにも関わらず、遂行しなればならない、気が重い任務でしかない。
日々変わりゆく情勢によってコロコロ変わる指令塔や行き先、一筋縄ではいかない敵の出現、上司の裏切りといったものに振り回されながらも、文官の論理と交渉術で颯爽と道を切り開いていく主人公たちの姿はかっこいい。だがその一方で、道行く先々で資産の一部を掠め取られたり、彼ら自身がやむを得ず賄賂としてその一部を渡したりを繰り返し、それを律儀に領収書に記載し続けるという地味な作業を必死で続け、結局何を守ろうとしているのかわからなくなっていく姿はなんとも滑稽だ。
たとえばナチスの問題を考えたときに、目が行くのはヒトラーとか、ゲーリングとか、アイヒマンだと思うんですが、彼らが何を叫んでも、役所が動かなければ何も動かないんですよ。だからそういう状況になったときに、実際に現場を動かしているのはただの公務員なんですね。で、このただの公務員はナチかというと、実質的には違っていて、仕事をしているだけだったりする。(文芸WEBサイト「カドブン」より引用)
と、佐藤亜紀自身が言及しているように、本書は、そういう実体のない、思考停止の悪を描いた物語でもある。