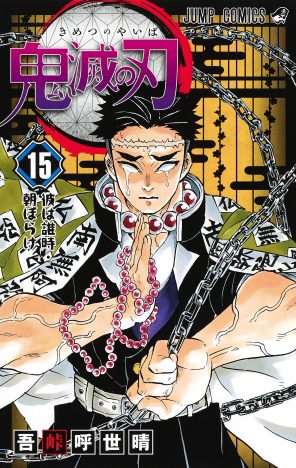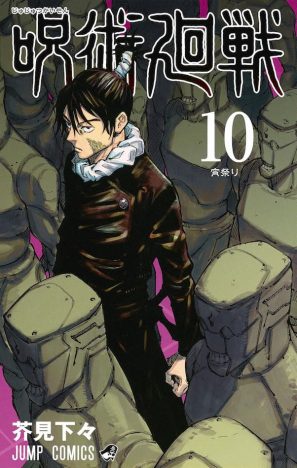『ダブル』野田彩子が語る、演技を漫画で表現する難しさと面白さ 「二次創作をずっとやってきたので、お話の中の人間に惹かれる」

メタフィクションと二次創作の経験から見た役者マンガ

野田:「演じている人」がそもそも好きなんですね。私は二次創作をずっとやってきた人間で、お話の中の人間に惹かれるので……キャラクターたちは自分とは次元の違うところで生きていて、そちら側を覗くことはできてもタッチできない。そういう距離感が好きなので、『わたしの宇宙』にはその感覚が出ているのかな、と。
役者の人たちも私たちは基本的には舞台や映像に出ている様子しか見られなくて、それ以外のところではまったく違う生活をしているかもしれない。
――3次元にいるはいるけれども、受け手は一方的に覗くしかないという意味では似ていますね。
野田:いくらSNSでプライベートについて発信したとしても全部見えるわけではなくて、想像がつかない部分がある。私はわからないものに対する興味があって、自分から断絶していればいるほどいいんです。努力やファンサービスが「見える」方より、「ここでアピールした方がよさそうなのに、なんでやらないんだろう?」という役者に惹かれます。意図を隠しているのでもなく、単純に読めない人。そういう人が「ふだん何を考えて生きているんだろう?」と考えるのが好きで。私がボーイズラブを描いているのも、男の人が何を考えているのかわからないから、というのがあると思います。
――二次創作の経験は『ダブル』で活きていますか? 演劇は戯曲・脚本をどう解釈して表現するかという点で二次創作的な発想と似ている部分があるのかな、とも思うのですが。
野田:私がマンガをちゃんと描くようになったのは二次創作のおかげなので、少なからず活きているのでは。それ以前から描いてはいましたが、二次創作を始めてから技術的にもしっかりしようと思いましたし、二次を描くには原作だけでなくて原作がモチーフにしている諸々も調べないといけない。その経験が今も役に立っています。ただ、今も調べものするのはものすごい嫌いで「なんとかならんか」といつも思っています(笑)。
――野田さんの劇中劇の解釈や切り取り方は独特ですよね?
野田:うーん、『ダブル』の中ではシェイクスピアやチェーホフを取り上げているんですが、解釈が全然違ったらどうしようと思ってはいます。こわいですね。
稲泉:演劇は歴史が長いこともあり、古典をかなり大胆に再構成して演じる流れもあって、挑戦的な作品にわりと好意的ですから、『ダブル』での解釈もポジティブに受け取ってもらえるのではないかと、どちらかといえば楽観視しています。15話(「ふらっとヒーローズ」2020年4月掲載分)がすごいんですよ。役と役者の関係を何層にも重ねたつくりになっているので。
野田:役者ものだと、まず「キャラクター」がいて「キャラが演じる役」がある。キャラクター自体も「劇団の人間としてのポジション」と「映画で知り合った人たちの中でのポジション」は違う。そういう違うレイヤーを重ねて「人間関係ってこんな感じだよな」ということをやっています。
オーディオコメンタリーや創作ドキュメンタリーが好き
――野田/新井作品だとふたりで一緒に映画を観に行ったり、家でアニメや映画を観るシーン多いですが、映画もお好きなんですか?
野田:そんなに数は観ていないですね。好きになった同じものをくりかえし観る人間です。『シン・ゴジラ』のときに初めてまともに邦画を観たくらいで。そこから『シン・ゴジラ』みたいな「スーツ姿の偉い人がいっぱい出てずっと揉めている映画」を探しているときに『金融腐食列島 呪縛』に出会って、カット割りとか音楽とかが全部かっこいいなと思って原田眞人監督作品をたくさん観るようになりました。でもそれくらいですね。
――「スーツの人たちがずっと揉めている映画」(笑)。
野田:原田監督の映画は「すべてのカットをかっこよくする」という気概に満ちているんですよね。たとえば銀行の頭取の部屋のセットなんかにしても「本当の頭取の部屋がどういうものか」より、「リアルにしても画が地味になるだけ」という判断で、哲学を持ってドハデにしている。私もやりたいと思ったことはきっちり全部できるようにしたい、あまりかっこわるいものにしたくないな、と思っています。
稲泉:オーディオコメンタリーもお好きですよね?
野田:そうですね。マンガ家ってひとりで作業していることが多くて、ストーリーに飢えているときは映画本編を観ればいいんですけど「人が話している声を聞きたい」と思ってオーディオコメンタリーを観ることが多いです。緊迫したシーンでもそのときの思い出をなごやかにしていたり、なごやかに話しているけど「この人、現場では怖いんだろうな」という方がいたりするのを聞いて「映画の現場ってこんな感じなのか」と想像するのが好きなんです。
稲泉:『もののけ姫』とか。
野田:『もののけ姫』はオーディオコメンタリーではなく制作ドキュメンタリーですね(『「もののけ姫」はこうして生まれた』)。あの作品では企画段階に始まって「広告どうしよう」「配給どうする」といったことまで裏側を追いかけていて。それを観ているとスタジオジブリ内の人間関係が想像できるんですよね。宮崎駿監督がジブリの女性社員にやり込められているシーンがあったり、明示的には語られていなくてもそれぞれの関係性が見えてくるところが面白いです。
――今うかがっていて、そういう「制作の裏側にある人間関係」が好き、という視点が『ダブル』の演劇や映画の制作シーンに活きているということが非常によくわかりました。
野田:私自身は人間関係が希薄で特定の方としか付き合わないんですが、他人がどう付き合っているのかがわかると孤独が柔らぐといいますか。想像じゃないとこわいですね。