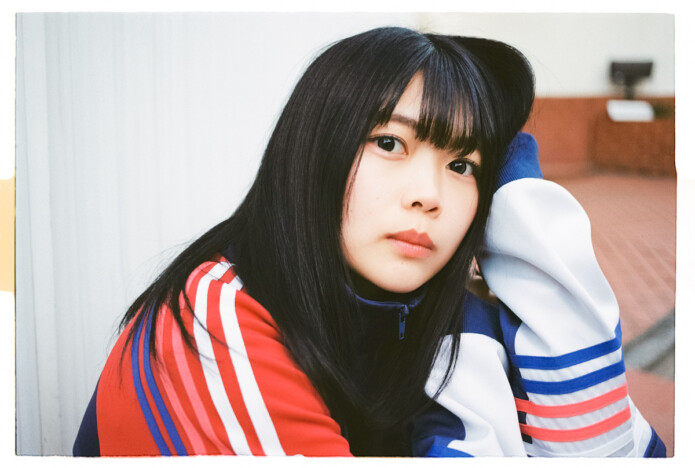Bialystocks『Tide Pool』クロスレビュー
Bialystocksの音楽とはどのようなものなのか? EP『Tide Pool』をライター3氏がレビュー

原雅明「Bialystocksが作り上げる二人のパーソナルな音楽としてのポップス」
1曲目の「Over Now」は、 イントロのエレクトリックピアノ(ウーリッツァー)の心地よい響きからグルーヴとハーモニーが生まれ、ボーカルはそれを軽妙に乗りこなしていく。各楽器の音は、空間的な拡がりを意識させるように散りばめられている。ポップスらしく曲が進行する中で、ネオソウルを支えたロイ・ハーグローヴを想起させるトランペットが一瞬、聴こえたかと思うと、不意に左チャンネルからギターがインサートしてくる。その短いフレージングは他より遥かに大きい音量で、軽く聴き流している状況でも耳を捉えるはずだ。ギターがトリガーとなった間奏から戻ると、最後はギアを少し上げてすぐさま微かな余韻を残して終わる。
2曲目の「All Too Soon」は、メロウなグルーヴとそれに乗るメロディが維持されるのだが、レイドバックした空気にシンセの重く低いベースラインが異質なレイヤーを加えていく。それは、ブレイクを挟んで展開される現代ジャズのシャープでタイトなドラミングへの誘導だったと気がつく。その素早い転換はスムーズで、忙しない印象は与えない。やがて、〈夢の続きを聞かせて〉というフレーズの反復とコーラスの重なりが一つのサウンドスケープを作り、即興性を感じさせる演奏に変化する中で、終盤はピアノのソロが入ってくる。
冒頭の2曲はどちらも3分台の曲だが、その倍の時間があると錯覚するような構成要素と展開から成り立っている。この2曲はEPの中でも傑出していて、Bialystocksの音楽が内包する複雑さが表れている。それは、録音芸術としてのポップスと、ライブ音楽としてのジャズのせめぎ合いだと言える。その間にある均衡を聴かせようとする音楽は、ありきたりな融合に終わることもある。ポップスに、あるいはジャズに徹していた方がリスクは少ないが、そのリスクとトレードオフで得られるものが魅力を放ってきたのも事実だ。
例えば、ジャズピアニストのブラッド・メルドーの『Largo』というアルバムがそうだった。エイミー・マンやフィオナ・アップルを手掛けたジョン・ブライオンをプロデューサーに迎えて録音された『Largo』は、それまでアコースティックのピアノトリオでの即興演奏とクラシック音楽から来るソロピアノにストイックに向き合ってきたメルドーが、ポップスに接近したアルバムだった。だが、それはジャズとポップスの融合ではなく、せめぎ合いの連続だった。ジャズの流儀に則ったのだと言わんばかりに、スタジオでのライブ録りでオーバーダブを加えていないことがわざわざ明記された。にも関わらず、このアルバムは手の込んだスタジオプロダクトに聴こえるように仕上がっていた。
『Tide Pool』が一体どのような制作プロセスを経て出来上がったのかは知らないのだが、このEPも手の込んだスタジオプロダクトに聴こえる。同時に、バンドサウンドというより、一人で制作された多重録音のような感触がある。パーソナルな感情にフォーカスする歌もそのことを印象づける。「フーテン」で聴かれるクラリネットの響きにオーバーダブを初めて使ったシドニー・ベシェをふと思い出したのだが、一人で多重録音にのめり込むミュージシャンとベッドルームで孤独な作業を繰り返すトラックメイカーは、時に似通った表現衝動に突き動かされてきた。シンガーとプロデューサーの関係でも、デュオやバンドの関係でもない、二人のパーソナルな音楽としてのポップスをBialystocksは作ろうとしているのだろう。特に『Tide Pool』の2曲からはそう感じた。