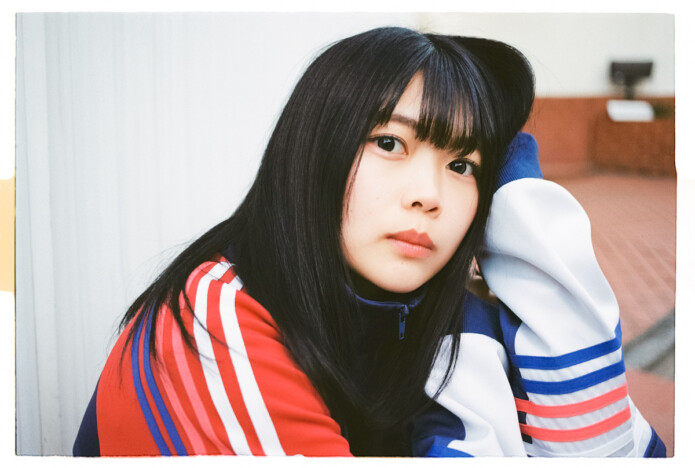Bialystocks『Tide Pool』クロスレビュー
Bialystocksの音楽とはどのようなものなのか? EP『Tide Pool』をライター3氏がレビュー

ボーカル&ギターの甫木元空とキーボートの菊池剛から成る2ピースバンド・Bialystocks。2019年、甫木元が監督・脚本・音楽を務めた映画『はるねこ』(2016年)の生演奏上映をきっかけに結成されたという特殊な経歴を持つバンドだ。甫木元はフォークミュージック、菊池はジャズといったそれぞれが持つ異なるルーツと、二人体制という個と集団の間のような形態がBialystocksならではのユニークな音像を作り出している。
Spotifyが躍進を期待するアーティスト「RADAR:Early Noise 2022」に選出されるなど、年始から話題を集める彼らが1月にリリースした最新EP『Tide Pool』について、リアルサウンドでは音楽ライター・松永良平、原雅明、岡村詩野の3氏によるクロスレビューを展開。異なる角度から聴く同作、そしてBialystocksの音楽とはどのようなものなのか。まだ彼らの音楽にふれたことのない方にとっては優れたガイドに、すでにふれている方には新たな発見をもたらすようなテキストになっている。(編集部)
松永良平「彼ら自身が“水溜り”から生まれる新しさへの可能性を感じている」
Bialystocksは、映画の作り手であるボーカルの甫木元空とキーボード奏者、菊池剛のバンドだという。甫木元の作詞は、映画の脚本のようではないが、物語的というか、物語を動かしていく思いや言葉の断片をメロディに置いていくようなところがある。ストーリーを語っているというより、この言葉の連なりから聴き手が思い浮かべるストーリーがある、という感覚に近いか。だから、素描的で、荒っぽさもあって、ゴツゴツしている。
甫木元の言葉の配置は、むしろ完成されそうな楽曲を感性によって不安定化させるものだ。言葉によって不安定化し、コンパクトなパターンから逸脱した楽曲は、遠近法的な奥行きや広がりを作る。そういう意味では、これは正しく映像的、映画的な音楽の作り方なのだろう。甫木元と菊池のふたりがどのくらい意図的にこのBialystocksというバンドのあり方を志向しているのかはまだまだ未知数だが、この最新EP『Tide Pool』の冒頭に収められた「Over Now」や「All Too Soon」は、彼らの世界観をかなり具現化した楽曲だといえる。
いっぽう、後半の「フーテン」「光のあと」「あいもかわらず」の3曲では、甫木元のシンガーソングライターとしての身体性が前面に出る。R&B/ジャズ的なアレンジではなく、甫木元の弾き語りに菊池が豊かな肉付けをしていったというスタイルだと思える。現代型フォークシンガー、あるいは、甫木元が脳内で描く映画のロケーションにポツンとたたずむ登場人物のようなムードと、ロマンチックでありながら自分の思いに飲み込まれてしまわない絶妙さがあって、そこにも彼らの可能性を見る。
もともと、彼らの存在を知ったのは、そんなに前のことじゃない。友人のVIDEOTAPEMUSICが高知で行う滞在制作とライブの対バンとして告知されたことがきっかけだった(2021年11月27日『現代地方譚9 LIVE すきま たゆたう』須崎市立市民文化会館第3駐車場)。彼らがそのライブに出演したのは、甫木元が現在、映像制作のために祖父の実家のある高知に定住しているという縁があったからだそうだ(映像という点ではVIDEOTAPEMUSICとも関連が少なからずあった)。
「あいもかわらず」に収められているのは高知で日々感じていた自然音だろうか。映像だけでなく音楽面でも、まだまだ彼らの表現は変わっていく気がする。その経過点を記録したEPなのだとしたら、あとあとになってまた振り返られるのかも。潮が引いた海岸に残された水溜りを指す『Tide Pool』というタイトルにも、彼ら自身がその水溜りから生まれる新しさへの可能性を感じていることが読み取れた。