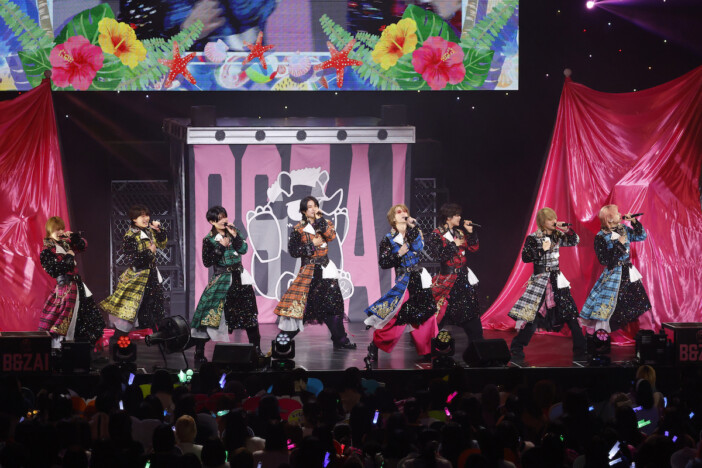シティポップ(再)入門:南佳孝『SOUTH OF THE BORDER』 シティポップを象徴する世界観、最高にスタイリッシュな一作
日本国内で生まれた“シティポップ”と呼ばれる音楽が世界的に注目を集めるようになって久しい。それぞれの作品が評価されたり、認知されるまでの過程は千差万別だ。特に楽曲単位で言えば、カバーバージョンが大量に生まれミーム化するといったインターネットカルチャー特有の広がり方で再評価されるケースが次々登場している。オリジナル作品にたどり着かずとも曲を楽しむことが可能となったことで、それらがどのようなバックボーンを持ち、どのようにして世に生み出されたのかといった情報があまり知られていない場合も少なくない。
そこで、リアルサウンドではライター栗本斉氏による連載『シティポップ(再)入門』をスタートした。当時の状況を紐解きつつ、それぞれの作品がなぜ名曲・名盤となったのかを今一度掘り下げていく企画だ。毎回1曲及びその曲が収められているアルバムを取り上げ、歴史的な事実のみならず聴きどころについても丁寧にレビュー。当時を知る人、すでに興味を持ってさまざまな情報にふれている人はもちろん、当時を知らない人にとっても新たな音楽体験のガイドになるよう心がける。
連載第6回となる今回は、自身3作目にして最高傑作との呼び声も高い、大人のためのシティポップを表現した南佳孝『SOUTH OF THE BORDER』について紹介したい。(編集部)
南佳孝『SOUTH OF THE BORDER』
はっぴいえんどのドラマーだった松本隆は、バンド解散後に作詞家としての一歩を踏み出した。まだそれほど一般的に知られていない頃、ひとりのアーティストをプロデュースする話が持ち上がる。そして1973年にプロデューサーとしての記念すべき第一作として発表されたのが、南佳孝のデビューアルバム『摩天楼のヒロイン』だ。二人は知り合ったその日に意気投合し、一本の映画のような都会的な音楽というコンセプトでこのアルバムを作り上げた。シティポップの元祖ともいわれることも多い本作は、ジャズ、ファンク、レゲエなどの要素を取り入れ、日本人離れした感性で作られている。たしかに、当時のフォークやロックが全盛だった音楽シーンにはあまり見られない世界感である。
こうして南佳孝という稀有なシンガーソングライターは颯爽と登場した。1950年に東京で生まれた南佳孝は、兄や姉の影響で幼少時からナット・キング・コールやフランク・シナトラといったジャズやポップスを聴いて育っている。そして、中学生でバンドを組んでドラムを担当し、徐々にオリジナル楽曲を作っていった。大学生になるとジャズから多大な影響を受け、3拍子で書いた「ここでひとやすみ」という楽曲が、フジテレビの音楽番組『リブ・ヤング!』が主催するシンガーソングライターコンテストで3位に入賞し、デビューのきっかけを掴んだ。それが『摩天楼のヒロイン』に繋がるのである。ただし、南佳孝本人としては、『摩天楼のヒロイン』はあくまでも松本隆の世界であり、自身の作品という認識はなかったそうだ。このデビュー作は評価が高かったもののセールス的には惨敗して自信を無くしたため、アルファミュージックと作家契約をして裏方になることを決意。しかし、CBSソニーから声がかかり、1976年に2作目の『忘れられた夏』を発表したところから、本格的にシンガーソングライターとしての道を歩み始めるのだ。
彼の作品はいずれも大人っぽい洗練された作品が多いが、なかでも最高にスタイリッシュな作品が、3作目となった1978年の『SOUTH OF THE BORDER』ではないだろうか。『摩天楼のヒロイン』は矢野誠が音楽的なイニシアチブを取っており、『忘れられた夏』では、林立夫、小原礼、鈴木茂、佐藤博といった売れっ子のスタジオミュージシャンの他、宮沢昭一、稲葉国光、直居隆雄といったジャズ系のミュージシャンを起用していた。『SOUTH OF THE BORDER』ではメンバーは多少かぶるものの、新たに坂本龍一に全曲のアレンジを依頼する。坂本龍一は本作に取り掛かる時点で、ちょうど自身のソロアルバム『千のナイフ』をレコーディングしていたが、まだ一般的に世に知られた存在ではなかった。ただ、すでに山下達郎の『SPACY』(1977年)や大貫妙子の『SUNSHOWER』(1977年)といった作品で重要な役割を果たしており、数々のセッションに参加するキーボード奏者でもあった。新進気鋭のミュージシャンとして評価が高まっており、そのセンスが認められての起用だったのだろう。
『SOUTH OF THE BORDER』のサウンドのキーワードは、ラテンやブラジルといったところだろうか。レコーディングに入るにあたって、南佳孝は坂本龍一にジャズやボサノヴァの大量のレコードを参考資料として渡してアレンジを依頼したが、予想以上の出来栄えになって返ってきて非常に驚いたというようなことを後に語っている。参加しているミュージシャンの力量もあるとはいえ、これほどまでに日本のポップスに無理なくラテンミュージックのエッセンスを取り入れた作品はないかもしれない。
なかでもサンバやボサノヴァといったブラジリアンサウンドと、南佳孝の楽曲の相性は抜群だ。大貫妙子とのデュエットでメロウに展開する松任谷由実が作詞したソフトサンバ「日付変更線」、梅垣達志&ミト夫妻のコーラスと坂本龍一の流麗なエレクトリックピアノがグルーヴィなサンバのビートに絡み合う「夜間飛行」、夏の終わりの夕暮れ特有の郷愁を感じさせるスローボッサ「終末のサンバ」という3曲は、本作の中核といってもいいだろう。ブラジル音楽やラテン音楽にはリズムセクションが非常に重要になってくる。そのため、本作にはドラマーとパーカッショニストには強者が揃っており、林立夫、高橋ユキヒロ(現高橋幸宏)、浜口茂外也、斉藤ノブ(現斉藤ノヴ)、ペッカー、ラリー寿永、吉川祐二と7人もの名手が名を連ねている。楽曲によって組み合わせは違うが、彼らの生み出すリズムこそが、本作における大きなグルーヴ感の秘密といえる。
ブラジル音楽以外のラテンテイストも、ここでは効果的だ。細野晴臣が叩くスティールパンの音色が涼しい「夏の女優」、ブレッド&バターのコーラスとレゲエ風のビートの融合がユニークな「朝焼けにダンス」、サルサのエッセンスを取り入れた「ワンナイト・ヒーロー」、1950年代頃のオールドラテンを思い起こさせるシルキーな「ブルー・メロディ」と、どれも本格的にラテンミュージックに傾倒したサウンドが楽曲を演出する。