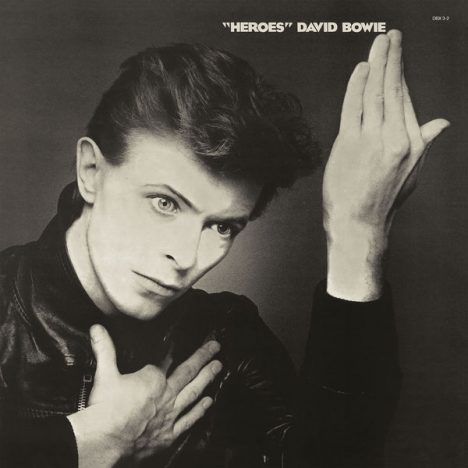デヴィッド・ボウイはいかにして“ジギー・スターダスト”になったのか 『世界を売った男』50周年記念作品から活動の軌跡を辿る

デヴィッド・ボウイが英国で1971年に発売したアルバム『世界を売った男』の50周年を記念して、21曲もの貴重な未発表音源を含む2枚組のCD作品『ウィドゥス・オブ・ア・サークル~円軌道の幅』が海外では5月28日に、日本で6月9日に発売される。
「ウィドゥス・オブ・ア・サークル」とは『世界を売った男』の1曲目のタイトル。「過ぎ去る朝、街角に座り、僕は始終、神を咎めるだろう」という意味深で自省的な詞の曲。1960年代を苦しい雌伏の時で過ごし、実質的な1stアルバムとして考えられている『スペイス・オディティ』で華々しい再デビューを飾ったかに見えるボウイが、まだ悩みを抱えていたことを象徴する詞である。なぜか。『スペイス・オディティ』は同名シングルこそ話題になったものの、アルバム全体としてはそこそこの結果だった。そもそも同名シングル曲は、再デビュー前からの盟友でボウイの生涯の立役者=トニー・ヴィスコンティがプロデュースを降り、エルトン・ジョンの名プロデューサー、ガス・ダッジョンに譲った結果ヒットしたもの。リック・ウェイクマンもフィーチャーした飛び抜けた宇宙的サウンドは無敵である。他の曲はトニー・ヴィスコンティのプロデュースによるものだが、60年代末を引きずるサイケ・フォーク的な曲ばかり。トニーのプロデュースワークも、方向性がガツンと来ないファジーな印象となった。
このままでは、再び60年代のように沈没してしまうとボウイは焦っていたに違いない。そんな状況を打開すべく制作されたのが『世界を売った男』。そのサウンドは、すでにトニーが仕掛けていたT. Rexなどグラムロックの急激な勃興を意識し、ボウイの変身を物語る。そして後にロック界を代表するスターとなるボウイの基礎を作った重要なアルバムとなった。しかしレビューは様々に解釈が分かれていた。そんな盤の秘密を解くべく企画されたのが今回の2枚組であると言えよう。
初期ボウイの立役者=ミック・ロンソン加入直後のライブ音源
なんといっても注目はCD1。ここには1970年2月5日に録音された『THE SUNDAY SHOW INTRODUCED BY JOHN PEEL / ザ・サンデイ・ショウ・イントロデュースト・バイ・ジョン・ピール』の音源が14曲収録されている。ジョン・ピールによるラジオ番組の公開録音はロウワー・リージェント・ストリートにあるBBCのパリス・スタジオで行われた。これはブレイクの鍵となった「ボウイにとってのキース・リチャーズ」こと、ミック・ロンソン加入後の初ライブとなる超貴重なライブ音源である。ベールに包まれていた音源を丸ごと聴けることで、70年代の大スターとなる「ジギー・スターダスト」とは何だったのか、という疑問が解ける内容となっている。

1曲目はボウイの弾き語りによる「Amsterdam / アムステルダム」。ボウイが尊敬するフランスのシャンソン界の神、ジャック・ブレルの曲。ボウイは英国のスコット・ウォーカーに多大な影響を受けており、スコットの伝記映画『スコット・ウォーカー 30世紀の男』の製作総指揮も務めている。そのスコットがブレルの数多くの曲をカバーしているーーいわばボウイの大先生ともいえるのがブレルなわけで、これは原点吐露といえる幕開けだ。
『スペイス・オディティ』収録のM2「God Knows I’m Good / 神は知っている」、初期の未発表曲であるM3 「Buzz The Fuzz / バズ・ザ・ファズ」、M4「Karma Man / カーマ・マン 」と弾き語りが続く。これらは、アコースティックギター1本の弾き語りで、手慣れた演奏には確かな手応えがあり見事。この時点までのボウイはサイケ・フォーク歌手として完成していた。そんなボウイに触れられることが嬉しい。
ボウイ初期を代表する佳曲、M5「London Bye,Ta-Ta / ロンドン・バイ・タ・タ」は3種類のスタジオバージョンが存在するほど、自身の思い入れが強い。60年代に拡がったヒップなロンドンが思い浮かび、ノスタルジアを感じさせる曲だ。ここでいよいよベースにトニー・ヴィスコンティ、ドラムにJunior's Eyesのジョン・ケンブリッジが加わる。この時点でのバンド名は「ハリー・ザ・ブッチャー」だった。前々日の2月3日にJunior's Eyesが前座でボウイのライブが行われ、そこでJunior's Eyesは解散、ジョンは正式にボウイ・バンドのドラマーになる。さらにそのライブでボウイ・バンドで弾いたギタリスト、ティム・レンウィックもレコーディング日には招かれない(※1)。たった2日の間に、それだけの出来事があった。ボウイは激動の日々を過ごしていたのだ。
再び、叙情的なフォーク曲 M6「An Occasional Dream / おりおりの夢」は、ジョニ・ミッチェルに向こうを張る成功も叶ったかと思わせるような素晴らしいメロディ。ここでミック・ロンソンの登場となる。この録音には『スペイス・オディティ』録音中にドラムのジョン・ケンブリッジが紹介したギタリスト、The Ratsに在籍していたミックが招かれた。彼は数日前からロンドンに戻っており、この人気番組のためにボウイが呼んだ。まさに針の穴に糸を通すような運命の綱渡りか。もしこの時に上手くジョイントできていなかったら、ボウイのキャリアはどう転がったか分からない。
ジョン・ピールの「このバンド(ハリー・ザ・ブッチャー)は君の正式なバンドなのかい?」という問いに対し、ボウイは「え~っと、今晩だけになると思います」と答えた。そしてそうなった(※2)。
まず演奏されるのは、タイトル曲のM7「The Width Of A Circle / 円軌道の幅」。全く様相が一変するとはこのことだ。不穏なイントロにミックのギターが絡むと、何かとてつもない魔法が生まれたことに気づく。それまでのM4〜6に全くなかった深いエロティシズムが生まれ、トニー・ヴィスコンティのベースもうねるうねる。ギター1本でここまでバンドは変わるものかと思うと、ボウイの驚き微笑む顔が浮かぶ。ボーカルもそれまでの曲とは全く色彩を変え、シャウトする声色は、その後、死まで変わることのない「あの声」である。まさに「ジギー・スターダスト」降誕の瞬間。ほとんどリハーサルの時間がなかっただろうこのバンドだが、そんなことはどうでもいいのかもしれない。ロックとはまずは人間同士の存在の火花なのだ。
『スペイス・オディティ』収録の3曲、アメリカン・ロック調のギターリフが冴えるM8「Janine / ジャニーヌ」と幻想的なフォーク曲のM9「Wild Eyed Boy From Freecloud / フリークラウドから来たワイルドな瞳の少年」、ミックのリフで一大ロックンロールに変貌したM10「Unwashed And Somewhat Slightly Dazed / 眩惑された魂」。ミックの加入によって大きく音楽性が変化しており、ブギー調の未発表曲 M11「Fill Your Heart / フィル・ユア・ハート」と続くが、このライブ前年の重要なヒット曲「スペイス・オディティ」が行われないのはなぜか。この時点でボウイを知らしめた唯一の曲といっていいのに。再現が難しいから? その代わりに演奏されるのが続くシングル曲となったM12「The Prettiest Star / プリティエスト・スター」。哀愁のあるギターリフは聴いたら忘れないもの。ここからミックが抜けたメンバーで再び『スペイス・オディティ』収録の2曲、幻想的なフォーク曲 M13「Cygnet Committee / シグネット・コミティー」、ボウイにとって忘れられない思い出のフェスを歌ったM14「Memory Of A Free Festival / フリー・フェスティバルの思い出」でライブは閉じる。ミック参加のM7〜12と他の曲のサウンドを比べることで、ボウイの変身を語れてしまう。それほど、ミック・ロンソンのギターは決定的な凄まじい証拠となった。