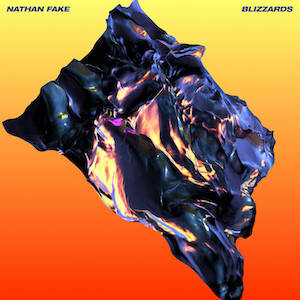小野島大が選ぶ、2020年洋楽年間ベスト10 テイラー・スウィフト、フィオナ・アップルら今年を象徴する作品も
Fleet Foxes『Shore』
Taylor Swift『folklore』
Jacob Collier『Djesse Vol.3』
Four Tet『Sixteen Oceans』
Nathan Fake『Blizzards』
Rian Treanor『File Under UK Metaplasm』
Fiona Apple『Fetch the Bolt Cutters』
Moses Sumney『græ』
Nicholas Jarr『Cenizas』
Run the Jewels『RTJ4』
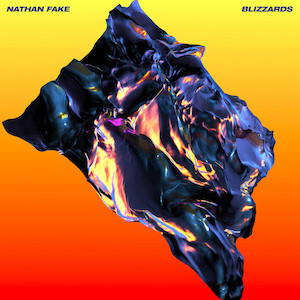
順不同。コロナという誰も予想しなかった未曾有の事態が音楽シーンに与えた影響はもちろん甚大だったが、音楽そのものの質や傾向になんらかの悪い影響があったかと言えばそうでもなかった。上半期に出たものはコロナ以前から準備されていたものが大半で、それ以降もむしろ、自宅作業が多くなって時間ができた分、作り込みがより緻密になり、さまざまな工夫が凝らされ、モチベーションがより高まった、つまりは意欲的かつアイデア豊かで完成度も高い作品が多かった印象がある。また複数のメンバーが一堂に会してのレコーディングが難しくなった分、バンドと銘打ちながら実際には曲を書いている中心メンバーがほとんどひとりでトラックを作っているケースも多く(Fleet Foxesなど)、バンドとは一体なんなのか、という問いかけがいつも以上に為される年だった。
また私が「新譜キュレーション」で対象としているエレクトロニックミュージックに関して言えば、いわゆるダンスミュージックのアルバムが激減し、いわゆるアンビエント〜ドローン系の作品が多くを占めていたのが今年の際だった特徴と言える。2019年も多かったが、2020年は体感上、リリースされるアルバムの7〜8割がビートのないアンビエント作だった印象。ダンスミュージックを作っても、それが鳴らされるべき現場が消失しているという現状も大いに関係しているし、アーティストの意識が自己の内面に向きがちだったということもあるだろう。もちろん玉石混淆だし、ずっと前から優れた作品をいくつも送り出している作家は多いが、やや食傷気味であったことも確か。

選んだ10作の中から今年を象徴するような作品を選ぶとすれば、やはりテイラー・スウィフトということになるだろう。The Nationalのアーロン・デスナーと全面的にコラボすることで、ポップとインディの垣根を打ち壊し、広義のアメリカンミュージックの再編成をも迫った大傑作である。コロナ禍という事態で両者がステイホームを強いられたため実現したプロジェクトであり、お互いがまったく顔を合わせることなく完全リモートで作られた、いわばロックダウンアルバムでもある。テイラーがアーロンに直に連絡を取り実現したもので、そのあたりの経緯も2020年的だ。とはいえテイラーの人としての成長やアーティストとしての自覚が伴ってのアルバムであり、年初に配信されたNetflixのドキュメンタリー『ミス・アメリカーナ』は、そうした彼女の変化を示す作品だった。内容もアーロンによるエレクトロニックなアレンジや技巧的なサウンド処理が為された圧巻の音響アート作品で、空間の広がりを意識することでテイラーのボーカルを際立たせる音像も魅力的だ。