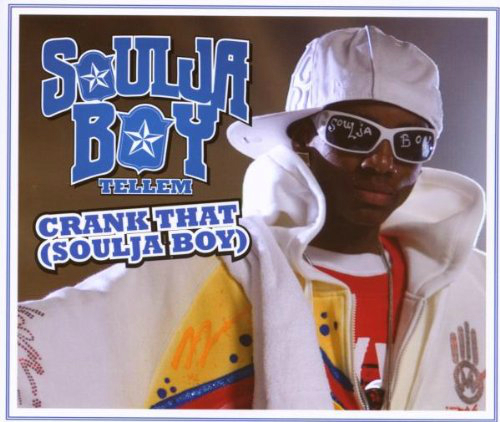「リズムから考えるJ-POP史」第9回
リズムから考えるJ-POP史 第9回:宇多田ヒカル『初恋』に見る「J」以後の「POP」
1990年代から2010年代まで。本書では、7つのトピックをアラカルト的にたどりながら、この30年のJ-POPを追いかけてきた。その締めくくりに、一枚のアルバムを取り上げたい。宇多田ヒカル『初恋』(2018年)である。

『初恋』、ポップミュージック全般からヒップホップ、ロック、ジャズに至るまで2010年代の後半に爛熟を見せたリズムの語彙をめぐる進歩と宇多田ヒカルの作家性がシンクロした一作だ。
また、作品としてのクオリティのみならず、『初恋』にも収録されたシングル曲などのリリースを経た宇多田の活動からは、「J」以後の「POP」をめぐる動きの予兆を読み取ることもできる。J-POPをめぐる30年を辿ってきた本連載の終着点にふさわしい作品と言えよう。
「人間活動」以後の宇多田ヒカルが見せた変化
1998年、シングル『Automatic/time will tell』で衝撃的なデビューを飾って以来、日本を代表するシンガーソングライターとして活躍してきた宇多田ヒカル。和製R&Bや「ディーヴァ」ブームの波に乗って登場しながら、軽々とその枠組みを乗り越えて数々のヒット曲を送り出してきた。デビューアルバム『First Love』(1999年)は日本で最も売れたアルバムとして知られており、この記録はもはやCDバブルが去ったいまとなっては破られることはないだろう。
しかし、デビューから12年、5枚のアルバムを発表したのち、2010年に宇多田は「人間活動」に専念するとして活動を休止する。その後、6年間のブランクを経て発表されたのが『Fantôme』(2016年)である。
同作でまず目をひくのはコラボレーションの多さだろう。かねてから親交のあった椎名林檎に加え、若手ラッパーからは本連載第6回でも取り上げたKOHHが、さらにオルタナティブR&Bデュオ・N.O.R.K.のメンバーであり、シンガー兼プロデューサーの小袋成彬が客演している。「人間活動」のための活動休止までのディスコグラフィのなかで客演があったのは、『ULTRA BLUE』(2006年)収録のTHE BACK HORNの山田将司が参加した「One Night Magic」のみだった。この事実だけでも、3人ものミュージシャンをフィーチャーすることの異例さはわかるだろう。
また、3作目となる『DEEP RIVER』(2002年)以来、自身で編曲やプログラミングまでを手掛けてきた宇多田が、初めてプレイヤーを集めてバンドによる生演奏を取り入れるようになった作品でもある。このコラボレーションを中心とする制作スタイルは、『初恋』に至る宇多田の復帰後の活動を特徴づけるものだ。
『Fantôme』で宇多田は、「日本語で歌うこと」に改めてチャレンジした。かつて「Automatic」でJ-POPの風景を一変させた(近田春夫いわく「敗戦」をもたらした)彼女が、日本語による表現を突き詰めることの意義は大きい。これは宇多田本人の歌に対する真摯さのあらわれであると同時に、「2010年代に日本語で歌うこと」を問う内容といえる。小袋成彬、KOHHといった若いシンガーソングライターやラッパーをフィーチャーしたことは、そうした意識のあらわれだろう。
この「日本語で歌うこと」へのこだわりは『初恋』へも受け継がれる。『Fantôme』収録曲の具体的な内容については紙幅の関係上割愛するが、「日本語で歌うこと」、「ラッパーやシンガーの客演」、「生バンドによるプロダクション」という点は抑えておきたい。
『First Love』から『初恋』へ
いよいよ、復帰第二作となる通算7枚目のアルバム『初恋』となる。『First Love』の直訳となるタイトルを付した本作は、デビュー20周年という節目を飾る一作である。
もともと、デビュー当時から宇多田ヒカルをめぐる評価で目立つのはリズムに対する感性だった。「本場」のR&Bのフィーリングを取り入れたことに加えて、特に日本語の慣習を裏切るような譜割りにも注目が集まった。しかし、そうした評価に宇多田自身は違和感を覚えていたようだ。
最初に「Automatic」っていう歌が注目された時に、「日本語の使い方に特徴がある」とよく言われて、本当に意味が理解できなかったの。「七回目のベルで(な・なかいめの/べ・るで)」って、言葉の途中の一瞬に間が空くことへの評論があって、「?? だって音楽じゃん? 言葉?」ってなった。
(宇多田ヒカル 小袋成彬 酒井一途 座談会)
歌であることと言葉であること、この2つは似て非なるものだ。歌の流れに従って言葉が屈折することで、伝わるものが増えたり、あるいは謎めいたりもする。この差異をどのように調停するか、すなわち「日本語としての意味を維持したまま、どうやってポップスを歌うか」は日本の戦後歌謡史を考えても大きな問題だ。しかし、宇多田はこの違和に拘泥することはない。
こうした宇多田の言葉に対する姿勢は、上掲の座談会で「第一言語としての音楽」というコンセプトにまとめられている。
酒井:ヒカルさんの今の話を聞いてて思ったのは、第一言語が音楽なんだろうな、って。
宇多田:あっ! そうそう! そんな感じ!
酒井:音楽を日本語に翻訳する、という作業が、作詞する時に発生してくるわけだよね。だからこそ、第一言語が日本語の僕らがもってる、日本語ひとつひとつの言葉に対するイメージを更新することができるんだろうね。
(宇多田ヒカル 小袋成彬 酒井一途 座談会)
第一に音楽があり、それを日本語なり、あるいは英語なりに翻訳していく。これは宇多田の制作プロセスにも一貫するものだ。彼女はいわゆる「曲先」の書き手で、デモまで出来上がった段階で歌詞を書く。自身初となる詞集に寄せたまえがきで彼女はこのように語っている。
私の作詞は作曲から始まる。
和音、主旋律、曲の構成、伴奏などがほぼ決まったデモを完成させてから、最後に歌詞に取り掛かる。
(宇多田ヒカル『宇多田ヒカルの言葉』エムオン・エンタテインメント、2017年)
ここで興味深いのは、「作詞は作曲から始まる」という表現だ。ふつうに考えれば、「作曲のあとに作詞が始まる」だろう。しかし、思わずこのように書いてしまうほどに、宇多田は作曲というプロセスと作詞を切り離せないのだ。
それでは、宇多田の「第一言語」たる「音楽」とはどのようなものか。これについても、座談会のなかで小袋成彬がこのように指摘している。
小袋:ヒカルさんの曲作りにおいて、違和感やメロディが重要ということは、プロデュースされてる中でもずっと言われてたんだけど、その次に来るのがリズムなんだろうなと思ってる。一緒に「パクチーの唄」を作ってたときも、まあリズムにうるさい。すごくこだわる。
小袋:[…]僕はこんなにリズムにこだわりをもって、聴きどころにしているシンガーって、あまり見たことがない。もちろん他にもいるけど、ヒカルさんはプライオリティがあまりにも高すぎて。
宇多田:私はメロディ自体をリズムとして捉えてるから、私からしたらリズムにピッチついてるみたいな感じ。
(宇多田ヒカル 小袋成彬 酒井一途 座談会)
つまり、宇多田にとって「音楽=言語」とは第一にリズムであり、メロディはその文彩なのだ。
この考えを踏まえて、『初恋』における「音楽」の世界に分け入っていこう。