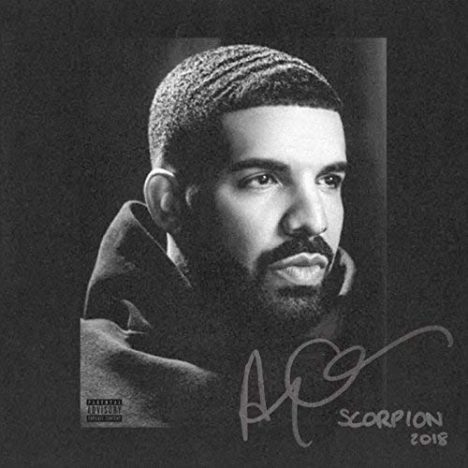『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』訳者・吉田雅史に聞く、ヒップホップ批評の新たな手法

もしあなたがヒップホップのビートについて思いを巡らせたことがあるなら、2006年に発表されたJ・ディラのアルバム『Donuts』が特別な作品であることに疑いはないだろう。ジャンルを問わずあらゆる音源からサンプリングし、その手法の可能性を最大限に引き出すテクニック、あえてクォンタイズをかけないことで生まれる絶妙にヨレたビート、溢れるほどのアイデアの中に滲み出る深い音楽愛、そして迫り来る死の匂いーーアルバムを通して聴けば、彼がどれほどの時間=人生をビートメイクに捧げてきたのかが自ずと伝わり、その深遠なクリエイティビティに触れることができるはずだ。同時に、リリース直後の同年2月に32歳の若さでこの世を去った天才ビートメイカーが、なぜ最後に病床でこれほど挑戦的なアルバムを作ろうとしたのか、多くの謎を投げかけてくる作品でもある。

西海岸を代表するアンダーグラウンドのヒップホップレーベル〈ストーンズ・スロウ〉の創始者であるピーナッツ・バター・ウルフに、「いくつかの曲で一体全体何をやっているのか理解できていない」と言わしめる『Donuts』には、どんな意思が込められていたのか? そもそも、もしもディラが生きていたのならば、『Donuts』は名盤足りえたのか? そうした疑問を、Q・ティップやクエストラヴ、コモンほか盟友たちの証言から紐解いていくのが、8月3日に発売されたジョーダン・ファーガソンによる書籍『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』のテーマだ。翻訳を手がけたのは、8th wonderのビートメイカー兼MCであり、批評家としても活動するMA$A$HIこと吉田雅史氏。『Donuts』の分析や制作過程のドキュメントにとどまらず、ビートメイキングの歴史やその独特の慣習、ヒップホップ史におけるデトロイトの位置づけにも光を当てた本書を翻訳するにあたって、吉田氏はどんな点に留意したのか。ビートメイカーであり、批評家でもある立場から語ってもらった。(編集部)
インストヒップホップの可能性と『Donuts』の特異性

ーー本書の序文は、ピーナッツ・バター・ウルフが寄稿しています。序文の中に出てくるウルフのレコード『Peanut Butter Breaks』(1994年)は、相方で幼なじみのラッパーであるカリズマが亡くなった後に、彼が再起をかけて作り上げた作品です。短いサンプルのループとビートだけで構築されたシンプルなインストゥルメンタルの作品ながら、彼が抱いていたであろう青春の終わりに対する複雑な感情や、その強い決意が込められている作品だと感じました。吉田さんは、インストのビートアルバムのどんなところに魅力があると考えていますか。
吉田:『Peanut Butter Breaks』と素晴らしい出会い方をしたんですね。いまのお話には二つ重要なポイントがあると思います。一つは『Peanut Butter Breaks』が『Donuts』と同じようにインストのビートアルバムであること。ウルフは『Donuts』について、「DJシャドウの『Endtroducing…..』(1996年)のようなものだと思って欲しい」と言っています。インストのヒップホップは非常にマイナーなジャンルで、それほど多くの需要があるものではありませんが、その中にも『Endtroducing…..』のように後のヒップホップのみならずインスト音楽全般に大きな影響を与えた名盤はあって、『Donuts』もまたそのような作品です。そこにはインスト作品だからこその可能性が確かにあって、たとえば言葉がないゆえに感情移入しやすい部分もある。歌詞によって限定される状況がないから、誰もが自らの状況や個人的な風景を音楽に重ねることができるので、いわば「人生のサウンドトラック」となりうる。それこそが、インストヒップホップの最大の魅力だと思っています。
それからもう一点、『Peanut Butter Breaks』から青春の終わりを感じたというのも、興味深いところです。というのも、『Peanut Butter Breaks』はA Tribe Called Questの最初の3枚のアルバム、特に3rdアルバム『Midnight Marauders』(1993年)の作風に近いところがあって、数小節のサンプリングのループをコラージュ的に重ねていく手法を用いた作品です。その手法は、ディラの世代のビートメイカーと比較すればウルフの言うところの「一世代前のビートメイカー」によるもので、実際にディラがビートメイカーとして参加した4thアルバム『Beats, Rhymes and Life』(1996年)からは本書の中では「ディラの方程式」と呼んでいるように、チョップした上モノに手弾きのベースラインを合わせるなど、全く異なるアプローチでのビートメイキングが行われています。1993年から1994年にかけて、ビートメイカーの世代交代が行われたという意味でも、『Peanut Butter Breaks』はヒップホップのゴールデンエイジという青春の終わりをビートの面で象徴する作品と言えるかもしれません。
ーー『Peanut Butter Breaks』は、二重の意味で青春の終わりを表していると。たしかにウルフは同作のリリース以降、1996年に〈ストーンズ・スロウ〉を立ち上げ、1997年からディラとの仕事を始めるなど、次世代の発掘に力を入れるようになりました。そして、1999年にはもう一人の天才ビートメイカーであるマッドリブとも契約し、2000年代にはディラとマッドリブの共作名義・ジェイリブの『Champion Sound』(2003年)をリリースするなど、独自路線を追求することで〈ストーンズ・スロウ〉はビートメイキングの世界において重要な位置を占めるようになります。
吉田:ウルフは、もともとバンドマンとしてキャリアをスタートしていて、レーベルのヘッドとしてもアヴァンギャルドな精神を抱き続けている人物です。どんなに売れなさそうなものでも自分が面白いと思ったものはリリースするタイプで、そうした自由なレーベルの気風は、やはりLAのような多文化間の交流が活発なシーンだからこそ育まれたものだと思います。ディラが故郷のデトロイトを離れてLAへ移ったのは、ライバルであり親友でもあるマッドリブの存在もさることながら、そのような気風に惹かれてのことだったのではないでしょうか。
ーーウルフは『Donuts』について、「アルバム制作を取り巻く事情を抜きにしても、僕にとってこれはストーンズ・スロウの歴史を決定づけた瞬間だったのだ。【中略】彼(ディラ)がもう一度病気になると分かるより前からすでにクラシック(名盤)だったのだ」と語っています。私自身、制作の状況などを一切知らないで『Donuts』を聴いたのですが、それでも圧倒的なクリエイティビティに特別な作品である印象を受けました。吉田さんは、『Donuts』はその背景が知られずとも、クラシック足り得た作品だと思いますか?
吉田:間違いなくクラシックと呼べる作品だと思います。僕も今回、本書の最後にディラのディスクガイドを作るに当たって、『Donuts』にまつわるエモーショナルな状況を一度抜きにして、可能な限りフラットな視点からサウンドだけを聴くように努めてみました。それでも、やはりこの作品の特異性は目立っていて、なんだか汲み尽くせない複雑さとともに、他の作品と比較すると違和感というか、異物感がある。個々の楽曲を見ても、一聴するとバラバラに思えるけれど、その並べ方や挿入されるSEによって驚くほどの統一感が与えられているんです。ディラが培ってきた様々な手法やアイデアがふんだんに詰め込まれていて、そういう意味では彼のクリエイティビティの集大成とも取れる。
僕自身もそうですが、ディラのようなビートメイカーは毎日のようにビートメイキングをする。ひとつあたりほんの数分でスケッチのように作ってしまう。そうすると食事を取るように日常生活の中の習慣になってくるので、一曲ごとに深い思い入れがあるわけではなかったりする。ディラもある程度の数のビートがたまると、バッチと呼んでミックステープにまとめていた。だからこそスケッチのようなミックステープから、さらにアルバムというひとまとまりの作品としてどうパッケージするかが大切で、言い換えると日常の積み重ねをどのように切り出してみせるのかが、インストヒップホップにおいても非常に重要なポイントだと思います。『Donuts』の収録曲の大部分は、ディラが最後に入院する前に作られたもので、病床ではエディットを行なっていたとされています。このエディットこそが、『Donuts』をアルバムというひとつの作品にまとめあげている。そしてそのエディットが晩年を悟ったビートメイカーの視点で行われていることが、『Donuts』を単なるビート集ではなく、ひとつの芸術作品と呼びたくなるものに昇華したのではないかと考えています。たとえディラのことを知らなくても、『Donuts』からは何か尋常ではないものを感じてもおかしくない。