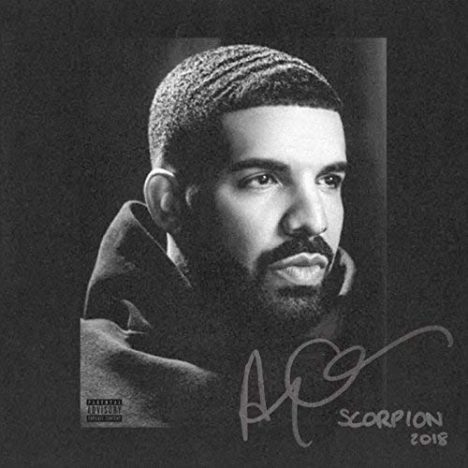『J・ディラと《ドーナツ》のビート革命』訳者・吉田雅史に聞く、ヒップホップ批評の新たな手法

批評家としての著者ジョーダン・ファーガソン

ーー『ディラと《ドーナツ》のビート革命』は、ディラの生涯を描いた伝記としての側面がありながら、『Donuts』をどう解釈するか、著者が見解を述べる本でもあります。翻訳をする中で、気づいたことは?
吉田:当然ながらディラ本人から話を聞くことはできないし、生前のインタビューもとても少ないので、必然的に周囲の人々の話から彼の人物像を立体的に浮かび上がらせている。本人の言葉というより、周囲の人々が彼とどんな会話をし、彼や彼の作品をどう見ていたのか、というところから『Donuts』を掘り下げていくのは、決して正解を持たない作品分析の手法としても有効なアプローチだと思いました。それに加えて、著者のジョーダン・ファーガソン自身の解釈を、哲学や現代思想の知見を交えつつ説明していくところが、ディラと『Donuts』の理解に複雑な視点をもたらしてくれます。
ーー周囲の人々の様々な解釈から、「そういう見方があったのか」と新たに発見することも多く、刺激的でした。また、精神科医のキューブラー=ロスによる「死の受容モデル」や、エドワード・サイードの「晩年のスタイル」を用いて、『Donuts』を詳細に分析していく手法も非常に面白かったです。著者のジョーダン・ファーガソンを、批評家としてはどう捉えましたか。
吉田:ジョーダンはカナダ出身ですが、アメリカのヒップホップ批評で印象的なものの中には、単に「この作品を好きな人は、きっとこの作品も気にいるはず」といったリスナーにお勧めを提示するガイドライン的なものではなく、様々な比較対象を駆使して批評家自身が独自の解釈を提示するものが少なくありません。ジョーダンがここで展開しているのは、かなり想像力を駆使した彼自身の解釈なので、そこは評価の分かれるところかもしれません。そこまで行くと妄想なのではという批判もあるかもしれない。しかし僕自身は見立てが独自の批評に惹かれるところがあるし、それらの存在によって物の見方が豊かになったと思っているので、ジョーダンの手法は刺激的でした。それから、何かを論じるにあたって、一見すると全く関係のない思想や作品をいくつか参照し、見えないところにある共通点を探りながら論を展開していくような批評は、まさにサンプリング的な手法でもあると考えています。本書の解説で、ビートメイキングのサンプリングの魅力をデペイズマンーーつまり異質なものの邂逅がもたらす驚異だと書いたのですが、本書自体にもまた、デペイズマン効果が表れていると思います。アルベール・カミュやサイードがディラの音楽と結びつくことへの驚きがある。
それから、ジョーダンが本書の中で繰り返し、「ディラはこの本を嫌うだろう」と述べているのも、とても印象に残りました。ディラは常に未来を向いている人物で、つい3カ月前に作ったビートにさえ興味を失うタイプだったので、過去を詮索されるのはさぞかし嫌がるだろうという意味なのですが、もう一つ、この言葉には作者の挑戦的な姿勢も隠されていると思うんです。というのも、批評家は作者が意図したことを言語化するだけでなく、作者が「そういう意識はなかったけれど、言われてみればそうかもしれない」と思うような、その無意識下にある物語を引き出すのも重要ですよね。つまり「嫌うだろう」とあえて書くことで、ジョーダンはそれだけ作者の意図に反するオリジナルの解釈を提示してみせようという意思を表明している。論じる対象である作家に嫌われてもいいから、それを言語化したいとも読める書き方には、批評という営みへの思い入れを感じます。