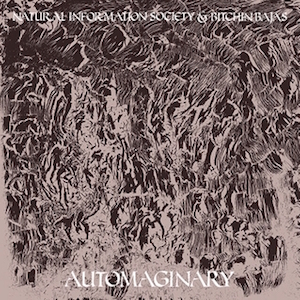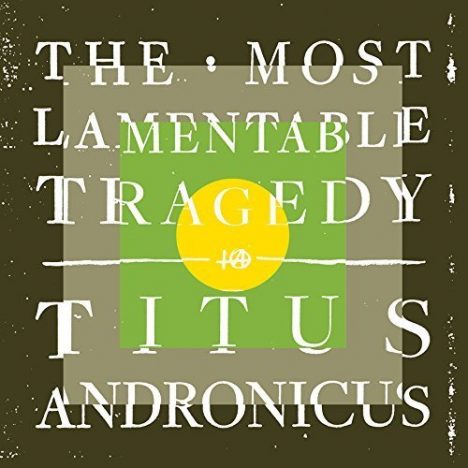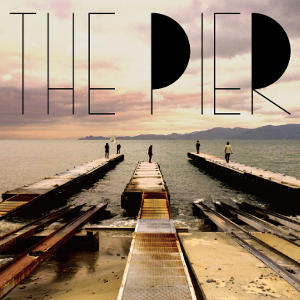岡村詩野の新譜キュレーション 第2回
ブルックリン・シカゴからアフリカ・アジアへーー岡村詩野がUSインディーのルーツを探る
10年以上前のこと、アニマル・コレクティヴのパンダ・ベアに初めて取材をした時、こんな話をしてくれたことを今も時々思い出す。「ブルックリンでは誰か一人が面白い音楽を見つけたら、それが仲間内で次々とシェアされていくんだ。00年代に入る前くらいに、僕が西アフリカのフォークにハマったらそのあとは周囲の友達が同じようにハマっていった。そうやって僕らブルックリン界隈のアーティストは、周囲の仲間と情報を共有させながらとりわけ欧米以外の音楽、ロックが誕生する前の音楽へと視野を広げているんだよ」。これは、彼らを含めたブルックリンの音楽家たちはなぜこんなにも音楽的越境が鮮やかでハイブリッドなのか?という質問に対する回答。イェール大学出身のデイヴ・ロングストレス(ダーティー・プロジェクターズ)とブライス・デスナー(ザ・ナショナル)を筆頭に、学究肌のアーティストが集中していることから、ブルックリン界隈のバンドの多くがリファレンスに対して研究熱心であることは知られている。それが音作りにおいては、コンテンポラリーなヒップホップ、ハウス、R&Bのサウンド・プロダクションへの関心などと結びつき、他のエリアにはない異種交配された作品へと昇華されてきたというわけだが、そんな彼らの活動や作品が00年代以降、ここまで広く世界中に知られるようになったのは、その未知なる領域、未知なるエリアの音楽の現在と過去を探究するだけではなく、さらにそれを仲間と分け合う開かれた意識によるものだった。いかにブルックリンがクリエイティヴィティを持った若者が集まる希有な場所であるとはいえ、そこにいる者たちの共闘意識がある程度はないとやはり大きなムーヴメントとして外には伝わりにくい。世界各地の音楽の聖地はおそらくこのようにして歴史を重ねて作られてきたのだろう。
そうした住民たちの意識の高さに惹かれて移住してくる音楽家も多く、アメリカはサンタフェ出身ながら東欧への一人旅や滞在を経て現在はブルックリンに暮らすザック・コンドンもその一人。彼のソロ・ユニット、ベイルートは既に過去3枚のアルバムをリリースしており、前作『ザ・リップ・タイド』(2011年)が発表されたタイミングでは初来日公演も実現、トクマルシューゴとのカップリング・ライヴを東京と大阪で成功させたことは記憶に新しい。ジプシー・ブラスやバルカン半島付近のフォークロア・ミュージックの影響を強く受け、自らトランペットも奏でるザックは、ザ・ナショナルやグリズリー・ベアのメンバーやオーウェン・パレットらとの交流から自然とブルックリンに拠点を移すこととなったそうだが、実際に前作あたりからあからさまな東欧音楽信者ぶりが後退し、開かれたポップ・ミュージックを聴かせてくれるようになった。長期的なツアーによる疲労や私生活での別れなどを経て完成させたという4作目『ノー・ノー・ノー』は新しいガールフレンドがトルコ出身であることから、彼女の母国であるトルコへと向い、そこで西アジアの国としての文化、宗教、民族性に触れたことが契機になったとのこと。コンドンが訪れた時は、前年に起こったタクスィム・ゲジ公園におけるデモを一つのピークとする反政府運動の影響が色濃く残っていた頃。“アラブの春”になぞらえて“トルコの春”とも呼ばれる政治改革の息吹が、コンドンに大いなる刺激を与えただろうことは想像に難くないし、トルコがアジアとヨーロッパの境目のような場所に位置することもまた、様々な辺境の音楽に魅せられてきたコンドンにとって創作のヒントになったのかもしれない。
そのザック・コンドンとつきあいの深いザ・ナショナルのブライス・デスナーはソロ・アルバム『Music For Wood And Strings』を自身のレーベルであるBrasslandから発表。ブライスはザ・ナショナルのサウンド面での要となる人物で、イェール大学時代に現代音楽を学んできた頭脳派だが、ここではフィリップ・グラスなどとの共演体験を積んできた彼らしく、地元ブルックリンの前衛パーカッション・カルテット“ソー・パーカッション”との共演を軸に完成されている。また、自作楽器を操ることで話題を集めているビューク・アンド・ゲイズ(Brasslandからアルバムを出している同じくブルックリンの男女デュオ)のアロン・サンチェスによるオリジナル楽器が使用されているのも注目すべき点で、ブライス・デスナーがブルックリン界隈に創作性ある現代音楽の要素を持ち込んでいることがよく伝わってくる1枚だ。全曲“木と弦”というタイトルが与えられているように、叩く音、弦を弾く音によって構成されており一切の歌はない。だが、決してアカデミックなクラシック音楽の系譜に位置したものではなく、むしろアフリカン・ビートにも連なりそうなパーカシヴでパッションある野性味を感じさせる演奏なのも魅力で、もしかするとこういう側面にアニマル・コレクティヴやヴァンパイア・ウィークエンドからのシェアによる影響が表出されているのかもしれない。
かようにハイブリッドな形でアジアやアフリカの音楽に向き合っているブルックリン界隈の連中同様、近年のシカゴからもそれまでの90年代ポスト・ロック世代とはまた異なる感覚の音楽家が登場してきている。2010年にサイケ~クラウト・ロック系バンドのCaveのメンバーであるクーパー・クレインとロブ・フライらによって始まったBitchin Bajasは、サイケ・アンビエントと言えるような作風で静かな人気を集めるグループだが、新作『Automaginary』は同じシカゴを拠点とするアヴァン・ジャズ系のNatural Information Societyとのコラボ作品。Natural~がタウン・アンド・カントリーのジョシュア・エイブラムスが中心ということもあり、今回はことのほかアフリカン・ミニマリズム的な演奏を試みているのが面白い。もともとジョシュアはファラオ・サンダースやムーンドッグなどに傾倒したベーシスト。昨年CD化された自身のソロ名義作でもモロッコの伝統音楽であるグナワを現地の弦楽器であるゲンブリを用いて聴かせるなど積極的に自身の音楽性を撹拌させてきているが、それとほぼ同じアプローチをここでも展開させており、結果、グナワのトランシーな感触とポリリズミックなジャズの要素とが混ざり切らずにミックスされている。