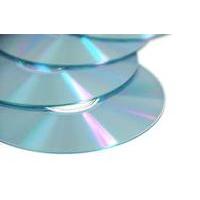話題騒然のアルバム『THE PIER』レビュー
タコツボ化時代に生まれた奇跡の生命体――くるり新作の音楽的背景を岡村詩野が分析
米『ローリング・ストーン』誌などに執筆していた音楽評論家、レスター・バングスは、77年当時に「僕らはエルヴィスについて同感していたような具合に何かに同感するということは二度とないだろう」と発言している。それを受け、同じく音楽評論家のグリール・マーカスは「その通りだ」とした上で、「ロックの聴き手はますます分離してしまい、種々雑多な聴き手が互いを無視しあっている」と述べた。これが80年のことだ。驚くことにこうした見識は34年後の今なお散見され、所謂タコツボ化していることの危機感のようなものが延々増幅されながら語られ続ける結果となっている。
だが、果たしてそれは本当に危機的な状況なのだろうか、と思うのだ。タコツボ化してバラバラになっているならちょうどいいじゃないか。そもそも、世界中のあちこちには何の遮断もなく魅力的な音楽がたくさん転がっている。その新旧バラバラな音楽を自在にピックアップして同一線上に並べてごらん。勿論、相当な想像力、撹拌力、創出力は必要だろう。でも、ほら、そうしたらこんなに新しい音楽が生まれるじゃないか。ここに届いたくるりの『THE PIER』というアルバムは、まさに分離分散の極致にある時代だからこそ誕生した奇跡の生命体のような作品だ。
ストリングスの滴るような音色と、ジャストなビートがレイヤーのように重なっていくオープニングの壮大なインスト「2034」をオーバーチュアにしてアルバムは幕を開ける。そして、世界各地の新旧様々な大衆音楽を力強く自分たちの手元に引き寄せつつも、昭和40年代前後の歌謡曲をも思わせる純然たる日本語の大衆ソングへと展開していく。例えば3曲目「浜辺にて」。大枠はダンス・ポップだが、エレクトリック・シタールのリフが軸になっていることもありヒンディー語の歌謡曲のようでもあるし、途中からはオペラのようなコーラスが挿入され、ついには英国トラッド風の鼓笛隊まで登場する、という具合。マリアッチのようなトランペットのイントロから入り、清潔感あるメロディと繊細な電子音が絡まってマーチング・バンドのように進行される「ロックンロール・ハネムーン」も、シャンソンを彷彿とさせるアコーディオンとアコギを中心に3拍子でゆるやかにたゆたっていく「遥かなるリスボン」もそうだが、どれもが1曲につき100個以上の音の情報が埋め込まれたアマルガムのようなポップスになっている。この情報量の多さを前にたじろぐ人も多いかもしれない。集中のエネルギーを消費して疲労を招く人もいるだろう。だが、筆者には、これほど同感できる豊かな音楽にまだ出会うことができるとは! みたことかレスター・バングスよ! という誇らしい気持ちと充足感しかない。