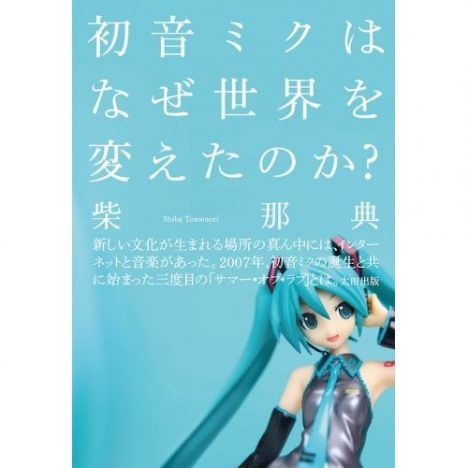新作『YANKEE』インタビュー(前編)
米津玄師が語る、“ボカロ以降”のポップミュージック「聴いてくれる人ともっと密接でありたい」

ボーカロイドプロデューサーの”ハチ”として数々の有名曲を発表後、本名名義で独自の歌世界を切り開きつつある米津玄師が、4月23日にセカンドアルバム『YANKEE』をリリースする。今作の特徴のひとつはバンドサウンドの導入。“ハチ”作品のエッセンスを取り入れつつ、前作『diorama』とも異なる、ダイナミックな演奏を聴かせている。インタビュー前編では、彼がシングル『サンタマリア』で宅録スタイルからバンドサウンドに移行したきっかけや、「普遍性」への志向、さらには想定するリスナー層についても語った。
「自分が作ったものに手を加えられるのが嫌だった」
――新しいアルバム『YANKEE』は、前作とはまた違ったバンド色の強い作品です。まず、どのような形で作り始めたのでしょうか。
米津:一曲一曲作っていって、曲が溜まってきたのでアルバムにしようと思って。だから前回とは全然違うアプローチで作りました。
――前作『diorama』はコンセプトを決めてから?
米津:前回は「街」というコンセプトを決めて、そこから作り始めたんですが、今回はそういう感じはなかったですね。
――今回、曲単位で作ったのはどんな理由からでしょうか。
米津:なんというか……前作でコンセプチュアルなものを作ったから、次は違うことをやろうというものがあって。というのも『diorama』は自分の家で一人で作って、誰かとやりとりして作ったものではなかったので。それが『サンタマリア』からバンド形式にして、ミュージシャンを招いてやるようになって。「これは慣れが必要だな」と思った。今まではやってこなかったことだったので、右も左も分からないというか。とりあえずそこに染まっていくために、ある程度時間と経験が必要だなと思いました。そういうところに向かって行くための実験とか訓練とか、そういう意味合いが少なからずありますね。
――その「サンタマリア」以降、アレンジ面でもバンドサウンドになったわけですが、どんな発見がありましたか。
米津:『diorama』の頃は、自分が作ったものに手を加えられるのが嫌だったんです。手を加えられた結果として作品が悪くなったとか、他の人の感性が悪いものだとは思わないし、客観的に見るとそっちの方が良いという意見もあると思うんですけど、自分の中に明確な線引きがあって。エゴの塊というか、自分が「許す・許さない」の線引きがあって。自分の中で「許さない」のラインに入っているものを提示されると、それだけでもう嫌になってしまう。そういうのがあって、自分一人で作ってきたんですけど、そういうところでずっとやっていても、同じことの繰り返しになるし、一人で作ることには限界がある。だから、ある種無理やりにでも、そういうところから出て行かないといけないと思って。それで「サンタマリア」を作っていくうちに、だんだん許せるようになってきたんですよ。デモの状態から音一つずらされるだけで本当に嫌だったんですけど、だんだん許せるようになってきて。
――なぜ許せるように?
米津:自分自身の変化もあると思いますが。ドラム、ベース、ギターにアレンジしたほぼ完成形のデモを渡して、で、レコーディングという手順を取っているんですけど、凄く良く理解してくれるんですよね。
――今作参加のプレイヤーとの出会いが大きかったんですね。さて『diorama』の密室的な感じも良かったですが、今回の音の跳ね方、リズムの感覚はまた新しい一面だと思います。今回のレコーディングではどのような音を求めていました?
米津:大きく変わったのは、「いろんな人にわかりやすく、ポップに」というのを、すごく心がけましたね。
――よりリスナーにダイレクトに伝わる音と?
米津:そう。
――ただ、米津さんの音楽はオリジナル性が高いもので、このスピード感、このテイストの音、密度は他にないように思います。
米津:わかりやすくというのは心がけたんですが、人と同じことをやってもしょうがないと思うので、それをどう文脈に乗っ取ってやるか、どう外すかっていうのは自分の中でも考えるところ、重要視するところですね。