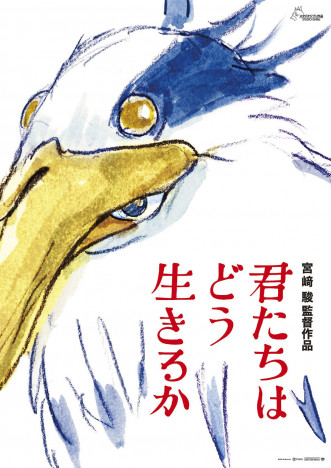日本アニメーションに到来した“作家の時代” 2022年を振り返るアニメ評論家座談会

日本映画製作者連盟(映連)は2022年を「アニメの当たり年だった」という言葉で総括した。その言葉通り、新海誠監督の『すずめの戸締まり』をはじめ、人気漫画/アニメ原作の『ONE PIECE FILM RED』『THE FIRST SLAM DUNK』と大作が大ヒットを記録。さらに湯浅政明監督の『犬王』に代表されるような映像演出に優れた作品も数多く誕生した。今のアニメ映画はIPの力と同等以上に、“作家性”の重要度が高まってきていることが分かる。
リアルサウンド映画部では、レギュラー執筆陣より、アニメ評論家の藤津亮太氏、映画ライターの杉本穂高氏、批評家・跡見学園女子大学文学部准教授の渡邉大輔氏を迎えて、座談会を実施。2022年の代表作を振り返りながら、「作家の時代」の到来による演出の変化、そして日本のアニメーションを支えるために必要な映画祭の存在などを語ってもらった。(編集部)
『犬王』と『ONE PIECE FILM RED』にみる作家性

ーー2022年の年間ベストを伺うと、みなさん『犬王』が共通してランクインしていました。大作が続いたラインナップの中でも本作の作家性は際立っていましたが、『犬王』の登場はどのような意義があったのでしょうか?
藤津亮太(以下、藤津):湯浅政明監督の“代表作”と呼べるものが登場したと言えるでしょう。『マインド・ゲーム』から本格的に監督として仕事を始められましたが、元々ビジュアル的に尖ったマニアックな表現をする方でした。それが『四畳半神話大系』以降ポピュラーな表現も増えてきた中で、今作は絵の力が強い尖った表現がまた前に出る一方で、同時にポピュラリティも濃厚に残っている形になっていました。『マインド・ゲーム』の頃は物語性が足りないと評されることもあり、ご本人もいろいろなインタビューで語っている通り「ドラマとはなにか」を考えながらキャリアを積んできている側面がありましたが、『犬王』ではドラマ性がしっかりと確立していて、そこにビジュアルとしての面白さがバランスよく調和していましたね。
杉本穂高(以下、杉本):そうですね、『犬王』は“歴史ものである”というのが面白いところだと思っています。歴史って固定的で動かし難いものだと思いがちだけれども、実はそうじゃないんだ、というのを湯浅監督の自由闊達なアニメーションによって強い説得力を与えられたと思います。原作者の古川日出男さんは、「自分が『平家物語』に新たに物語を付け加えるんだ」ということを語っておられました。結局、歴史の中の出来事について私たちはほとんど分かっておらず、新しい事実が判明していく度に歴史認識は絶えず更新され、変化していく。そういった事実と、湯浅監督のアニメーションとの相性がとても良かったですね。歴史ものはアニメではあまり積極的には作られてきませんでしたが、とても大きな可能性を拓いた気がしました。
藤津:そして音楽要素も加わっていて、ある意味では世界的なトレンドにもしっかりとはまっていましたよね。湯浅監督は、音楽を“心の解放”の表現としてよく使用しますが、今回はそれでハッピーになるわけではなく、音楽によって解放されつつも、同時に彼らはそれ故に歴史の中に埋もれていき、悲劇になる。湯浅監督のこれまでの作品と違うケースとなっていますが、それでも胸に残るラストになっていたのが印象的でした。
渡邉大輔(以下、渡邉):私も『犬王』はまず、湯浅監督自身も最近こだわりを見せ、また昨今脚光を浴びる音楽アニメとして面白い作品だったと思います。象徴的には『君の名は。』以降、アニメの映像と音楽のコラボレーションが大きなトレンドになっていて、メディア論的にもとても時代にフィットしていると感じます。そして近年、単純に音楽を使うだけではなく、キャラクター自身が「歌う」作品が続いていますね。『竜とそばかすの姫』『アイの歌声を聴かせて』など。これは、実写映画の『ボヘミアン・ラプソディ』『エルヴィス』と続いているミュージシャン映画の流れとも明らかに連動しています。2022年の『ONE PIECE FILM RED』や『犬王』も明らかにその流れの中にある作品ですが、それとは別に“個性”が際立つ作品でもあり、ポピュラリティもあった上で話題作となった点が印象深いです。

杉本:作家の名前で客を呼べる人は限られていますが、湯浅監督もその数少ないうちの1人になってきたというわけです。
藤津:そうですね。ただ、ロングランというか、今も特別上映が続いたりしてはいるものの、興行の数字はそこまで大きくないですね。
杉本:この興行の壁さえ超えられれば、もうやりたい放題できそうだなと感じます。なんとか10億円の興行成績に達してほしい作品だと思います。
藤津:作家性という点でいくと、『ONE PIECE FILM RED』も確実に触れておきたいです。どうしても『ONE PIECE』というIPの大きさの影に隠れてしまいがちですが、あれはどう観ても谷口悟朗監督の映画だったことは強調しておきたい。体感としては観客の1割程度の人しか『コードギアス 反逆のルルーシュ』や『スクライド』の谷口監督作品だと理解していなかったのではないでしょうか。
杉本:谷口監督はプロデューサー的な視点を強く意識される方で、今作で音楽をフィーチャーしたことも、全部谷口さんの戦略なんですよね。その戦略が全部ピタリとハマって大ヒットしたように私には見えていました。近年は、TVシリーズでも劇場クオリティの作画の作品が作られてきている時代なので、そういう時代に映画館に観客を呼ぶために“音楽”のチョイスがされたのではないでしょうか。

藤津:つまり「ゴールがどこか」みたいな話だと思います。谷口監督は、TVシリーズで渋い作品を作った時にインタビューをすると、プロデューサーから話を聞いた上で「これはヒットはさせなくていいのだと思いました」ということを言うわけです(笑)。別のところにゴールがあるプロジェクトと認識してディレクションした、というわけです。ただ、これまでの『ONE PIECE』の劇場版は少なくとも50億を超えた作品がずらずらとあるので、“ちゃんと当てる”ことが必要。そうなった際に何を描くのか、つまり“ルフィが誰と戦えばいいのか”に焦点があたります。そこに“地に足のつかない理想を語るキャラクター”がつらい目に遭うという谷口監督作品らしい要素を配したところに、作家性を強く感じました。
ーーそうした観点でいえば、中規模の作品も話題作が多かった印象です。
藤津:『夏へのトンネル、さよならの出口』(以下、『夏トン』)も田口智久監督の明確な演出で作られていましたよね。原作はSFギミックのある青春小説で、サブキャラの登場シーンを原作より減らしてシンプルに作っている分、どういうカット割りにするか、そしてどこにカメラを置くかが研ぎ澄まされていましたね。田口監督は今ではもう仕事が詰まっていて、業界でも期待されている人だと思いますが、2022年を「作家の時代」とするならば、本作が一番印象深かったです。
杉本:田口監督はこれから4クール構成のTVアニメ『BLEACH』にかかりきりになってしまうので、自身の色濃い作家性のあるフィルムをこのタイミングで1本残せたのはキャリア的に大きい気がします。
藤津:田口監督の『デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆』はすごく良い映画でした。主人公たちが大人になってデジモンに別れを告げる話を、細田守監督が手掛けた最初の映画『デジモンアドベンチャー』の引用を入れつつ作っていました。やはり注目の監督ですし、この後にもう一度長編をやってほしいなと思います。
杉本:ただし、『夏トン』もそんなにヒットしているわけではないのが残念ですよね。作家の名前でお客さんを呼ぶということが、新海誠監督を除けば、なかなか難しい印象があります。
藤津:なので私自身は、優れた作家性を持っていながら名前がまだ知られていない監督について積極的に語っていきたいと思っています。TVアニメ『宇宙よりも遠い場所』のいしづかあつこ監督作『グッバイ、ドン・グリーズ!』も、演出がリードして作られている映画だと感じました。今回は脚本を自身で書かれているので、脚本家から見ればバランスが良いとは言えないかもしれないのですが、作中ではキーポイントのところに赤い色が必ず置かれていて、そうしたイメージを持ってドラマを語ろうとしている作家だと思いました。
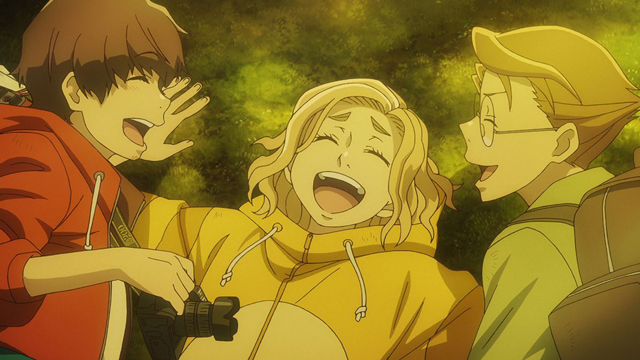
渡邉:そうした作家性の話と同時に語りたいのが、昨今のアニメ映画のプロモーションについてです。『君の名は。』以降、ここ数年、劇場オリジナルの長編アニメ映画のブームがずっと続いていますが、『夏トン』も含めて、どうしてもいまだに「『君の名は。』っぽい」ポスターや宣伝イメージが打ち出されがちです。ネットでは「ジェネリック新海誠」などと呼ばれているものですね(笑)。その傾向は2022年もあり、例えば『バブル』があまり盛り上がらなかったのもそこにかかわっているかなと思います。
杉本:映画会社のアニメの売り方がまだ手探りな感じがしますよね。『君の名は。』が売れたので、同じようにやれば売れるんだろうという考えがちょっと透けて見えるプロモーションはたくさんあったと思います。どちらかといえば、『君の名は。』の、あのテイストは、新海監督の作家性があって輝くものだと思います。異なるセンスの他の作家がやって上手くいくものではない。そういう意味で『バブル』は、あれが荒木哲郎監督の得意ジャンルだったかというと、必ずしもそれまでにやってきたこととは違う気がします。映画会社がもっと、監督のセンスを活かせる企画をたて、作品を売り出せるようにならないといけないと感じています。
渡邉:『君の名は。』でやってきたようなプロモーションは、消費者としてはすでに食傷気味になってきていて、なかなかヒットに繋がらない。しかし、『夏トン』のように、個別の演出としては観るべき作品が作られている。そうした、ある種の「プロモーションの行き詰まり」があると思っています。
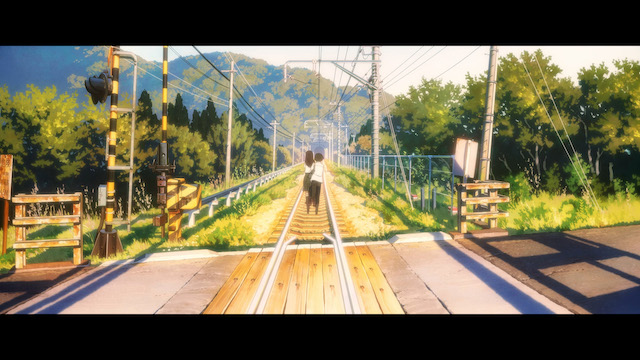
藤津:そういう意味では、企画が「みんなが期待するハードな荒木監督」という“作家性”への期待とはミスマッチな感じがしましたね。僕は80年代のアニメに通じるエンタメ作として楽しみましたが。
杉本:プロモーションの話で言えば、中級ヒット作品の中では『五等分の花嫁』とか、『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』があるのですが、これらの作品の配給会社って必ずしも大手とは限らず、ポニーキャニオンとかバンダイナムコフィルムワークス(旧バンダイナムコアーツ)など自社で配給している作品ですよね。
藤津:いわゆる“メーカー”さんですね。
杉本:映画会社の力を借りずにこれだけのヒットが作れる時代になったというのは、ステージが一つ変わったなという印象があります。やはり、こうしたメーカーはアニメファンの心をつかむ術をよく知っていると思うんです。そういうメーカーが映画作家をプロデュースするようになると面白いかなと思っています。