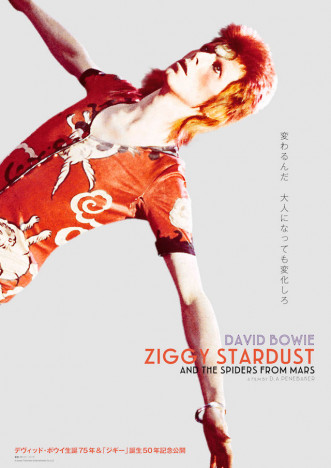『スターダスト』が掲示した新たなデヴィッド・ボウイ像 1人の若者が“異星人”になるまで

イギリスの音楽誌『NME』に「史上最も影響力のあるアーティスト」に選ばれたデヴィッド・ボウイは、様々なカルチャーから常に影響を受け続けたアーティストでもあった。そして、その影響を独自に昇華させて、音楽性やアーティストイメージを変化させ続けた。なぜボウイは自分らしさにこだわらず変化することを選んだのか。実話をもとにして、ボウイのアーティストとしての原点にフォーカスしたのが映画『スターダスト』だ。
映画の舞台となるのは1971年。当時、ボウイは24歳でサード・アルバム『世界を売った男』を発表したばかり。前作『スペイス・オディティ』(1969年)に収録されたシングル曲「スペイス・オディティ」がヒットして一躍注目を集めたものの、『世界を売った男』でセールスは落ちてしまう。そこでボウイはアメリカでプロモーションツアーをして名をあげようと決意。渋るレコード会社を説得して単身アメリカに乗り込んだ。

しかし、初めてアメリカにやって来たボウイは完全にアウェイ状態だった。ワシントンの空港に降り立ったボウイは華美な衣装を身にまとい、空港職員に「オカマ野郎」と陰口を叩かれる。当時、イギリスではグラムロックが盛り上がりつつあったが、アメリカでは男が着飾ることに強い偏見があった。映画ではアメリカに降り立ったボウイが、いかに「異星人」だったかを観客に伝える。しかも、レコード会社のミスで就業ピザが申請されていなかったため、ボウイはアメリカでコンサートを開くことができなかった。
先が思いやられるなか、ボウイを空港に迎えに来たのはリムジンではなく、レコード会社のパブリシスト、ロン・オバーマンのくたびれた車。宿泊するのはロンの実家だ。レコード会社から見捨てられた状態でもボウイは諦めず、ロンが必死で見つけた場末のクラブや小さなパーティで演奏しながらアメリカを横断していく。ドサ回りもいいところだが、ボウイにとって素顔のアメリカは刺激的だったに違いない。

NYについた途端、憧れていたアンディ・ウォーホルのパーティにいそいそと出かけていく姿も微笑ましいが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのライヴを観に行ってルー・リードと話をしたと思ったら、すでに脱退していたルーのふりをしたメンバー、ダグ・ユールだったというオチ。また、旅を通じて絆を深めていくロンから、未来の親友、イギー・ポップの魅力を叩き込まれたりと、ロックファンならニヤニヤしてしまうエピソードがちりばめられているのも楽しいところ。最悪のアメリカツアーがボウイを鍛え、そこで得た知識や体験がアーティストとして成長するきっかけになったのだ。
そして、そんな旅の途中にフラッシュバックのように差し込まれるのが、ボウイがデビューする前の記憶だ。それはおもに10歳上の兄、テリーにまつわるもの。ボウイはテリーから音楽的な影響を受け、テリーのことを深く愛していた。ところがテリーは次第に精神のバランスを崩し、ついには精神病院に入院してしまう。その悲しみ、そして、いつか自分も精神病を発症してしまうかもしれないという不安(ボウイの母方の叔母と祖母も精神病を発症していた)がボウイを苦しめていた。