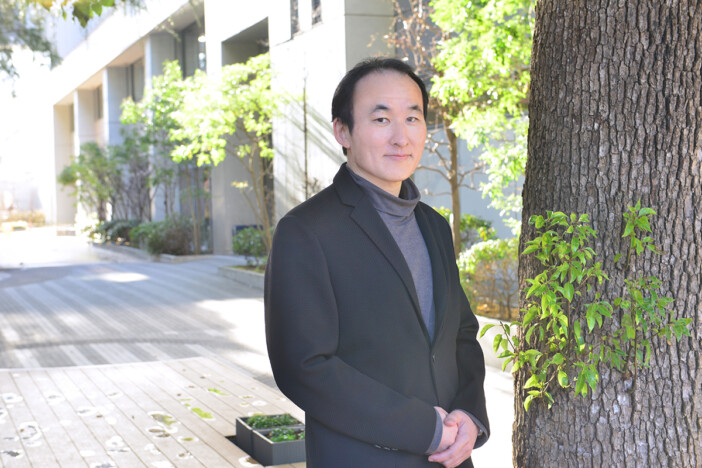こだま × 青山美智子『けんちゃん』対談「一人ひとりにとっての自然体とは何なのか、読者に問いかけている」


私小説『夫のちんぽが入らない』(通称:『おとちん』)で注目を集めたこだまが、初の創作小説『けんちゃん』(扶桑社)を上梓した。特別支援学校の寄宿舎を舞台に、ダウン症の男子高校生・けんちゃんの日常を描いた本作は、鋭さとユーモアを併せ持つ筆致で「自然体に生きること」の清々しさを伝えている。
「けんちゃん。ただ、あなたの隣にいてもいいですか。」と本作の帯コメントを寄せたのは、作家・青山美智子。かねてよりお互いにリスペクトを寄せていたというふたりが、今回念願の初対面を果たした。「やっと会えましたね!」という温かなやりとりから、9年という長い年月をかけて完成させたこだまの本作への思い、そして青山が惚れ込んだ「こだま文学」について熱く語ってもらった。
スポーツのゴールを見届けた気持ちで「こだまさん、よくやった!」

――『けんちゃん』は、こだまさんが特別支援学校での経験がベースにあるそうですね。
こだま:はい。この本に登場するけんちゃんは創作なんですけど、もともとモデルとなる“けんちゃん”がいて。彼のことが大好きだったので、以前からエッセイや文芸誌で何度か書いたことがあったんです。それで、『おとちん』を出したころから、担当編集さんに「次の本は、けんちゃんのお話がいいんじゃないですか」というお話をいただいて。ですが、創作小説の書き方に慣れていなかったこともあって、なかなか進められず……。9年かかってやっと書き上げることができました。今は、ただただホッとしています。
――青山さんは、そんなこだまさんの活動をずっと見守られていたんですよね?
青山:SNSやインタビューでこだまさんの近況を拝見していて、新作のタイトルが『けんちゃん』だと知った瞬間「あの“けんちゃん”だ」と気づいた自分に、「どんだけファンなんだよ」って思いました(笑)。今日はファンミーティングのような気持ちでここにいます! 小説家って、どこかアスリートに近いところがあると思っていて。こだまさんが『けんちゃん』を書き終えたと知ったときは、スポーツでゴールの瞬間を見届けたときみたいな気持ちで、とにかく「こだまさん、よくやった!」と称えたい気持ちでした。
――青山さんが、こだまさんの作品に注目されたのは、いつごろからなのでしょうか?
青山:『おとちん』が発売される半年ほど前ですね。タイトルと紹介文を拝読して「これは大真面目な本だな」と思って、すぐに予約したんです。その刊行が2017年1月で、私が小説家としてデビューしたのが2017年8月なんですよ。勝手ながら、私はこだまさんのことを「同期」だと思っていました。
こだま:私のほうはデビューが同時期だったなんて、教えていただくまでまったく気づかなくて。青山さんってたくさん本を出されていて、ずっとベテランの方だと思っていたんです。青山さんが『リカバリー・カバヒコ』(光文社)を発表されたころ、書店で「青山さんおすすめ本」として私の本を取り上げてくださっていることを書店員さんや編集者さんを通じて知って、驚きました!
青山:でも、こだまさんもご自身のエッセイに私の本のことを書かれていましたよね。読者として読んでいたので、「ひゃー!」ってなりましたよ。
――おふたりが直接メッセージのやりとりをされたことは?
こだま:なかったですね。互いにSNSのリプライくらいだったかも。あ、青山さんが出演する配信でサプライズ的に短い動画のメッセージを送ったことはありました。
青山:そういう距離感もどこかこだまさんと近いものがあるのかなと思っていて。今日だって、ほら! スカートがちょっと似ていません?
こだま:私も思いました! けんちゃんといえば赤、と思って履いてきたんですが、もしかして……?
青山:もちろん、私もけんちゃんをイメージして履いてきました!
こだま:うれしいです! 青山さんが以前「本に合わせてお洋服を決める」とおっしゃっていたのを見かけたことがあるので、「もしかして合わせてくれたのかな? それとも次の青山さんの作品にちなんでいるのかな?」と思っていて。
青山:いやいや、今日はもう『けんちゃん』の日なので!
――雅なやりとりですね。そんなこだまさんファンの青山さんとしたら、帯コメントの依頼には感無量だったのでは?
青山:それは、もう「ついに、この日が!」という気持ちでした。もちろん、こだまさんの作品に関われる喜びもありましたが、担当編集の方からのメッセージに「“寄り添う”とも違う」という言葉が添えてあったのが胸に刺さりました。どうしても、障害のある方が登場するお話だと「寄り添う」って言葉が使われがちだと思っていたので。これは、上からでも下からでもなく、寄り添うでも向き合うでもなく、フランクな立ち位置で「隣にいる」っていう物語なんだなと感じて、あの一文になりました。
「そんなわけない」が「そんなわけある」になってしまう「こだま文学」

――改めて、青山さんがこだまさんの本に惚れ込んでいる理由について教えてください。
青山:私は「こだま文学」と呼んでいるのですが、まず文体がポエジーで求心力をすごく感じるんです。ちょっと朗読していいですか。40~41ページにかけての文章なんですけど……。
暗い窓に疲れた女の顔が映る。夜の静かな廊下は非日常的で、記憶の中を彷徨っているような錯覚を起こす。廊下のまばゆい蛍光灯を順に落としていく。ほんのりとやさしい橙色の常夜灯が、天井から通路を照らす。緑色の非常口のマークも急に存在感を増す。明るい世界では目立たなかった者たちが生き生きと浮かび上がる。非常口の中の人物が心なしか昼間よりスピードを上げている。
これっ! この何がすごいかって、最後の「非常口の中の人物が心なしか昼間よりスピードを上げている」ってところ。たぶん、この一文を書こうとすると多くの人が「スピードを上げているように見える」ってなると思うんです。でも、「上げている」って言い切ってしまう。これが「こだま文学」。「そんなわけない」が、こだまさんが書くと「そんなわけある」。これが言いたかった!
こだま:ありがとうございます。恐縮です(照)。
青山:待って! まだあるから(笑)。もうひとつお伝えしたい魅力が「的確なツッコミ」。たとえば『けんちゃん』の14ページ。けんちゃんが現れる場面の描写なんですが……。
本人はうまく隠れているつもりかもしれないが、丸みのある背中におどろおどろしい書体で『網走監獄 脱獄中』とプリントされていた。目立ちすぎる。脱獄があまりに下手すぎる。
このリズミカルなツッコミって誰かに習ったり、努力して手に入れられるものではないんですよ。このクールな眼差しも天才的!
こだま:けんちゃんについては、もともとツッコミどころが多すぎるんですよね。
青山:でも、決して貶めるものではないんですよね。笑いってとても繊細で、誰かをバカにしたり、逆に持ち上げすぎていても素直に笑えないじゃないですか。すごくストレートなのに、誰も傷つけていないから気持ちよく笑える。それはすごい才能だと思います。まだまだ語りたいところはありますが、ひとまずこのくらいで(笑)。
こだま:「誰も貶めない」とおっしゃっていただきましたが、私も青山さんに対してもそう思っています。私が最初に青山さんの物語に触れたのが『お探し物は図書室まで』(ポプラ社)でした。当時、落ち込んで何もできない時期で、本も読めなかったんです。でも、この本なら読めるんじゃないかって、ページをめくったら、読み進める手も涙も止まらなくなって……。その人が今、必要だと思う本をそっと差し出してくれる司書の小町さんが、「私は何も。あなたが自分で必要なものを受け取っただけ」と言うのも、とてもやさしいんですよね。教えるんじゃなくって、自分で道を探せるようなお話なのが、すごく素敵で大好きです。
青山:どうしよう! 推しに推されるっていう、最高の幸せ!
みんながなれない「自然体な自分」を、全部けんちゃんがやってくれた

――支援学校を舞台にした『けんちゃん』では、「障害」や「多様性」といったテーマも自然と立ち上がってくると思います。作品を書く上で、何か心がけていたことや意識していた点はありましたか?
こだま:もしかしたら障害者への一般的な視線って、どこか同情的だったり、あるいはどういう感情で接していいかわからないものだったりすると思うので、そこだけは崩したいなという思いがありました。私自身、特別支援学校で働き始めたときに、それこそけんちゃんに教えてもらうことがたくさんあったんです。何もできず、ガチガチに固まっていた私のところに、けんちゃんはササッと近づいてきて、ボソッと面白いことを言って去っていく。その姿に、話題なんか用意しなくても話ができるんだって気づかされたりもしました。自分が実際に見てきた世界が、もともと想像していたよりも、すごくいろんな要素を含んでいるものだったので、そこが伝わってほしいなと。
青山:私自身いつも思うのは、心でも体でも「他の人と同じようにできないこと」が「障害」なのだとすれば、「障害のない人なんているだろうか」ということなんですね。『けんちゃん』を読んでいて、一番シンパシーを感じたのはけんちゃんでした。実際、原稿が書き上がったときには、ひとりでけんちゃんみたいに白鳥のダンスをすることもありますしね(笑)。
じゃあ、どうしてみんながけんちゃんでいられないのか。それは、人にどう思われるかとか、迷惑になるんじゃないかって、自然体でいることを自分で止めてしまうからだと思うんです。目立たず、平穏でいるほうがラク。でも、その選択が結果的に生きづらさになっているというねじれがあります。
そういう点では、葉月ちゃんの第四章はすごく核心を突いた章だと思いました。イヤーマフをつけていたほうが葉月ちゃんにとっては自然体でいられるんだけれど、それを装着することで周囲から「ふつうの人」として見られなくなるのが辛いと悩む。一人ひとりにとっての自然体とは何なのか。障害や多様性も含めて、読者に問いかけている章だと感じました。
117ページで「自分の嫌いな部分ってある?」と聞かれたけんちゃんが、「一個もないね」と即答するシーンにも端的に表れていますよね。私たちは周りに合わせて自分を誤魔化したり、ふと素の自分が出てしまったときに、どちらにしても自分を嫌いになりがちですよね。でも、けんちゃんにはそれがない。あるがままが「けんちゃんなんだ」って言い切れる。もちろん、全員がけんちゃんになったら社会は回らない部分もあるんですけど(笑)。だからこそ、けんちゃんは魅力的なんですよね。
こだま:私は書くだけでいっぱいいっぱいだったので、こうして言語化していただいて今すごく感激しています。たぶん自分がなれない部分を、全部けんちゃんがやってくれていたんですね。
落ち込む登場人物たちに共感する読者にも「間違ってないよ」と伝えたい

――『けんちゃん』には本当に魅力的な人物がたくさん登場しますが、思い入れのあるキャラクターはいますか?
こだま:コンビニ店員の七尾くんは私のなかで思っていたことを、全部言ってくれるキャラクターでした。「もっとフラットにみんなで付き合っていこうよ」って思っていても、なかなか自分からは周りに言ったことがなかったので。逆に、難しかったのは多田野先生。臨時職員をしていた当時の自分と重なるんですけど、だからこそ縛られてしまったというか。どうやったら自由にできるかなって苦戦しながら、第一章を書いていました。
青山:私は第一章がすごく小説を意識して書かれているなって思いましたよ。「こだまさんの話」ではなく、「これは小説の話です」という読ませ方をしているなと……って私が言うのもすごくおこがましいんですけど。
こだま:いえいえ、ありがたいお言葉です。実際に、その切り替えがすごく難しくて。ただ一方で、自分の体験って結構書き尽くしちゃっているところがあって。そういう意味では、けんちゃんがいてくれたから書けた小説だなと思いました。けんちゃんって他の人なら「ありえない」ことも「やってそう」と思わせてくれたというか。
青山:私が『けんちゃん』の登場人物たちを愛しく思ったのは、基本的にみんな落ち込んでるところなんですね。一つひとつの出来事を通じて、自分の愚かしさや情けなさを痛感して、反省するんです。本人はしんどいと思うんですけど、私はそういう人のことが好きですし、信用できるって思うので。どこかで、そういう人が苦しみすぎない社会であってほしいという願いもあります。
――その自己反省の感度の高さは、青山さんの小説に登場するキャラクターとも近いものを感じました。
青山:そうかもしれません。聖人君子でいることが偉いのではなくて、情けない自分をちゃんと振り返られることのほうが大切で。「落ち込んでいる時点で間違っていないよ」って伝えたい気持ちがあります。
こだま:私自身も余計なことをやっちゃって、落ち込むことがすごくあるので。そういうのを書きたいなって思っていたんです。「障害者について書いた本ですよ」という壁を感じることなく、登場人物たちに「なんか自分に近いな」って親近感を持ってもらったり、「支援学校ってこんな感じの施設なんだな」って身近に思ってもらえたらうれしいですね。
青山:あの最後にもうひとつだけ言わせてください(笑)。この『けんちゃん』って、視覚的にものすごく魅せる作品だって伝えたくて。雪とか綿毛とか、雪虫とか、白いものが全体を通して舞っているんです。そこに、けんちゃんの赤い服が効いていて。そしてこの装丁! この全体的に白いビジュアルに、スピン(しおり紐)がけんちゃんの赤! この間に入っているピンクの紙も、寄宿舎のカーテンの色! もう、どこまで考えてこの本が出来上がったのかと胸がいっぱいになりました。この表紙の折込みも、まるでプレゼントかのようじゃないですか。こういう作り手の愛情っていうのは、やっぱり伝わるんですよね。素晴らしいです、本当に幸せな本だと思いました。
こだま:雪とか白鳥っていうのは、けんちゃんのいるオホーツクの特徴として入れたいなって思ったんですけど、けんちゃんカラーについては、あの“けんちゃん”が本当に赤好きだったんですよ。スピンに関しては最初は銀だったんですけど、担当編集さんから「けんちゃんの色に」って最終段階で提案されたものでした。この『けんちゃん』も、『おとちん』のときと同じ担当編集さんとデザイナーさんのコンビで。私が書き上げるのに9年もかかったこともあって、すごく丁寧に作っていただきました。
――こだまさんファンの青山さんとしては、こだまさんの今後への期待は?
青山:もう好きなものを好きなように書いてほしいです。それが一番! こだまさんが気持ちのいい状態で書いた本が、ファンとしては読みたい本です。
こだま:担当編集さんから「今度は意地悪な人が出てくる話は?」と提案され、面白そうだなと思いました。頑張って書いてみたいなって思っています。逆にお聞きしたかったんですけど、青山さんの書かれる小説ってすごく幅があるじゃないですか。昔話がモチーフだったり、海外も舞台になったり、長い年月を経ていたり……どうやって思いつくんですか?
青山:私の場合、全部の物語が繋がっていて、ちょっとずつ他の物語の登場人物が出ているんです。だって、1つの作品のちょっとした場面にしか出てこないなんて、もったいないじゃないですか。その子にだっていろいろと人生があるのに。昔の友だちを「今なにしてるんだろう。また会いたいな」って思い出すような感覚で登場させていて。そしたら「この子とこの子が知り合いだった」なんてこともあるので、ネタが尽きないんですよ。
――なるほど! では、いつか青山さんの作品に、けんちゃんがススススッと出てきたり!?
こだま:それ面白いですね。オホーツクに行く物語があったら、ぜひ支援学校に寄っていただいて。けんちゃんの様子をのぞいてみてください。
青山:いいんですか? スペシャル・サンクスで、こだまさんの名前を入れて? なんて幸せな世界! いつか実現できたらいいですね。
こだま:ぜひ。やってみたいと思うことを自然体でやってみせてくれるのが、けんちゃんなので!
■書誌情報
『けんちゃん』
著者:こだま
価格:1,650円
発売日:2026年1月20日
出版社:扶桑社