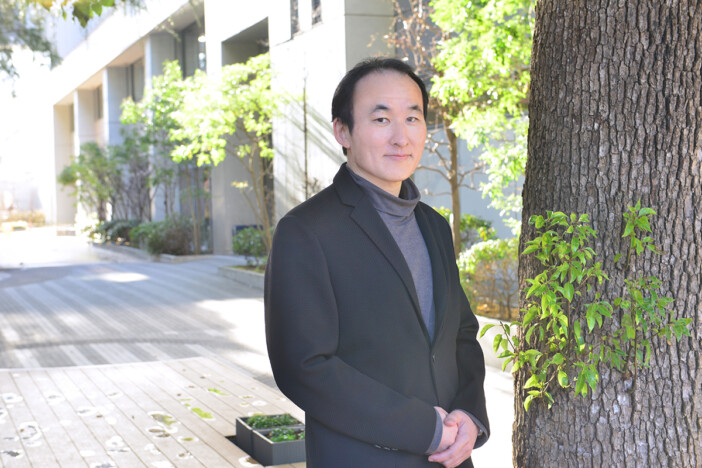【連載】柳澤田実 ポップカルチャーと「聖なる価値」 第五回 カトリック回帰と前衛:ロザリア、ダイムズ・スクエア・シーン、ウォーホル

「ポップカルチャーは我々の社会の宗教である。消費財は我々の聖餐である。セレブリティは我々の聖人である。名声は不死である。」(Paul Elie, The Last Supper: Art, Faith, Sex and Controversy in the 1980s, Farrar, Straus and Giroux, 2025)
若者のカトリック回帰
2025年、欧米のメディアでは、若い世代にキリスト教信仰への回帰が見られることがたびたび報じられていた。「信仰復興と言えるほどの数ではない」という留保がつきつつも、米国では全世代でZ世代の教会出席率が最も高いことが指摘された。特に若者が回帰しているのが、カトリックであるということは近年珍しく、イギリスでは英国国教会からカトリックへの改宗者が増え、世俗化が進んだフランスではZ世代の洗礼が増加し、パリからシャルトルへの巡礼にはおよそ20000人の若者が参加したと報じられている。ポップカルチャーにもカトリック回帰のような現象が見られ、スペインでは16世紀の修道女の著作を現代生活の指針として紹介するポッドキャスト「Las Hijas de Felipe」が人気を博し、ドルチェ&ガッバーナは「信仰と工芸の祝祭」をテーマに、司祭や枢機卿の祭服を思わせるローブをモデルに纏わせたショーを2025年7月にサンタンジェロ城で行い、賛否を巻き起こした。
4月にフランシスコ教皇が亡くなり、5月にはコンクラーベやレオ14世の教皇就任式がネットで生中継され、世界中の人々がカトリックの壮麗な伝統的儀式を目にしたことを思うと、2025年にカトリックへの回帰現象が起きたことは驚くべきことではないのかもしれない。しかし2025年も終わりに近づく11月にリリースされたロザリアのアルバム『LUX〔ラテン語で「光」〕』は、このカトリシズムの復興が決して表層ではなく、若者個々人の精神の深層で起きていることを示した。

アルバムのアートワークで修道女の白いベールを被ったロザリアは、カトリック国のスペイン出身で、祖母と教会に通った経験を持つと言う。2023年に婚約を解消した彼女が「光を求める旅」として制作したこのアルバムのために、ロザリアは、アビラの聖テレジア、ビンゲンのヒルデガルト、聖クララ、シモーヌ・ヴェイユなど、欧州のカトリック文化圏で崇拝される女性の神秘主義者たち、そして了然元総尼も含む様々な文化圏の女性神秘家たちについてリサーチしたそうだ。確かに歌詞には様々な引用が散りばめられ、その影響は十分に感じられるが、何よりこのアルバムが描く彼女の辿った道行きこそ、とても女性神秘家的な内容だと言える。
すでに本人が様々なインタビューで語っているように、ロザリアはこのアルバムを作るにあたって禁欲的な生活を送り、「より望まず(desire less)」、「自分のなかにできるだけ余白を作り」、「降伏する(surrender)」ことに徹したと言う。
これは「自己を放棄すること」によって逆説的に「自分になる」という、古代からキリスト教の修道者が探求してきた実践にほかならない。その伝統の中でも、ロザリアが参照した女性の神秘主義者たちは、俗世を放棄し、内面を深く掘り下げるなかで詩を書いたり(アビラの聖テレジア)、自分の見た幻覚を絵に描き、音楽を作曲したり(ビンゲンのヒルデガルト)することで、中世から近世にかけての女性としては考えられないほどの自由を得て、創造性を発揮したことで知られる。
2020年代半ばに、近代以前のカトリックの自己探究の方法が、33歳のロザリアによって提示されたことをどのように受け止めれば良いのか。ほんの数年前、いやおそらく昨年でさえも、若者の「自分探し」と言えば「アイデンティティ」の探求であり、ジェンダーやエスニシティや人種といった属性に強く紐づいていた。そうでなければ日本でも顕著な「セルフラブ」、「セルフケア」概念の流行に見られるように、最終的に「自分探し」は自己愛に帰着することが正解だとされていた。「LUX」ではむしろそのような「自己」理解は超えられていく。四章立てになった楽曲の第三章で、ロザリアは神の愛の近さに気づき(「La Yugular」)、相手への執着を自己愛に転じた後(「Focu 'ranni」)、持っているもの全てを捨てる(「私はジミー・チューを捨てる」「Sauvignon Blanc」)。続く第四章で彼女は「私は全てを許す」と歌い(「La Rumba Del Perdón」)、生の終わりの時点から自分を振り返る(「Memória」、「Magnolias」)。アルバムの終盤では、彼女はこの世を離れ、地上から浮かび上がっているかのようだ。
外側(=この世)から内面へ、そして内面から広大な外部(=神)へ開かれる魂の解放の遍歴を歌った「LUX」は、様々な媒体で2025年のベストアルバムに選ばれ、年末のチャートを席巻した。
ダイムズ・スクエアのヒップスターたち
同じく2025年、NYでは、カトリックの若者が中心となった前衛ムーブメントが終焉しつつあった。この前衛文化が興った場所は、チャイナタウンとロウワーイーストサイドに挟まれた地区にあり、「ダイムズ・スクエア」と呼ばれる。
元は長屋や工場だったレトロな建物が残るこの地域には、2010年代から新進のアート・ギャラリーが進出していたそうだ。その後2018年から、レストラン「ダイム」をはじめとする様々なレストランが路上にテーブルを出すと、Z世代を中心にヒップスターと呼ばれる流行に敏感な若者たちが集まるようになり、42丁目のタイムズ・スクエアを文字り「ダイムズ・スクエア」という地名が生まれた。コロナ禍のシャットダウンに逆らう意味も込め、この地では屋外パーティー、ポエトリー・リーディング、映画の上映会などが行われ活況を呈していたと言う。
ダイムズ・スクエアが様々なメディアから注目を集めたのは、ニューヨークという文化発信地の最新の動きだったからだけではない。むしろこの一角から発信される文化が、反リベラルを掲げる右派的な傾向を持ち、その若者への影響が、2024年のトランプ大統領再選を少なからず後押ししたと考えられたからだった。ニューヨークにも共和党支持者が住む地域が存在するが、マンハッタンの特にダウンタウンは、LGBTQカルチャーの拠点もあり、非常にリベラルな地域である。この地で一部のヒップスターたちはWOKE(ポリティカル・コレクトネスを重視する態度)の流行に反旗を翻して「表現の自由」を唱え、「反動的保守」を自認するようになった。ダイムズ・スクエアのイベントにはトランプ支持を意味するMAGAハットを被ったパーティー・ガールが出没し、民主党支持のニューヨーカーを驚かせた。その中心地の一つ、イベントスペース、ソブリン・ハウス(その名も「君主の館」)では、ピーター・ティールがシリコンバレーに広めたカトリックの思想家、ルネ・ジラールのドキュメンタリー映画の上映会や右派インフルエンサーのカーティス・ヤーヴィンの出版イベントなどが行われた。ソブリン・ハウスの主催者でテック業界出身のニック・アレンは、イーロン・マスクが始動し、多くの批判を浴びたDOGE(政府効率化省)の成果を賞賛するパーティーをワシントンDCで主催したこともある。ほかにもダイムズ・スクエアの文化は、SNS上でミーム化し、大統領選挙前から流行した「tradwife(伝統的な妻)」風のファッション、そして何よりカトリック回帰と連動していた。
ソブリン・ハウスの常連にはカトリックが多く、彼らは日曜に聖パトリック大聖堂へ集い、午後7時のミサ(通称「ホット・ミサ」)に参加していたそうだ。カトリックの儀式性や道徳は、あらゆる価値が相対化され、ポリアモリーやオープンリレーションシップなど何でもありになったNYの急進的な若者文化への反動だった。中心人物の一人、女優のダーシャ・ネクラソワは2018年に始まった「Red Scare」(「赤狩り」の意味)というポッドキャスターの共同ホストとして知られている。ダーシャは、いわゆる「キャンセル・カルチャー」によって「表現の自由」を抑圧する左派の狭量さや道徳を軽視する態度に幻滅し「新右翼」の流れに協調するようになったと言う。2024年にはトランプ支持を明らかにし、時折神学的なテーマを扱いつつ、極右の陰謀論者アレックス・ジョーンズらをゲストに招くダーシャたちのポッドキャストは度々炎上しながら人気を博し、2024年のクラブカルチャーを席巻したミュージシャン、チャーリーxcxがそんなダーシャをモデルに「Mean girls(意地悪な女の子)」を制作したというエピソードもある。ダーシャは自分が反動的であることを認めつつも、2016年の大統領選で民主党のバーニー・サンダースを支持していたことからもわかるように、決して右派を自認することはない。
もう一人、この運動を代表するカトリックのインフルエンサーにマイルズ・ヤードリーがいる。サロメという洗礼名を異名にしていたヤードリーは、ニューヨークの複数のカトリック教会でオルガニストを務め、オルガンを教える傍らで、トランスジェンダーのモデルとして活躍していた。15歳の時にヤードリーはフィラデルフィア小児病院のジェンダークリニックをたった2回訪れただけでアンドロゲン遮断薬を投与され、後にエストロゲンも投与されたと言う。そして2024年にホルモン治療の影響が疑われる下垂体腺腫(脳腫瘍)と甲状腺機能低下症が発見されたことを切っ掛けに、ヤードリーはホルモン治療を止めた。その後、病院を提訴したヤードリーは、自分はトランスジェンダーではなく単に「女の子っぽい男の子」なのではないか、アセクシュアルなのではないか、と揺れ動きつつ、Pariah the Doll名義で、ファッションや音楽、そして自身の信仰を発信し続けている。ホルモン投与をしている時期のインタビューでヤードリーは既に「自分はただカトリック教徒です。性別や性的指向、政治的立場といった他のレッテルで自分を定義することを拒んでいます」と語っていた。何よりまず自分は「神の子」なのだと。
属性やイデオロギーによるラベリングを拒む態度は、ダイムズ・スクエアのカトリックを自認する反動主義の若者たちの多くに通じ、彼らは自分たちを右派とはみなさず「カトリック」という肩書きだけを受け入れたいと言っている。トランプが大統領に返り咲き、共和党政権になった2025年、右派でいることはカウンター的な意味を持たなくなった。結果、ダイムズ・スクエアは政治色を薄め、以前ほどの求心力を持たなくなったとも言われている。ダーシャは、ポッドキャストのゲストに極右のインフルエンサー、ニック・フエンテスを呼んだことを理由に事務所との契約を切られ、ほぼ活動休止状態にあり、ヤードリーは一旦LAに移り住み、閉店したソブリン・ハウスに変わって同オーナーが開店したレインは、誰でも飛び込める場所ではなく会員制クラブになった。
そもそもダイムズ・スクエアカルチャーは、本物のアートではなく、前衛芸術の真似事に過ぎないと眉をひそめる人も多い。しかしながら、Z世代(厳密にはZ世代寄りのミレニアル世代も含む)が「カトリック」の名の下に、わかりやすい属性に自分を押し込む自己規定を拒み、自己を超えた存在(=神)を認め、自己検閲にがんじがらめになった「表現」を解放しようとしたこのムーブメントの意義は決して小さくなかったように思う。それはロザリアの「LUX」同様、セルフラブやセルフィー(自撮り)など、「自分(self)」に縛られた状態しか知らない若者世代が、伝統的形式を援用しながら自意識を超え、自己を解放する方法を編み出す挑戦だったようにも見えるからだ。
「アンディ・ウォーホルのようなカトリック」
ダイムズ・スクエアを代表するダーシャは「アンディ・ウォーホルのようなカトリック」と自称しているが、この表現は的を射ている。ウォーホルが抱えていた「自己」を巡る問題と実践(※1)は、改めて考えると非常に先駆的で、ダイムズ・スクエアのカトリック教徒たちは確かにその系譜上にあるように見える。
ウォーホルは小さい頃から振る舞いがどこか女性的でおとなしく、彼の生まれ育ったピッツバーグではいじめられっ子だったそうだ。彼は終生オープンにはしなかったがゲイだった。絵を描くことで社会との繋がりを作ることを学んだウォーホルは、偉大なアーティストになるという大志、今風の言い方では巨大な承認欲求を抱いてニューヨークに移住した。その後、20世紀最大の(少なくとも知名度において)芸術家となったウォーホルの成功については、もはや語るまでもないだろう。1960年代の寵児となった彼が採った方法は、当時すでに盛んになっていたアイデンティティの探求やゲイ解放運動のような政治活動ではなく、ウィッグとサングラスによって、クールで無性的(アセクシャル)な自身の虚像を作り上げ、その像をイメージを介して無限増殖させていくという方法だった。「誰もが機械であるべき」、「(自分を知るためには)僕の表面だけ見てください、裏には何もない」などの彼の有名な言葉が示すように、彼は唯一無二の自己の本質や内面の存在さえも否定していた。
2022年にNetflixで制作された「アンディ・ウォーホル・ダイアリーズ」(※2)でも示されていたように、何より自分自身を作品化し、流通させたウォーホルが、その後のポップスター像、とりわけ21世紀のインターネット普及以降に一つの職業にまでなった「インフルエンサー」を先取っていたのは間違いがない。無数のインフルエンサーたちがセルフォンを片手に自分の虚像=セルフィーに向かって話し続け、他者の承認を求めてネット上にばら撒き続ける2020年代。ウォーホルと交友のあった俳優のロブ・ロウは、ウォーホルが生きていたらきっと今の社会を気に入っただろう、と語っている。「まさに見せ物小屋(フリーク・ショー)だから」。
しかしこの極めて俗っぽく見えるイメージの増殖と拡散は、ウォーホルにとっては宗教的な実践でもあった。ウォーホルの母親はビザンチン・カトリック(※3)を信仰しており、彼もまた幼い頃からこの教派の典礼や芸術に親しんでいた。ウォーホルの代名詞とも言える反復するイメージもまた、その着想はビザンチンのイコン(聖像画)に由来すると言われる(※4)。人間の創意工夫を超えた「作られざる像」という理解に立つイコンは、画家の個性を許さず、西洋絵画のような一枚一枚の個別性がない。「全能者キリスト」、「慈悲の聖母」など、テーマごとに人物のポーズや表情など細かいルールが決まっていて、全く同じように描かれ、反復される。
マリリン・モンローやエルビス・プレスリーといった、セレブリティを描いたウォーホルの肖像画においても、像は無数に反復されることで、この世を超えた聖性を帯びる。有名人や名声に強い関心を持っていたウォーホルにとって、死後も永久に忘れられないセレブが「聖人」だったとしても不思議はない。ウォーホルは、初期のキャンベル・スープ缶にはじまり、自画像であれ、電気椅子であれ、自殺者であれ、性器であれ、像を反復し、しばしば壁にしきつめ、イコノスタシス(聖域を隔てる聖堂内の壁)のように展示した。いずれにおいても、試されているのは根本的には同様の実践に思われる。彼は、これらの像を版画(シルクスクリーン)によって反復することにより、具体的な個物を超えた、死をも超えた永遠のものへと聖化しようとしていたように見える。ウォーホルの作品が、強度がありながらも、作り手の意識や内面を感じさせない一因はここにありそうだ。キリスト教の土台には自分の意志を神に委ね、自己を犠牲にしたイエス・キリストの「自己無化(ケノーシス)」がある。彼の愛読書の一つは中世のトマス・ア・ケンピスが書いた『キリストにならいて』だったそうだが(※5)、彼が好んだイメージの反復もまた自己無化の実践の一種と言えそうだ。
ウォーホルのキリスト教信仰は、最晩年に彼のセクシュアリティと深く絡まり合いつつ、さらに複雑な形で前面化する。80年代後半、それまで性的放埒を謳歌していたニューヨークのゲイコミュニティをHIVウィルスが襲う。ウォーホルは、多くの身近な友人たち、そして1986年には恋人をAIDSで失うことになった。恋人の逝去直後に彼は、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を描く仕事を引き受ける。そして翌年の1987年、このシリーズをレオナルドの「最後の晩餐」があるイタリアのミラノで公開した直後に、ウォーホルは持病を悪化させ、手術後、帰らぬ人となった。
アンディ・ウォーホル美術館キュレーターのジェシカ・ベックの論考(2018年)によると、ウォーホルのホモセクシュアリティと信仰、特にAIDSとの関係は、死後約30年の間、多くの研究者や評論家が触れることを避けるタブーだったのだそうだ。ベックは「最後の晩餐」シリーズを、「信仰と性的指向の間に感じた葛藤の告白であり、最終的には、この時代に同性愛者コミュニティが被った苦しみからの救済を求める嘆願」として読み解いている。その解釈の中心にあるのは2022年に幸いにも日本で展示された「最後の晩餐(the big C)」(1986年)だ。中央の大きなCは「キリスト(Christ)」のCであると同時に当時のAIDSの別称だった「ゲイの癌(Gay Cancer)」のCであり、同様に中央にキリストに重なる形で描かれた巨大な「699」は『黙示録』の獣の数字「666」と性的な体位「69」を示しているとベックは読み解く。バイクもまた性的な含意を持つ。

これらの暗号を理解した上で迫ってくるのは、一見グラフィティ風でカラフルな本作が持つ圧倒的な不穏さだ。画面の右上にある製品のロゴから取られた眼光鋭いフクロウの目は、当時の世間が、AIDSの蔓延に苦しむゲイコミュニティに向けた眼差し、そしてキリスト教の保守派が主張した「神の裁き」を想起させる。また自分の受難を静かに受け入れようとしている、文字通り「自己無化」を体現するレオナルドのキリストの像は、ウォーホルの作品では様々な大きさで4回反復されているが、切れ切れに描かれ、呪詛のような文字「THE BIG C」や数字「699」が上に描かれたその姿は弱々しく、痛ましい。しかし同時にその広げられた手と優しい表情には、ウォーホルの切実な祈りが確かに託されているように感じられる。
ベックは「最後の晩餐」シリーズを、ウォーホルの「最も個人的で内面を露わにした作品群」と位置付けている。ビザンチン・カトリックは、一方で、ウォーホルに永遠や普遍を志向するための形式を与え、他方で、内面を志向するための形式を与えた。いずれにおいても俗なるもの、猥雑さは切り捨てられることなく、その全てが抱擁され、神に委ねられている。
(※1) ミシェル・フーコーがウォーホルと同年にエイズで亡くなったことを考えると、『性の歴史』で探究された「自己のテクノロジー」という主題もまた、ウォーホルの晩年の近い問題意識に基づくことに気付かされる。今後考えてみたい。
(※2) この番組では機械になりたかったウォーホルのコンセプトを汲む形で彼の声をAIで再現し、日記を朗読させるというウォーホル的な演出を施していた。
(※3) ビザンチン・カトリックとは、ビザンチン典礼に従う東方カトリック教会を指す。教皇の権威を認めつつも独自の典礼、伝統、統治構造を保持している。
(※4) 宮下規久朗『ウォーホルの芸術~20世紀を映した鏡~』 光文社新書、2010年、第二章。
(※5) 宮下規久朗、同書、最終章。
「アイデンティティ」の2010年代が終わって
2025年にポール・エリーが公刊した『最後の晩餐:1980年代のアート、信仰、セックス、論争(※6)』(未邦訳)が示したように、1980年代のニューヨークにはウォーホル以外にもキリスト教、とりわけカトリック文化を表現の基軸にした文化人たちがいた。アートでいえばSMや同性愛を躊躇なく被写体にしたロバート・メイプルソープや1987年に尿にキリスト像を浸した写真「ピス・クライスト」で一躍時の人となったアンドレス・セラーノが挙げられる。よりポピュラーなところでは1989年にマドンナが「ライク・ア・プレイヤー」をリリースしたのを思い出しても良いだろう。彼らは一様にカトリックが罪とみなすことを積極的に侵犯する形で自分の表現を拡張していった。カトリックは厳格に罪を定める教派であると同時に、「悔い改め」と「許し」で構成される告解の儀式を持つ。この結果的に包摂的な(端的に「甘い」とも言える)美的弁証法こそが、カトリック文化圏に芳醇な退廃的文化を育んできたのは間違いない。堕落を含めての美的秩序こそ、教義としては明言化されないが、カトリックの美学なのである。
潔癖主義の19世紀イギリスで華開いたデカダンスも、プロテスタント国では少数派の改宗したカトリックによって先導された。オスカー・ワイルドやオーブリー・ビアズレーは、当時の前衛として、薬物使用や性的実験とそこから生み出される芸術を追求した(※7)。ヴィクトリア朝中期まで、「pervert(道から外れた者・倒錯者)」という名詞はカトリックへの改宗者を指していたそうだ。驚くべきことに19世紀イギリスでは、本来は同性愛を厳しく禁じるカトリックが、性的規範から外れているという意味で大衆の意識のなかでは同性愛と紐づけられてもいた。こうした文化として清濁を併せ呑むカトリックの性質は、20世紀のプロテスタント国アメリカで、同性愛者のウォーホルやメイプルソープが、カトリックでい続けた理由と無関係ではないだろう。
19世紀ロンドンでは産業革命後の近代化とペストやコレラの流行が起き、1980年代ニューヨークではゲイカルチャーの興隆とHIVの流行が起きた。そして2020年代にはアイデンティティ・ポリティクスの先鋭化と世界的なコロナの大流行が生じたが、いずれにおいても急進的な文化の浸透と疫病の流行の後に、カトリック回帰が生じている(このメカニズムについては今後考えたい)。「宗教回帰」と聞くと、しばしば単なる右傾化や権威主義の回帰のように捉えられることも多い。が、カトリックの回帰がむしろ文化としては、表現の拡張や自己の解放に繋がっている点は見過ごせないように思う。それはロマン主義的反動と一言では片付けられない。政治的な意味での近代化ではカバーできない人間の根源的な欲望を示しているように見えるからだ。
ロザリアは「LUX」で自分自身の伝統であるカトリシズムに還ることから、かえって様々な異なる地域の伝統に開かれ、結果本作では13の言語で歌うという快挙を成し遂げた。古くからある「形式」がかえって、自分だけでは到達しえない自由と開放の術(すべ)を与え得るということは、個人の選択に重きを置く現代のリベラルな文化が見落としがちなことである。ダイムズ・スクエアがただのお洒落スポットになっても、2026年現在、ニューヨークのカトリック教会はまだ若者で賑わっている。未知の地平を切り拓く潜在力は、近代以前から続く伝統のなかに残っているようだ。
(※6) Paul Elie, The Last Supper: Art, Faith, Sex and Controversy in the 1980s, Farrar, Straus and Giroux, 2025.本書では、実際のカトリック教会とカトリック文化を用いたアーティストたちとの一筋縄ではないダイナミクスについて論じられている。表紙の写真は、エイズ解放パワー連合(ACT UP)が、ニューヨーク大司教区がエイズ患者支援で広範な活動を展開する中で、ジョン・オコナー枢機卿が堅持した性道徳に関する教条的な方針に異議を唱えた時のダイ・インの様子である。
(※7) Martin Lockard, Decadent Catholicism and the Making of Modernism, Bloomsbury, 2020.