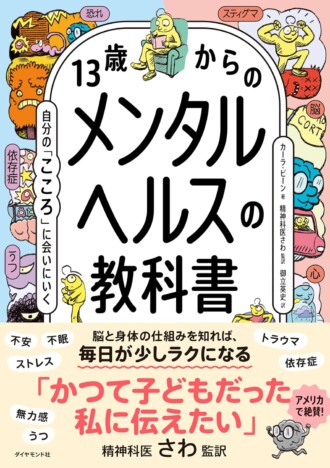長澤まさみ演じる“北斎の娘”は火事が好き? 映画『おーい、応為』の原作『百日紅』が描く恐怖とエロス
葛飾北斎といえば、海の波の大胆な描写が印象的な「神奈川沖浪裏」をはじめとする「冨嶽三十六景」のシリーズや、「北斎漫画」などの作品で知られる江戸時代の浮世絵師である90歳までの生涯で93回も引っ越したなど、変わった人だったと伝わっている。娘で父と同じく浮世絵師だったお栄(えい)を、北斎が「おーい」と呼んでいたことから、彼女の号が応為になったともいわれる。
北斎周辺は、たびたび物語の題材になっており、映画『八犬伝』(2024年。山田風太郎の同名小説が原作)では主人公の曲亭馬琴(役所広司)の話し相手として北斎(内野聖陽)が重要な位置を占めたほか、蔦屋重三郎を主人公にして浮世絵や戯作の世界を描く今年のNHK大河ドラマ『べらぼう』の後半には、若き日の馬琴(津田健次郎)や北斎(野性爆弾・くっきー!)が登場する。そして、長澤まさみのお栄を主人公にして永瀬正敏が北斎を演じる映画『おーい、応為』が、10月17日に公開された。
『おーい、応為』の原作は、浮世絵研究者の飯島虚心が著した『葛飾北斎伝』と、杉浦日向子の漫画『百日紅(さるすべり)』に収録された2話(「木瓜(ぼけ)」、「野分(のわき)」)だという。このうち『葛飾北斎伝』(1893年)は、画狂人を号した北斎の書簡や本人を知る人からの聞き書きをもとに彼の生涯を追ったもの。ただ、興味深い逸話が多く含んでいるとはいえ、明治時代の古い文章だから、今となっては注釈抜きでは理解しにくい。それに対し、『百日紅』(1983~1988年発表)は、浮世絵の文化が活気づいた時期の江戸の風俗を漫画に描いていてわかりやすい。『べらぼう』の視聴者などには、親しみやすい内容だと思う。
『百日紅』は、葛飾北斎、顎が出ているから父が「アゴ」と呼ぶ三女・お栄、北斎に傾倒し後に渓斎英泉(けいさいえいせん)となる池田善次郎の3人が、絵師として生きる日々を短編連作の形で描いている。各話の扉絵には実在した浮世絵作品の模写が多く掲げられ、本編でも浮世絵に通じる構図や描線などが散見され、江戸の雰囲気を醸し出している。『おーい、応為』では『百日紅』から2話を原作としてクレジットしただけだが、この漫画は全体で30話からなり、面白いエピソードが少なくない。
北斎は、なにか頼まれても素直には聞かないような変わり者だ。時おり彼の絵の代筆をさせていたお栄の絵が、彼女の名で売れたと知ると、この方が高く売れるだろうと今度は北斎自身が描いた絵に娘の名を記したりする。悪戯好きなのである。お栄も父に匹敵する変わり者であり、褒められたことではないが火事が大好きだ。どこかで火が出たと気づくと、夜中でも飛び出して屋根に上って見物したりする。女好きで春画で才能を発揮する善次郎は、北斎とお栄の住む部屋に居候して、周囲の騒動に巻きこまれる。
『百日紅』を読んでいて気づくのは、妖怪や幽霊を描いた絵や、男女が体をあわせた春画が登場する話が多いことだ。恐怖とエロスが、この世界の軸になっている。
「因果娘」では、女の両肩にそれぞれ手首の先だけが張りついていて離れない。昔、病身の母を背負い、医者に連れていったが死んでしまった。その時以来、母の手首が肩をつかんだままなのだという。「鬼」では、ある屋敷に頼まれて描いたお栄の地獄絵の出来栄えがよすぎたのか、怪異を呼び寄せてしまう。このように薄気味悪く恐ろしげな話が、しばしば出てくる。だが、「夜長」の場合、連れこんだ男が酔って階段から落ち、動かなくなったので死体を捨てにいくが、気を失っていただけで蘇るという滑稽譚になっている。
『百日紅』は、処刑されたさらし首を町で目にする時代を舞台にしており、死が間近にあることが表現されている。そのぶん、登場する人たちは、生と死の差を案外気にしていないかのごとく、あっけらかんとしている面がある。北斎など特にそうであり、娘による地獄絵に仏様を描き加えて怪異を鎮め、お栄はまだ半人前だとたいしたことではなかったようにいう。
また、男女間や性をめぐるあれこれをあつかった話も多い。自分の絵に色気がないといわれたお栄が蔭間(かげま=男娼)茶屋に行く「色情」や、善次郎がまだ大人とはいえない少女にまとわりつかれる「愛玩」などは、性行為への敷居が低い状況での相手との距離のとり方が、話の焦点になっている。なかでも興味深いのは、お栄が描いた美人画を買った隠居老人が、その絵と夫婦の盃をかわした「美女」だ。これは地獄絵の怪異を題材にした「鬼」と背中あわせのような話であり、老人は美人画の虜になり、絵のなかに自身の頭を入れてしまうのだ。
その場面もそうだが、『百日紅』には現実と幻想の区別が失われたような描写が、たびたび出てくる。恐怖やエロスは、個人の輪郭が揺らぐ体験といえるが、同作にはその種の体験が幾度となく出てくる。
北斎とお栄が住み、善次郎が居候する部屋には、彼ら絵師が描き損じた紙屑がたくさん散らばっており、ボロ屋なので雨漏りがする。雑然としていて隙間がある空間だ。誰かを締め出せるほど密閉された場所ではないし、客はためらいなく扉を開け、入ってくる。北斎たちは、隙間や出入りをさほど意に介さないらしい。
絵の世界に生きるそんな彼らには、生と死、性、現実と幻想といった、日常との境界線を無造作に越えることができる自由さがある。それが『百日紅』の魅力だろう。