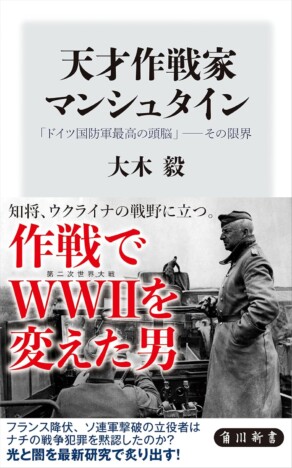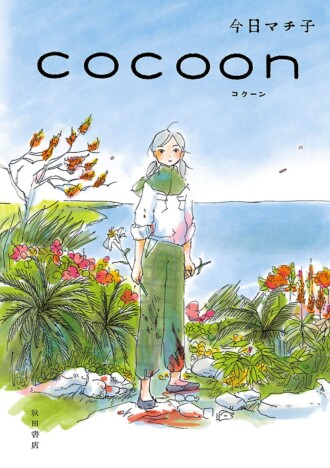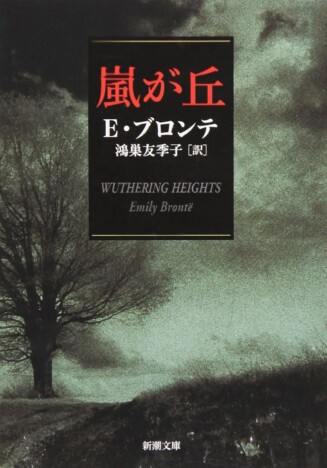【短期集中連載】戦後サブカルチャー偉人たちの1945年 第一回:戦わなかった兵士たち
やなせたかし、笠原和夫、川内康範……それぞれの戦争体験とは? 「戦わなかった兵士たち」の葛藤

笠原和夫:海軍下士官のまま終戦/映画『仁義なき戦い』『二百三高地』他の作品への影響
笠原和夫/映画脚本家
・1927年5月8日~2002年12月12日
・1945年の年齢(満年齢):18歳
・1945年当時いた場所:日本国内 広島県大竹町(現在の大竹市)
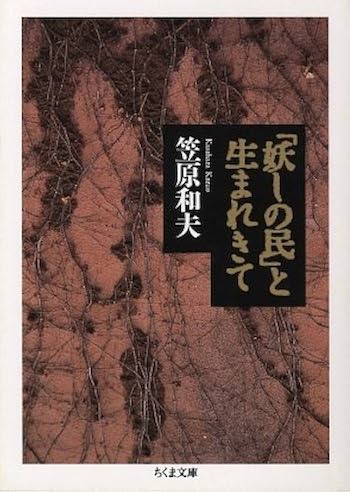
終戦時に軍人だった者たちのなかでも、笠原和夫はいわば最年少組で、ぎりぎり実戦に参加しなかった世代にあたる。その軍隊に対する思い複雑だ。
自伝的エッセイ『「妖しの民」と生まれきて』(筑摩書房)によれば、日米開戦時の直後、旧制中学生だった笠原は、真珠湾攻撃で戦死した九軍神(小型潜航艇の乗員)を英雄視し、岩田豊雄(獅子文六)の小説『海軍』を愛読する少年だったという。
笠原は転校をくり返しており、終戦前年の1944年には旧制新潟県立長岡中学に通っていた。同校は海軍元帥・山本五十六の出身校だけに、教師も先輩も海軍への入隊を促す声が強かった。喘息持ちの笠原は、医科専門学校に進学して軍医として軍艦に乗り込むことを望んでいた。ところが、長岡中学では予科練(海軍甲種飛行予科練習生)への志願を強制され、なぜか笠原が唯一の合格者となる。当時の価値観であれば栄誉だが、実際の少年飛行兵が「消耗品」だと理解していた笠原は、わざと友人とともに教師相手の暴力問題を起こして入隊を逃れた。ただ、この件が祟ったのか、一定の内申点があれば無試験で入れるはずの医科専門学校には合格できなかった。
1945年春、すでに満17歳を迎えて仮徴兵検査に甲種合格していた笠原は、そのまま陸軍に徴兵されるはずだったが、それでは「子癪に障る」ので、みずから自分の戦場を選ぶ。それは、海軍特別幹部候補生(下士官の速成教育コース)への志願だった。
長岡中学を卒業後、大竹海兵団に入団した笠原は、まず看護科を希望したが、視力がよかったので監督官によって無理やり砲科に変えさせられた。結局、笠原にとっての軍隊生活は終戦までの4か月のみであったが、この間にすっかり海軍に幻滅する。原因は上官の陰湿さや暴力だけではない、水兵長の階級を得た同輩が、ずっと歳上の水兵に暴行する姿を見て暗い気持ちになったという。笠原は戦前の軍隊について「ひとごろしが本業なのだから善人の集団であるわけもない」と書いている。
だが、この陰惨な経験が、後年の脚本家としての笠原の運命に大きく関わる。笠原の代表作たる映画『仁義なき戦い』シリーズの原作は、ジャーナリストの飯干晃一が、暴力団美能組を率いた美能幸三を中心に、戦後の広島抗争を描いたものだ。美能は当初、映画化に強く反発していたが、笠原が取材のため広島県の呉を訪れると、笠原より1歳上の美能も同じ大竹海兵団に属していたと判明して、両人は意気投合。そこから取材は順調に進み、1973年1月に公開された映画は大ヒットする。同作と第二部の『仁義なき戦い 広島死闘篇』には、戦場で死に損ない、捨て鉢な精神を引きずったまま抗争に明け暮れた戦中派の暴力団員たちの情念が色濃く反映されていた。

その後、笠原は『あゝ決戦航空隊』(1974年)、『日本海大海戦 海ゆかば』(1983年)など数々の戦争映画を手がける。いずれも綿密な取材を行い、『昭和の劇:映画脚本家笠原和夫』(太田出版)には、膨大な裏話が語られている。
笠原が脚本を手がけた戦争映画は、直截に反戦を訴えず、民衆を一方的な犠牲者として描くこともせず、それでいて末端の兵の目線で戦場の現実に迫っていた。『二百三高地』(1980年)、『大日本帝国』(1982年)では、温厚で知的な青年が、純朴に祖国日本の正義を信じて軍人となりながらも、過酷な戦場の現実に接し、戦友が悲惨な死を遂げるなかで、狂気じみた戦鬼と化していく姿を描いた。
みずから海軍に身を投じた笠原は、安易に自分を軍国主義に騙された善良な被害者とは認識していなかった。『昭和の劇』では、死を恐れなかった軍人たちの愚かさを認めつつも、そのストイシズムへの共感を語っている。一方で『「妖しの民」と生まれきて』では、戦時下の多くの日本人は単純な愛国者でも反戦平和主義者でもなく、ただ建前として天皇と軍隊に従っていただけで、敗戦後は米軍に抵抗することもなく、あっさりマッカーサー元帥を憧憬したと苛立たしげに記している。笠原にとって戦争と軍隊は、嫌悪すべきものでありつつ、極限の状況ゆえの人間の本音と覚悟を見せる場として、戦後の平和の欺瞞を突く精神の拠り所となっていたのだろう。