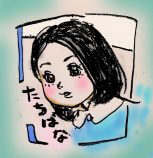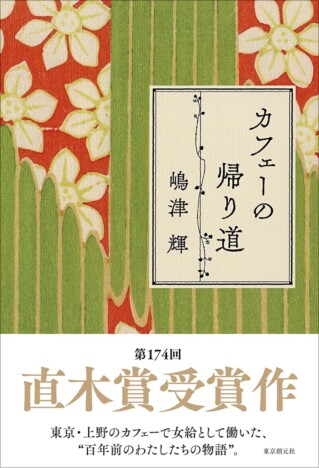町田そのこ、孤独死した老人の人生を描くことで得た視点 小説『わたしの知る花』インタビュー

これからも学び直し、新しい視点を身につけていけたら
――そういう意味で、登場する誰もが悪人でもなければ、善人でもないんですよね。善か悪かは、誰かの受け取った印象でしかなくて、それぞれただ懸命に生きてきただけ。平さんだけでなく、さまざまな人の生が、今作では多角的に描かれていた気がします。
町田:ああ、そう思っていただけたならよかったです。どんなに後悔していたとしても、人は過去を美しく見せたがるものだし、主観で歪んでしまうものがきっとある。登場人物が言い訳ばかりをしているように感じられたら、きっと読者の心には届かない。だから、ときには当人ではなく日記の言葉で語ることで、バランスをとるようにしていました。その人にいちばん近い場所から、直接的に描いたからといって、真実が浮かびあがるとは限らないんですよね。たとえ遠く離れていてもその人のことを想い続けることはできるし、触れ合える場所にいたとしても、距離をとることで冷静に見つめることができる。そういう、それぞれの適切な距離感も、描いてみたかったことの一つです。
――とくに二章はその感じが現れていましたね。平さんが刑務所に入る原因となった元恋人を介護していた女性の娘が母親の日記を通じて真実を知り、母との関係も見つめ直すという、あらすじにしてみるとややこしいですが、個人的にはいちばん胸を打たれました。
町田:母娘の関係は、私の書き続けてきた主題でもあるので、そう言ってもらえると嬉しいです。お母さんの日記は、書いていて楽しかったんですよね。「さみしいナ」とか「~なのよネ」とか、文体ひとつで、その場にいない彼女の性格がありありとわかる感じもして。
――あれ、よかったです(笑)。お母さんとは別行動をとりたい、と思っている娘との相容れなさも、文体だけで伝わってきて。
町田:血の繋がった家族だからいい関係が築けるというのは幻想で、むしろ三章のおじいさんは、奏斗という赤の他人だからこそ、ひとりの人間として誠実に接することができた。そして奏斗もまた、無関係のおじいさんだからこそ、その言葉を素直に受けとることができたんですよね。自分の孫に湯呑を投げつけるようなじじいが、こんなに優しい言葉をかけてくれるのか!というギャップもよかったのかもしれないけど(笑)。周囲の人間がどれだけ親身に言葉を重ねても心を動かすことができなかったのに、どうでもいい人の言葉が妙に突き刺さる、ということは往々にしてある気がします。
――湯呑を投げつけることについても、ラストに「そういうことだったの!?」という驚きが隠されていて、よかったです。隅々まで「一面的に描かない」心配りがされているな、と。
町田:四章に登場する、平さんの大家夫婦もそうですが、家族って、どちらか一方だけに原因があって責められる、ということは、実は少ないような気がしますね。被害者の面もあれば、加害者の面もある。だからこそ、私はこれまで、血のつながりになんてこだわらなくていい、家族というかたちはそれぞれが探っていけばいいんだ、ということを描いてきたのですが、じゃあ家族がすべて悪かといえば、やっぱりそんなこともない。育んでくれるもの、未来につなげてくれるものもきっとあるはずで、血の繋がりを肯定的にも描けたことは、今作で得た一つの手ごたえでした。
――だからといって、恋や愛を美しいものとして描きすぎないところも、町田さんならではという気がしました。四章の夫婦も、絶望と希望をとなりあわせに、これからもともに生きていくんだろうなと感じられて好きでしたね。
町田:迷いはしたんですよ。平さんの過去に隠されていた恋、そして愛は、やっぱり尊ぶべきものとして美しく描き切るべきなんじゃないか。人生の最後で一発逆転、平さんが報われることがあってもいいのではないか、と。でも……人生ってそういうものじゃないから。理想どおりにいくことのほうが少ないし、過去の後悔はたいてい、とりかえしがつかない。平さんは、噂されるほど危ない、だめな人ではなかったかもしれないけれど、いいことばかりをしてきたわけでもない。美しいフィナーレなどそうそう用意されてはいないものだけど、でも、別のどこかに希望を見出すことはできる。そんな物語になったらいいな、と思いました。
――多角的に描くという挑戦、ご自身の手ごたえはいかがでしたか?
町田:そうですねえ。最初は、薄汚くてよぼよぼしているけれど実はカッコいい素敵なおじいさん、という造形になるかと思っていたんですけれど、書き終えた今は「付き合うのはいいけど、生活力はなさそうだし、結婚はしたくないなあ」というのが本音です(笑)。でもそれは、結婚=男性に幸せにしてもらうものという意識があるからかもしれないとも思うんですよね。とくに昭和の時代、誰もが男女の役割にとらわれていたから、平さんも追い詰められていった部分がある。だからこそ……ラストで、ある女性が「わたしはわたしひとりで、しあわせになれる力のある女だった」と思う場面を書けてよかったと思います。「ならば、わたしがあなたをしあわせにすると言えばよかった」という、その気づきこそが大事なんだなと。
――それは、今の時代にも通じることですね。
町田:時代は変わったけれど、今もまだ、誰かに幸せにしてもらいたいと待ち続けている人はきっと少なくない。恋とか愛とかいうと、誰かとつがいになって、ともに生きていくイメージが強いけれど、必ずしもそばで寄り添いあうことだけが答えじゃない、ひとりでも幸せになれる恋や愛もあるんだってことを、この作品を通じて私も知った気がします。人との関係も、ジェンダーの問題も、そして恋や愛のかたちも、わかったつもりになって足を止めず、これからも学び直し、新しい視点を身につけていけたらいいなと思います。次は、今の時代に生きる人たちの人生を、どうしたら多角的に描いていけるか、私なりに挑戦してみたいと思っています。
■書籍情報
『わたしの知る花』
著者:町田そのこ
価格:1,870円
発売日:2024年7月22日
出版社:中央公論新社